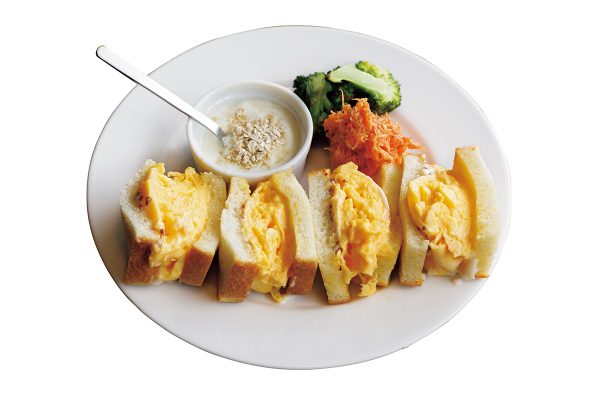自身のイタリア留学も、夫との出会いも、14歳の欧州旅の道中で知りあったお爺さんとの出会いがきっかけだ。人との巡り合わせを感じずにはいられないが、意外にも出会いに対しては閉鎖的だという。
「出会いに期待したり、意図して何かをするのは好きではなくて。だからこそ、印象深い出会いは記憶に刻まれているのだと思います」
昔から人が集まるところに行くよりも、野原で虫を探すことを好んだ。見知らぬ土地で生きるうえでも、虫の存在は大きかったそう。
「哺乳類と違って手懐けられる生き物じゃない。その土地で毅然と、抗わず、命を全うする頼もしい姿が、見知らぬ土地で感じる日々の孤独や緊張を癒やしてくれました」