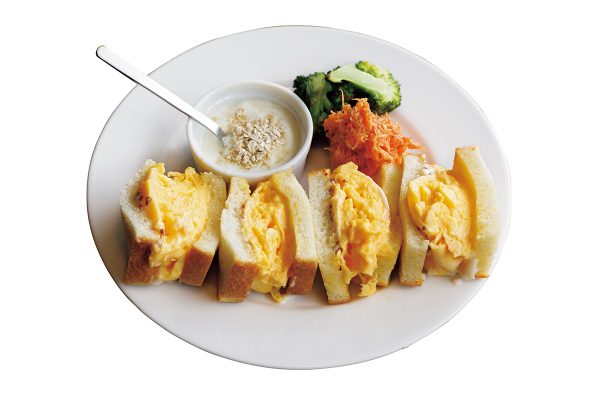「普段、私たちは明日死ぬかもしれないなんて考えながら生きていません。が、それがもし明日はないかもしれないとなったら、誰でもあまさずに生きようとするのではないか。そんなことを考えながらこの小説を書き始めました」
『棕櫚(しゅろ)を燃やす』著者、野々井 透さんインタビュー。「自分で書くものの枠を破りたかった」
- 撮影・谷 尚樹 文・堀越和幸
「自分で書くものの枠を破りたかった」

主人公の春野は父と5歳年下の妹・澄香の3人で暮らしている。ある日、父の体に変容が生じる。白衣のひとの説明によれば、何かが父の中に棲みついてしまったらしく、余命を1年と告げられる。
「棕櫚を燃やす」はこうした設定で家族3人が過ごす静かな時間が綴られる。著者の野々井透さんは、本作で第38回太宰治賞を受賞、これがデビュー作となった。
「家族って何だろうと思うことがあります。今は、介護は普通に社会化しているし、家事だってアウトソーシングで行える。このままいったら、100年後くらいには家族の機能そのものがなくなっているのではないかと考えたり……」
父の変容の説明を受けた数日後、澄香は春野に提案する。“これからの一年をあまさず暮らそう”と。
目にしたものをそのまま言える相手がいる。
頭の毛をなくして日に日に萎んでいく父、その父とこれまでに過ごした時間、今と過去の記憶をより合わせるように小説は進んでいく。
車を出して高速道路で遠出をすること、「上出来じゃない」「さもありなん」などの口癖、家の庭木が繁ってくると穴を掘って棕櫚を燃やすこと。
物語の後半、春野はいつもの川原の散歩道を、父、澄香と歩きながら思う。〈あそこに星がひとつ見える、だなんて言いたくなる宵を感じながら歩く。意味があってもなくてもいいようなことを言える相手は、私には父と澄香しかいない〉
「その辺に何が咲いているねとか、ただ見たそのまんまのことを言い合える相手がいるというのは、素晴らしいことだと思う」
家族とはそもそもそんな結びつきであるかもしれない。
〈やがてあなたのぜんぶが無くなった時、今、目にしているこの世界も無くなってしまうのだろうな〉と想像する春野が、いざその時を迎えて目に映すいつもの風景と、記憶に残る風景とではどんな違いがあるのか? 想像すると切ない。
小さな頃から小説を書くのが好きだった野々井さんは、この10年、小説教室に通っている。
「先生からは“人の評価を気にするのではなく自分の言葉で書きなさい”と常に言われていました」
本作を書くにあたっては、一度170枚ほど書いたものをすべて捨てて、初めから書き直したという。
「これまでの枠に収めるように書こうとしていたことをやめて、書きたいものにより近づきたいという思いで試行錯誤を重ねました」
人と向き合うのが苦手な春野は時に皮膚の下が生温かいもので“むるむる”する。詩のような手触りのある感覚表現が、すっと心に落ちてくる。次回作が楽しみな作家があらわれた。

『クロワッサン』1095号より

この記事が気に入ったらいいね!&フォローしよう
※ 記事中の商品価格は、特に表記がない場合は税込価格です。ただしクロワッサン1043号以前から転載した記事に関しては、本体のみ(税抜き)の価格となります。
人気記事ランキング
- 最新
- 週間
- 月間