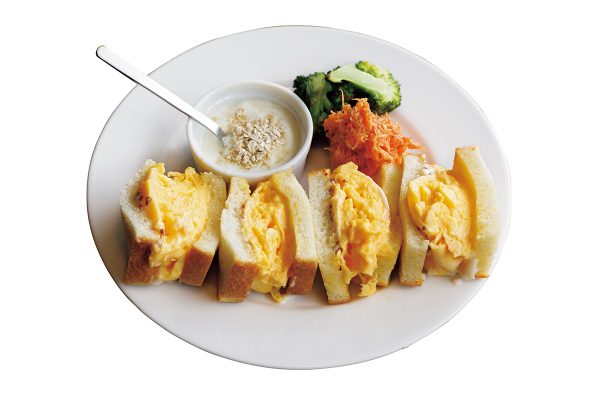本書は、ネネに見守られながら成長していく姉妹と、関わる人たちの40年間を縦横に紡いでいく。
そば屋の店主夫婦、律の担任教師、町の人たち。傍目にもおぼつかない暮らしを送る姉妹を、はじめ大人たちは遠巻きにし、親もとに帰そうとする。しかしひたむきに自立をめざす2人を、次第に受け入れ支えていく。全てをひと飛びに好転させてくれる救世主はいないけれど、背中をそっと支えるような少しずつの良心が、じんわりと温かい。
「優しいけれど、極端ではない親切。読者から見て『これなら自分にできないことはない』くらいになるよう心がけました。現実の人間って良い人ばかりでもないけど、すごく悪い人もそうはいない。その濃淡の間でできる程度の親切で、人って生きられるものなんです」
〈誰かに親切にしなきゃ、人生は長く退屈なものですよ〉
親の庇護のないタフな人生を歩む理佐と律。2人と関わる人々もまた、何がしかの欠落を抱えて生きているのだった。子を喪った過去、音楽家になる夢の挫折。誰もが痛みや欠落を抱えたまま、人生は続く。
「人に親切にしたので夢が叶いました、というのは違うと思いました。望んだ何もかもが手に入れられるわけではないし、だからといってそれは不幸ではない。何かを持たないままでいいし、諦めることがあってもいい。人生、すべてのカードを揃える必要はないですから」