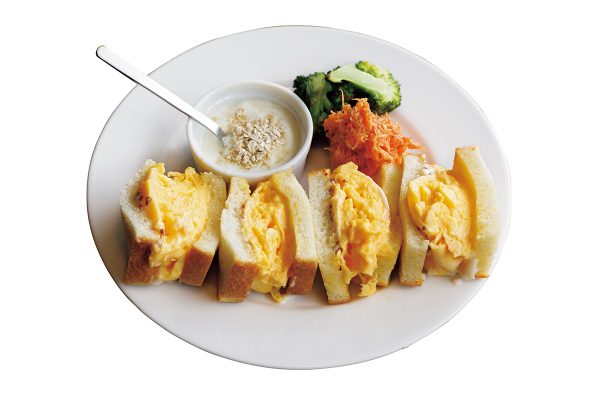不遇の女性を書く理由は?
「私自身が、ずっと安楽ではない状況にあった自覚があるんです。自分も子どものときにソノミみたいな状況だったし、新卒で就職したところもひどい会社だったし」
だからそういう主人公を書くのが自分には普通のこと、と言う。
「幼稚園でイジメてくる子とか、持て余した暴力的な金持ちのおじさんとか、普通の人が生きていて、そういう奸悪者に出くわす確率ってとても高いじゃないですか。そういうときに、どううまく逃げるかを書くことには、意味があると思うんです。たぶん私が読者として読んだときに、『ああこの人も苦しんでいる。この人もこんな目に遭ったんだ』ということが分かれば、救われることもきっとある」