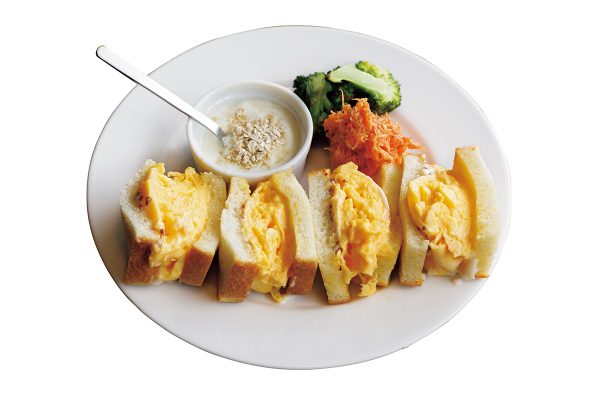「そうした具体的な情報がないまま物語は動かせるのか? ということを試してみようかと」
それに、と王谷さんは続ける。
「人の記憶って案外変なことを覚えていたり、逆に重要なことを忘れていたりしますよね。そういうのを混ぜ込むように書きました」
『君の六月は凍る』著者、王谷 晶さんインタビュー。「パターンを持たない10代の感情とは」
- 撮影・谷 尚樹 文・堀越和幸
「パターンを持たない10代の感情とは」

君の六月は凍った。
小説はこの一文から始まる。
「何の構想もないまま、ある日お風呂に入っている時にタイトルだけが頭に浮かんで、それに導かれるように書き出しました」と、作者の王谷晶さんは語る。
小説は「わたし」の語りで、その語りは30年前の「君」を思い返す記憶の物語だ。ある日、何かの媒体でわたしは君の名前を発見する。それをきっかけに、10代の頃とおぼしき君と過ごした時間が次々に蘇る。君とわたしはある田舎町に住んでいて、君にはZ、わたしにはBというきょうだいがいる。とのように作品では固有名詞が伏され、性別すら明示されない。
変えられない過去を人はなぜ思い返すのか?
町は小さく、わたしは昔から君の顔を知っている。君は小柄で、すれ違っても挨拶をせず、長い前髪の下から視線をよこすだけだ。わたしはそれを怖いと感じている。学校では異物扱いで、校庭の外れにある鳥小屋でよく一人で鶏のスケッチをしている。そして偶然その場に出くわしたことで、君と会話を交わすようになる。が、そのやりとりはどこかいびつだ。
「普段の私たちはパターンの選択で生きている気がしています。こんな時にはこんな対応、という。大人には経験の蓄積があるからそれで最適解を導けますが、子どもにはそれがない。だから言葉や行動がつい剥き出しになってしまう」
君と口をきくたびに、怒りや悲しみ、憎しみが胸に渦巻く。しかも普段無感情な君は、きょうだいのZといる時だけは一転して幼児のようにぐにゃぐにゃ甘える仕草で、こちらにあてこするかのようだ。自分の気持ちもわからないままにわたしは君への執着を深める。
「その君の態度もわたしの視点から見た君でしかないのですが……」
鶏は卵を産み、そのひなを君が盗み、家で飼い始めるあたりから物語の風向きが変わる。いじめの対象が君から私に移るのだ。
「自分でない他人とは基本的に不気味なものですが、大人になるとそれを想像力でカバーしたり客観性で補正しながらやっていける」
それが定まらない不自由な10代。王谷さん自身、小学生、中学生の頃は不登校の日々が続いた。
「自分のことを思い返すと、私自身も人とやりとりをするのにすごいエネルギーが必要でした」
変えられない過去を人はなぜ思い返すのか。書きながらその考えが何度も頭を巡った。そしてーー。
「人と人がぶつかるスパークみたいなものを書くのが、私にとっての小説なんだと思いました」
閃いたタイトルはどんな結末を迎えるのか? 痛々しくも純度のある、君への恋情が胸を突く。

『クロワッサン』1101号より

この記事が気に入ったらいいね!&フォローしよう
※ 記事中の商品価格は、特に表記がない場合は税込価格です。ただしクロワッサン1043号以前から転載した記事に関しては、本体のみ(税抜き)の価格となります。
人気記事ランキング
- 最新
- 週間
- 月間