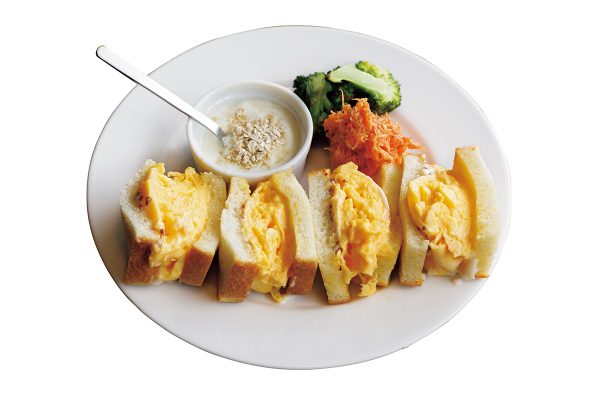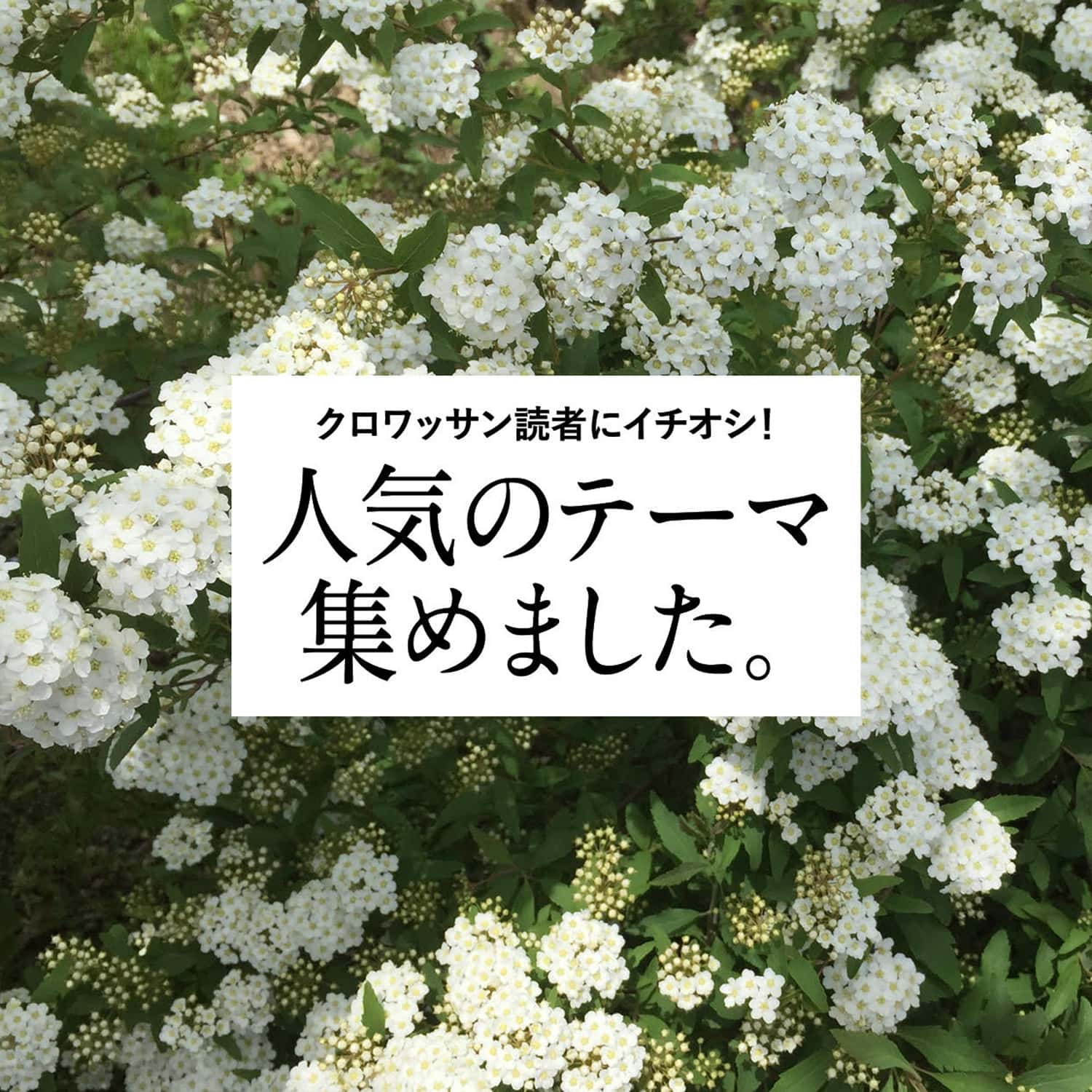からだ
平野レミさんの元気の秘密とは? 肩甲骨をほぐすストレッチや体操と肩甲骨を固めない生活習慣。
肩甲骨が柔らかいと肩や首も楽になり心も安定。
平野レミさんが整形外科医の遠藤健司さんに肩甲骨をほぐす簡単なコツを教えてもらいました。
平野レミさんが整形外科医の遠藤健司さんに肩甲骨をほぐす簡単なコツを教えてもらいました。
- 撮影・黒川ひろみ イラストレーション・サンダースタジオ 構成&文・片岡えり
写真ギャラリー




















この記事が気に入ったらいいね!&フォローしよう
※ 記事中の商品価格は、特に表記がない場合は税込価格です。ただしクロワッサン1043号以前から転載した記事に関しては、本体のみ(税抜き)の価格となります。
人気記事ランキング
- 最新
- 週間
- 月間