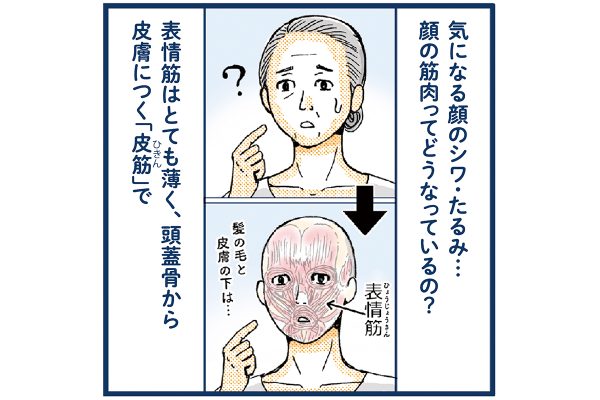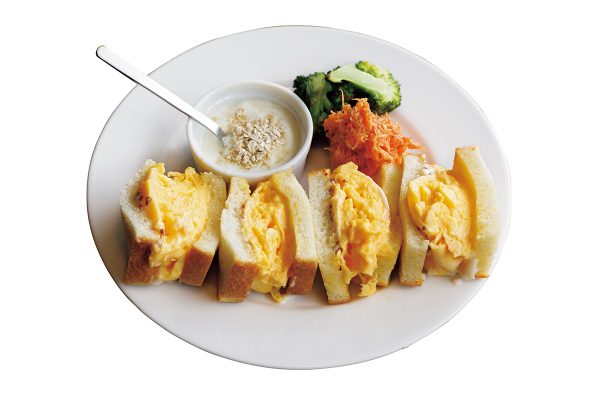「一番身近な人のことをびっくりするほど知らなかった。この本を書いて、そのことを実感しました」
そう話すジェーン・スーさん。約2年前、自身の父親を題材にした『生きるとか死ぬとか父親とか』を上梓した。
「私は24歳の時に母親を病気で亡くしているんですが、母がどんな人生を歩んできたのか、本人から話を聞いたことがなかった。母の母として以外の顔をほとんど見ずに終わってしまったことに後悔があって。父では同じことを繰り返したくないと思っていました」
ただし父親と正面から向き合うには時間が必要だった。母親という潤滑油を亡くしたことで、スーさんが30代の頃までは、会えば喧嘩ばかり。一時は絶縁することまで考えたという。
「でも、気づけば私も40代になり、父も年老いてきた。このままだと父が亡くなった時、すごく後悔するだろうと思ったんです」