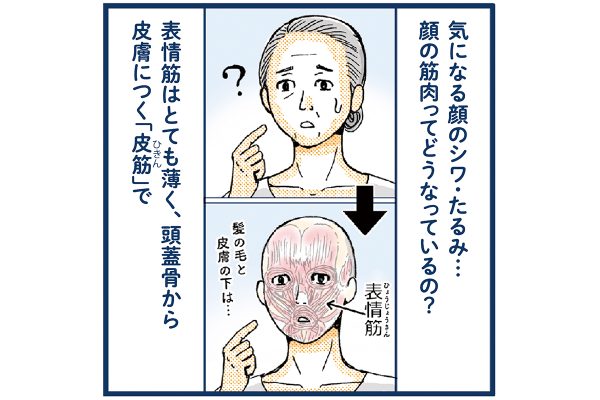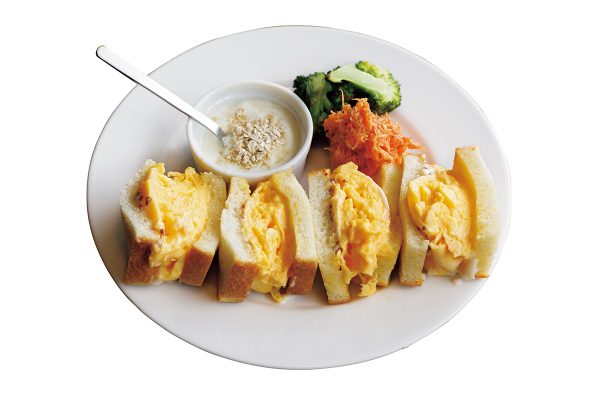「いろいろな母親がいる 母親にならない人も ダメな母親も 物語が始まる場所はいつも同じ 母親のおなかの中」。このモノローグからはじまるこの映画に、はなから惹きつけられた。フランスのパリを舞台に、「母」とは「母性」とは、という問いに、年代も立場も様々な人たちの幾つもの回答が投げかけられる。とはいえ、やっぱり母性が大切みたいなイイ話には決してなっていなくて、みんなそれぞれの立場で母との関係や、自身が母であること、母になることに、複雑な感情と悩みを抱いているのが、物凄いリアリティーだ。
母親であることは、 ずっと複雑なこと。映画『パリの家族たち』
- 文・小林エリカ 撮影・森本美絵


まさに私は昨今、気づけば無意識の「母親であろう」とする自分にもがき苦しんでいたので、映画を観ながら開眼した。老いて病気を患う舞台女優は若い男相手にこう語る。
「私が父親ならよかった 世間は男に寛大だもの 母親は影響力が大きすぎる 母親の視線にほんの少し無関心を感じたり失望の色があったら 子どもは深く傷つきいつまでも忘れない 母親は一生後悔し 子どもの挫折や失敗も自分のせいだと責める」

監督は、現代を生きるフランスの若者たちがホロコーストを捉えようとする『奇跡の教室 受け継ぐ者たちへ』のマリー=カスティーユ・マンシオン=シャール。母の日の由来と、オルセー美術館所蔵の画家ホイッスラーの「母の肖像」をリンクさせてくるあたり、冴え渡っている。
監督インタビューで「母親であることは、ただ子どもを産むことよりずっと複雑だと思います……」と語っているが、それが映画の端々にも滲み出て、光彩を放っている。

それにしても、フランスという国はもっと自由で進んでいるのかと思いきや、「母」や「母性」となった途端、やっぱり日本と変わらずまだまだ大変なんだな、というのも発見でした。つけ加えるなら、別に「母」なんかに興味がなくても、エスプリの効いた『ラ・ラ
・ランド』としても楽しめるということ。

『パリの家族たち』
監督、脚本:マリー=カスティーユ・マンシオン=シャール
出演:オドレイ・フルーロ、クロチルド・クロ、オリヴィア・コートほか
東京・シネスイッチ銀座、新宿武蔵野館ほかにて公開中。
http://synca.jp/paris/

小林エリカ
(こばやし・えりか)作家、漫画家。近著に訳書『アンネのこと、すべて』(アンネ・フランク・ハウス編、ポプラ社)がある。
『クロワッサン』998号より

この記事が気に入ったらいいね!&フォローしよう
※ 記事中の商品価格は、特に表記がない場合は税込価格です。ただしクロワッサン1043号以前から転載した記事に関しては、本体のみ(税抜き)の価格となります。
人気記事ランキング
- 最新
- 週間
- 月間