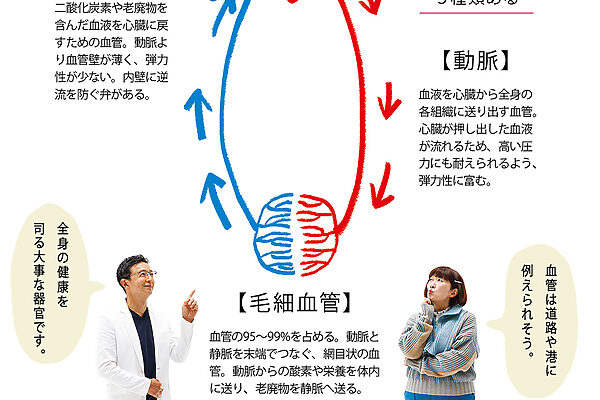生誕100年、今も魅了される「高峰秀子」という美学。
黒いドレスに真珠の二連のネックレスを身に着けたその人は、昭和の日本映画を代表する大女優・高峰秀子さんだった。
その佇まいはもちろん、名文筆家として遺した言葉、端正な暮らし方に、今も多くの人が魅了され続けている。
構成・越川典子 文・斎藤明美
「『高峰秀子』という美学」 あるいは「高峰秀子の美学」(文・斎藤明美)

前者は本誌面タイトルとして編集者が付けたもの、後者は今回の東京タワー大展示に私が付けたタイトル。高峰という人間そのものを「美学」と捉えてくれた点で、前者は光栄である。
だがそもそも「美学」とは何だろう? 高峰が無人島に一冊だけ持っていくとしたら「これ」と答えた広辞苑によると、(フランス語esthétiqueに中江兆民(なかえちょうみん)がつけた訳語で、旧訳語は「審美学」。自然・芸術における美の本質や構造を解明する学問。美的現象一般を対象として、それの内的・外的条件と基礎とを解明規定する。)
うーん、わかったようなわからないような……。ちなみに広辞苑を編纂(へんさん)した伝説の新村出翁(しんむらいずる)は高峰の大ファンで、『わたしの渡世日記』には、ナショナルの看板からポスターなど高峰グッズに囲まれ胸に高峰表紙の雑誌を抱えた、ご満悦の新村翁の写真が載っている。
高峰がまだ結婚間なしの頃、夫の松山善三と外出先から帰宅すると、お手伝いさんが「お留守の間にこういう方がおみえになりました」と一枚の名刺を差し出したそうだ。と、名刺を見るなり、松山が飛び上がって「えぇ! 広辞苑の人じゃないかッ」。すると高峰は驚く風もなく、「コウジエン? どこの中華料理屋だ?」と言って、さらに夫を驚かせたというエピソードがある。すぐに二人は、京都から上京している新村翁の宿泊先へ直行したそうだが。
この逸話には残酷な事実が隠されている。広辞苑という辞書の代名詞とも言える有名な辞書を、三十歳の高峰が知らなかったことである。
だから新婚時代、居間でやたらと新聞や雑誌をひっくり返している新妻を見て、松山が「何をしてるの?」と訊くと、「字を探してる」。つまり本を読んでいて読めない漢字があると、新聞や雑誌の中に同じ漢字を見つけて前後の文章から読み方を類推していたのである。松山はびっくりして――だいたいこの人は一つ年上の妻にいつもびっくりさせられ通しだったのだが――自分が旧制中学時代に使っていた辞書を新妻に与え、引き方を教えたという。
その時のことを高峰は私に、こう言った、
「もちろん辞書という物の存在は知ってたよ。でも私みたいなバカが触っちゃいけない物だと思ってた」
続けて言ったことは、
「とうちゃん(松山のことを私にはこう称した)がね、ボロボロの辞書をくれて、引き方を教えてくれたの。でも今は、二ページも違わずその字を引けるよ。引き算も割り算もとうちゃんが教えてくれた」

その嬉しそうな高峰の笑顔を見て、私は涙が出そうになったのを覚えている。
その三十歳で辞書の引き方も知らなかった女性が、私が出会った頃には「名文家」と呼ばれ、博覧強記(はくらんきょうき)の人となっていた。
その間の歳月を彼女がどう生きたのか――。
私は松山とこんな会話をしたことがある。
「結婚した時、かあちゃん(高峰)は既に大スターで映画界で最高のギャラをもらっていたわけでしょ。でもとうちゃんは助監督で月給12500円。農家の納屋の二階に、農林省に勤める弟と二人で住んで家賃を折半してた。かあちゃんに劣等感を抱いたことはないの?」
松山は穏やかに微笑みながら答えた、
「ないよ。例えば映画界が100メートル走だとするとね、僕がスタート地点に立った時、かあちゃんはもうゴールのテープを切ってた人だ。映画のことも、絵画、骨董、着物……全部、高峰が教えてくれた。高峰は僕の奥さんであると同時に、先生なんだ。敬愛する師でもあるんだよ。第一、彼女は人に劣等感を抱かせるような人じゃないことは、君が一番よく知ってるだろう」
これが、高峰秀子の美学である。
小学校に通算一か月しか通えない境遇に置かれても、玄関の三和土(たたき)で椅子を投げつけるような養母から毎日ハラスメントを受けようとも、顔も知らない十数人の親戚から金銭製造機のように扱われても、自分は女優という仕事に向かないと心底思っても、不平不満の一言も口にせず、いつかは自分の望む自分になるんだ、本当の自分を取り戻すんだ、それだけを心に秘めて、毎日カメラの前に立ち続けた人である。
ある日、高峰が台所の流しでサラダ菜を洗っていた時、くっついて甘えている私に、何を思ったか、こう言った、
「かあちゃんは子供の時から働いて働いて……だから神様が可哀想だと思って、とうちゃんみたいな人と逢わせてくれたんだね」
私はハッとして高峰から身体を放し、彼女を見た。
何と美しい横顔だったことか――。
評価を求めない。

デビューした五歳から引退する五十五歳まで五十年間、撮影を無遅刻無欠席で通した人である。
「ある朝ね、前の晩から熱が出て、さすがに今日は撮影を休ませてもらわなきゃいけないなと思ってたら、電話がかかってきて『今日は雪がひどいから撮影は中止です』。大雪だったのその日は。欠席にならなかった。だから無遅刻無欠席」
ちょっとおどけたように高峰は微笑んだ。
五十年である。撮った映画は三百本を超える。軽く微笑むどころの話ではない。
これが高峰秀子の美学である。
たとえば、夫の友人が三陸から名産の塩漬けワカメを送ってくると、洗って塩をとり、日当たりのいいベランダに新聞紙を広げて干す。
夫が香港で仕立てたシャツのボタンを全部とって、自分の気に入ったボタンに付け替える。
普通はその有名人形作家が送ってくれたら欣喜雀躍(きんきじゃくやく)して飾るであろう作品を、高峰は枝にとまった小さなニンフだけもぎ取って、木も枝も全部捨て、ニンフだけを特注したガラスの小さなドームに入れ、その足元に庭で見つけたセミの抜け殻を配する。
ハワイの自宅で過ごしていた時、知人女性が手作りの料理をタッパーに入れて「召し上がって」とくれると、自分で調味料を加えて味を調整する。
食卓の上の電灯の傘をこまめに拭く、夫と自分の合わせて五十足はある靴を懸命に磨く、冷蔵庫の中に輪染み一つ許さない、料理が出来上がった時には使ったボウルもザルも菜箸も全部洗って片付けてある……。
これが高峰秀子の美学である。

誰が見ていなくても、誰に評価されなくても、黙々としてやる。ハンコで押したように決まった時刻に起きて、決まった時刻に食事をし、間食は一切とらず、決まった時刻にベッドに入っていた晩年の生活。
つつましく静かで、確実、よく働く。
「年をとったなと自分で思ったのはいつ?」
私が訊くと、
「今日できることを明日に延ばした時」
こともなげに高峰は答えた。
「それは何歳の時?」
「七十四歳」
即答した。
私はそこらに穴を掘って入りたくなった。
嫌いな人とは食事をしない。原稿依頼の電話に「お断りします」「イヤです」。若い頃何度も共演したことのある有名俳優が死んだ時、映画雑誌がその人について書いてくれと電話をかけてくると、「あの人のことは嫌いですから書きません」。私はその発言を直に聞いたことはないが、高峰の古い知人の目撃談によると、本人に向かって「あなたには二度とおめにかかりたくありません」。
拒絶する。
これも高峰秀子の美学だと、私は思う。
多くの人から私は「高峰さんて怖いんでしょう?」と訊かれてきた。だがもしも高峰が怖いとしたら、二の句の継げないことを言う、拒絶する、そこではない。高峰秀子が本当に怖いのは、見抜くからである。人間を。
不幸な境遇にいた時も、幸せになってからも、高峰の“自分”は微動だにしなかった。
わがままとは違う。彼女の“自分流”は人に迷惑をかけなかった。人を押しのけなかった。長い年月、沈黙のうちに己の中だけで完成させたものである。
向上心と上昇志向、自慢と自負。その違いを高峰は黙って教えてくれた。冷徹と慈愛、情緒と合理性は、決して相反するものではないことを、身をもって示してくれた。
「人生で大切にしている信条は?」と訊くと、 迷わず、
「潔さです。潔くありたいと思っています」
他者と比べず争わず、外に評価を求めず、世間を基準にせず、常に己自身と闘い、問い続ける、「私は最善を尽くしたか?」と。
高峰はどうやってそんな自分になっていったんだ? 彼女が死んだあとも、私は考え続けている。そしてふと、司馬遼太郎(しばりょうたろう)先生がまじまじと高峰の顔を見ながら言った一言を思い出す。
「一体どういう教育をしたら、高峰さんのような人間ができるんだろう……」
私にわかることは一つだけ。今ある自分は自分自身が作り上げたもの。親のせいでも誰かのせいでもない。人生も同じ、満足だろうがこんなはずじゃなかったと思おうが、作ったのは自分だということ。それだけである。
一流の人間には「鬼」が棲む。
あなたの中に鬼はいますか?
生誕100年記念イベントが始まります。

●大特別展『逆境を乗り越えた大女優高峰秀子の美学』
3月28日~5月6日
東京タワー1階 RED°TOKYO TOWER特別会場
● 『巨匠が撮った高峰秀子』写真展
11月9日~12月8日
東京都写真美術館 地下1階展示室(予定)
●特集上映 高峰秀子[少女スタア時代篇]
〜4月27日 東京・ラピュタ阿佐ヶ谷
●斎藤明美連続講座
5月18日、6月22日、7月20日、9月21日、10月19日
東京・江東区古石場文化センター (6月は映画上映のみ)
● 『高峰秀子の映画と結婚』(仮題)
11月~2025年1月
神奈川・鎌倉市川喜多映画記念館
映画上映、展示、斎藤明美トーク&サイン会
● 『高峰秀子を未来へつなぐ』展(仮題)
2025年1月~3月 東京・港区立郷土歴史館
『クロワッサン』1114号より
広告