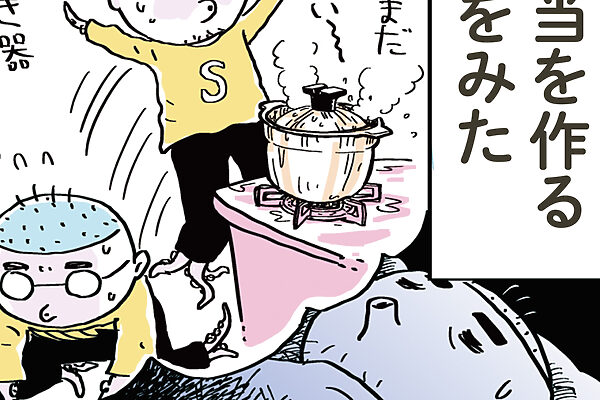『如何様(いかさま)』著者、高山羽根子さんインタビュー。「本物と偽物の境はどこにあるのか」
撮影・黒川ひろみ(本)谷 尚樹(著者)


時代は敗戦後。一人の画家・平泉貫一が戦地から戻ってきた。が、どうもおかしい。というのも、その顔は印象も輪郭もまるで異なる別人のそれだからだ。
この男は本当に本物なのか? 貫一と懇意にしていた美術系出版社の編集部員・榎田の依頼を受けた“私”は、戻ってきた男の正体を暴くべく動きだす。
「さる哲学者の思考実験で“スワンプマン仮説”というのがあります。ある男が雷に打たれて死にます。が、その雷の作用で近くにあった沼(スワンプ)から瓜二つのコピーが復活する。見た目だけではない、持てる知識や記憶まで同じ。であるなら、その人がその人たる理由とはいったい何か? という命題につながるのですが、その考え方が、本作を書くにあたってひとつのヒントになりました」
戦地から復員した男はほどなく行方をくらます。女性記者である私は、その周辺を埋めるように、戦前の貫一を知る関係者と面談を重ねていく。妾であった喫茶店の女店主、仕事を差配していた画廊主、所属していた部隊の隊長や軍医……そして、妻のタエはたった一度の見合いで、貫一が兵役しているあいだに嫁いできたから、その記憶はいたって曖昧だ。
私たちが見ているものと現実に存在するものと。
「会う人、会う人が、微妙に違うことを話す。とはいえ、決して嘘をついているわけではない。人が人を語る、というのはそういう部分があると思う」
調査を進めていくうちに、やがて私は戦前の貫一が贋作を得意としていたという事実に突き当たる。こと戦時下においては贋作の必要悪というものがあった。人々に慰めを与える、あるいは本物の流出を防ぐのに役立つ、ということが、作中では画廊主によって語られる。
「たとえば複製画に感動をした子どもがいたとして、その感動は嘘になってしまうのか? 何が善で何を悪とするかは、実は非常に複雑で、本物も偽物もその境は曖昧なグラデーションの中にある無数の一点にすぎないのではないか」
復員した男をまま貫一として受け入れようとするタエは、ある種達観しているようにも見える。
〈人は、まったく同じものがふたつ以上あると、ひとつを本物、残りを偽物と決めないと落ち着かない生き物なのかもしれませんね〉
高山さんは学生時代に美大でずっと絵を描いていた。
「だからでしょうか? 自分の見ているものやことに、疑り深いようなところがありまして(笑)」
たとえば物と物の境目となる輪郭線はあくまで便宜上のものであって、現実には存在しない。であるなら、その周辺世界の写実を丁寧に重ねていけば、あえてアウトラインなどを引かなくともその物自体を描き出せるのではないか。
「自分にとっては、小説もまたそんなイメージかもしれません」
周囲の証言によってあぶり出されていく歪んだシルエットの虚実。ラストの情景がまた美しい……。
『クロワッサン』1017号より
広告