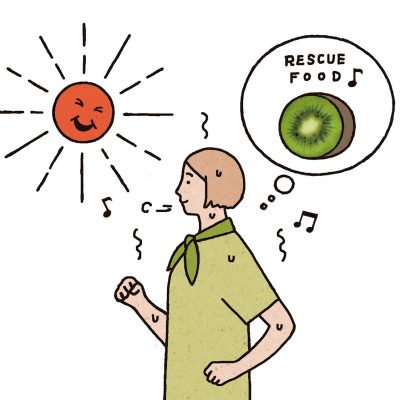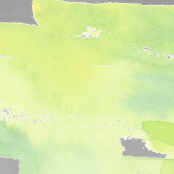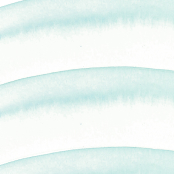『カヨと私』著者、内澤旬子さんインタビュー。「姿美しく好奇心旺盛、ヤギの魅力は尽きません」
文・遠藤 薫(編集部)
「姿美しく好奇心旺盛、ヤギの魅力は尽きません」

内澤旬子さんが小豆島に移住したのは8年前。東京の住環境による閉塞感に倦み、この地に家を借りた。しかし、庭先で動かしてみた草刈り機の大きな音に閉口。それならば雑草を食べてくれるヤギを飼えばよいと、迎え入れたのが雌ヤギのカヨだ。本書はカヨと内澤さんが、瀬戸内の穏やかな海が見える家で、心を通わせ生きていく日々を綴ったものだ。
カヨとの出会いは、ほとんど内澤さんの一目惚れ。〈ヤギがこんなに優美な形をした生き物だなんて〉〈カヨは、どこから見てもだれが見ても、美しいのだった〉
「会った瞬間、この子は私のプラテーロだと思いました」
と、20世紀のスペインの詩人・ヒメネスが隠遁人生の伴侶としたロバの名前を挙げる。
内澤さんはかつて、千葉県で豚を飼育したのちに食べた経験を『飼い喰い 三匹の豚とわたし』(角川文庫)に記している。人間と動物の関係性に真摯に向かい合う意志が並大抵ではないのだ。
そのときに培われた観察眼とコミュニケーションのスキルにより、1対1の暮らしのなかで内澤さんとカヨは魂の深いところで共振するようになる。〈カヨの中には人間が入っているんじゃないだろうか〉〈ねえカヨ、おまえが人間だったように、私は昔ヤギだったみたいだよ〉
そんな1人と1匹の女子の、文学的で耽美な、内澤さんも認める共依存的な関係は、カヨの発情と出産によって変化していく。儚げな少女から逞しいお母さん、カヨの成長を内澤さんはつぶさに追う。
私はカヨの飼い主になりたいわけじゃない。
「カヨが家族を持って、群れのリーダーになっていくのを一緒に体験できたのは面白かったです。母になったとき、子育てに疲れたとき、カヨがそれまでと違う表情をするようになったのもわかったし」
ヤギの数は増え、カヨは凛とした群れの長としてふるまうように。彼女を眩しく見上げる内澤さんの“ヤギになりたい願望”は一層高まるのだった。〈私もヤギになれたらいいのに。本当は飼い「主」になんかなりたくない〉
理想はカヨと対等になること、と内澤さん。しかし、「動物との関係って、法律では保護と管理の問題なんです。他の人を噛んだり畑を荒らさないよう、逃げないように柵で囲わなきゃいけない」。
飼い主として人間社会にいる以上、責任を負う立場になることは避けられないが、「でも本当は私も柵の中にいてヤギたちと一緒に寝そべって、『なんか柵できちゃってダルいよねー』『あっちの草食べたいよねー』とか言いたいんですよね」
発刊前は、ヤギの本を出すことに不安があったという。
「ヤギグッズってほとんどないし。犬猫はもとより、シロクマやペンギンにも負けてるじゃないですか」
けれど意外や、トークイベントには従来の読者に加えて、ヤギ好きが多く集うそうだ。
「それが分かってうれしくて」

『クロワッサン』1080号より