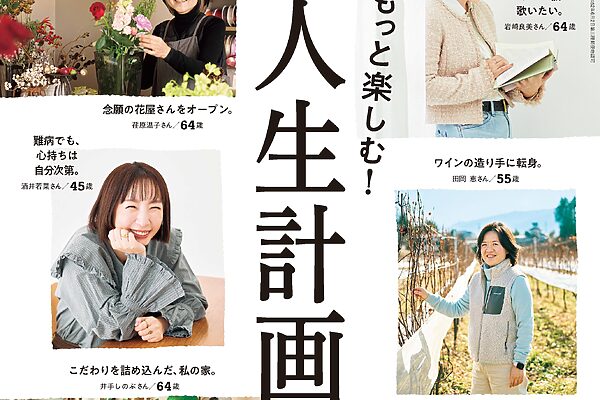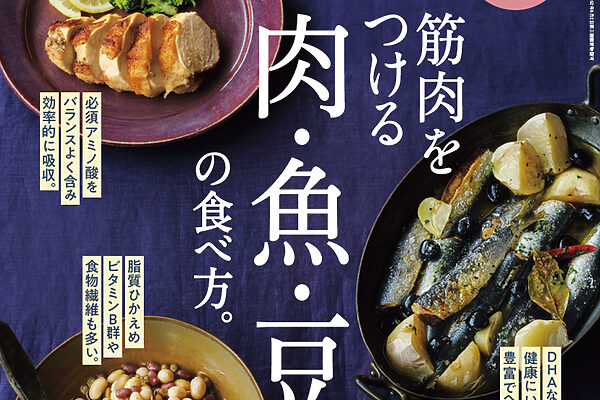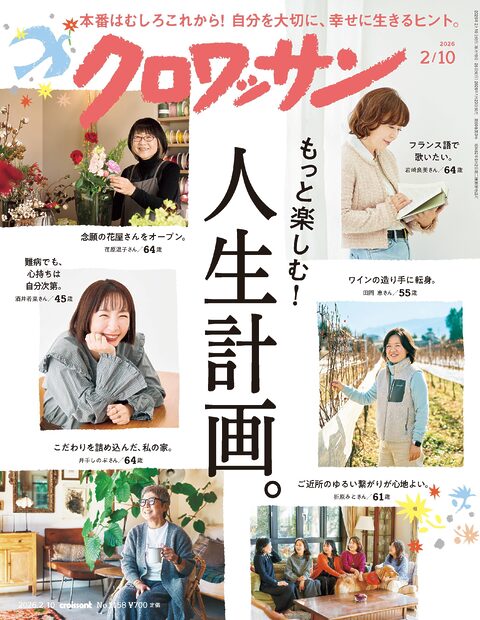感染症の専門家に聞く、インフルエンザの基礎知識。
毎年、冬に向けてじわじわと流行り始めるインフルエンザは、健康の難敵。対抗するにも、まずは敵を知らなければ!
イラストレーション・木下綾乃 文・黒澤 彩
インフルエンザには種類がある。
1シーズンの間に2度も3度も罹る人がいる。それは、インフルエンザにいくつかの「型」があるから。
「主には、A型とB型の2つ。一度A型が発症して治った人が、今度は違う種類のA型に罹り、その後B型にも感染するということは充分にあり得ます。秋ごろから早い時期にA型が先行して流行し、春にかけて後からB型というパターンが多いのですが、例外も」
B型は人と人の間だけで感染するが、A型は稀に豚や鳥からも人に感染する危険性がある。また、急な高熱や重度の合併症など、インフルエンザ特有の症状を引き起こしやすいのはA型のほう。
やっかいなことに、A型のなかにもさまざまな亜型(種類)があって、流行する亜型は毎年変わる。さらに同じ種類でも、発症した場合の症状の重さもまちまちだ。形を変えながら進化していくA型のウイルスは、ときに強い病原性を持つ新型となって世界に広まる。
「2009年に新型インフルエンザの世界的な流行があったのを覚えているでしょうか? あれもA型の一種で、もとはメキシコの豚の間で流行していたものが、豚から人へ、そして人から人にも感染したことから、『豚インフルエンザ』とも呼ばれました。このように、人が今まで経験したことのないウイルスを新型インフルエンザといいます。誰もそのウイルスに対する免疫を持っていないので、重症化しやすく、感染が一気に広がります」
2009年の新型は、翌年以降、季節性のものとして定着している。近年はA型のなかでも、この2009年に流行した型と以前からあった香港型が流行する傾向があるという。

02 / 03
広告