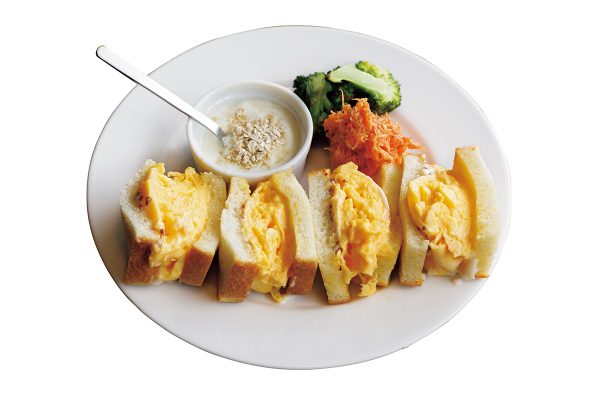ところで、子どもは思いのほか冷徹な傍観者だ。先生のずるさ、友だちの嫌なところ、大人たちのひそひそ話……小さかった私たちもずいぶん複雑なことがわかっていたものだ、と思い至るだろう。一方で水面のきらめきに心奪われる柔らかな感受性も備えている。
「詩というものは一応1行目から始まるんだけど、実は始まる前のほうがずっと大事なんです。なんでもそうなんじゃないでしょうか。植物なら、まだ発芽していない、土の中で眠っている時間。子どもでいえば、何も表現しないで、そして今おきていることがどんな意味を持つのかもわからず、ただ見て味わって聞いて生きている、そんな純粋な状態。それがどんなに豊かな時間であることかと思います」
“私が本当に詩人だったのはまだ何も書いていなかった子どもの頃”という趣旨の記述が本書にある。