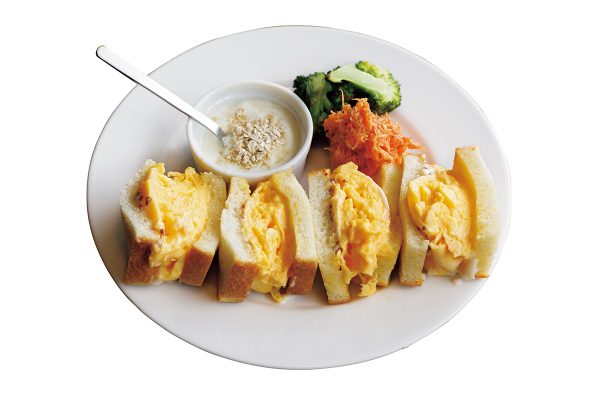アール・ヌーヴォーの代名詞的存在であるアルフォンス・ミュシャ。細やかな線で描かれた女性などのロマンティックな作風で知られるが、実は優雅な曲線も背景に描かれる円環の構図も、緻密な計算のもとで描かれていたという。
「ミュシャは『構図は画家の思いを伝えるスピーチである』という言葉を残しています。作品を見た方に、より効果的にメッセージが伝わるようにとデザインの研究はもちろん、知覚心理学も深く学んでいたことが近年の研究で明らかになってきました。そのため、没後80年目に開催される本展では、ミュシャ作品の“読むアート”という一面にスポットを当てたのです」と、監修者のミュシャ財団キュレーター・佐藤智子さん。
 アルフォンス・ミュシャ黄道十二宮 1896年 カラーリトグラフ ミュシャ財団蔵(C)Mucha Trust 2019 「目を引く美しい女性の顔、髪の波打つような曲線、背景の円環といったミュシャ様式が色濃く出始めた頃の作品です」
アルフォンス・ミュシャ黄道十二宮 1896年 カラーリトグラフ ミュシャ財団蔵(C)Mucha Trust 2019 「目を引く美しい女性の顔、髪の波打つような曲線、背景の円環といったミュシャ様式が色濃く出始めた頃の作品です」
全五章にわたる本展では、第一章から第三章までは繊細で華やかかつ特徴的な構図の「ミュシャ様式」と呼ばれるスタイルが、どのように形成・確立され、発展していったのかをたどる。
第四章では、ミュシャ作品に影響を受けて生まれ、’60〜’70年代の英米を席巻したレコード・ジャケットなどを含む作品を紹介。さらに第五章では、ミュシャ作品の影響が見られる日本のマンガ家やアーティストたちの作品がずらり。
 山岸凉子 真夏の夜の夢 「アラベスク」(『花とゆめ』1975年4月9号付録ポスター用イラスト) 1975年 カラーインク・紙(C)山岸凉子 「このマンガの連載を始めた頃にミュシャ様式と出合われたそうで、円環のモティーフなどにその影響がうかがえます」
山岸凉子 真夏の夜の夢 「アラベスク」(『花とゆめ』1975年4月9号付録ポスター用イラスト) 1975年 カラーインク・紙(C)山岸凉子 「このマンガの連載を始めた頃にミュシャ様式と出合われたそうで、円環のモティーフなどにその影響がうかがえます」
「今回の展示にあたり、水野英子さんや『24年組』と呼ばれる山岸凉子さんなど、’70年代に登場した少女マンガの作家の方々に取材をして、それぞれがミュシャ作品から何らかの影響を受けていらっしゃったと確認できたことから、このような展示が実現できました。当時の少女マンガの美的表現とミュシャ作品との共通点を探してみるのも面白いと思います」
19世紀末に確立し、現代の作品にも受け継がれるミュシャ様式を追う本展。馴染み深い少女マンガを見た後に、また“本家”の鑑賞に戻るのも一興。何度も反芻しながら、今に伝わるミュシャのメッセージを読み解く楽しみを味わいたい。