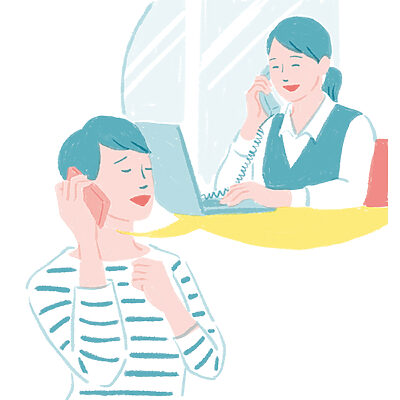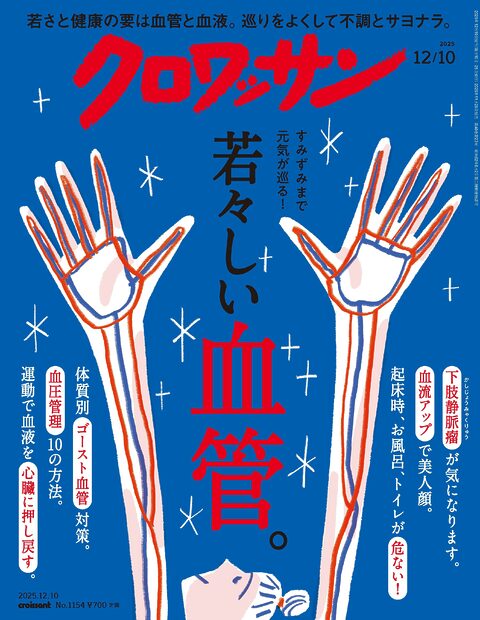食事で健康を保つ秘訣は毎日6杯の味噌汁にありました。
撮影・青木加代子

日曜の昼時、家族7人が食卓に集う大久保文靖さん宅を訪れた。大久保さんは、明治38年創業、長野県松本市で営む醤油・味噌の蔵元、「大久保醸造店」の3代目。大久保醸造店の醤油や味噌といえば、有名料亭や割烹でも愛用され、料理研究家・辰巳芳子さんも推薦する確かな味の逸品だ。
「うちの食事は美食じゃないよ。特別贅沢もしないし、地味なものばかりだから」と文靖さんは笑うが、テーブルに並ぶのは、新鮮な野菜をふんだんに使った、素朴ながら滋味溢れる料理の数々。キュウリやニンジンの漬物に、春菊のおひたし、ナスの煮物と、大皿にこんもり盛られた様子がなんともおいしそうだ。けれど、この食卓の主役は、なんといっても味噌汁。大人も子どもも必ずおかわりし、もちろん一日3食、1食につき2杯以上は飲むという。その味噌汁の鍋やお椀の中をそっと覗き込むと、まるで粉雪が舞うように軽やかに味噌が漂っている。

「ふわー、ふわーっと、溶いた味噌がいつまでたっても沈まず動いているでしょう? これは分子量が関係しているんです。味噌造りの工程の中で微生物がきちんと働くことで、原料の大豆のたんぱく質をズタズタに分解して、アミノ酸にしてくれる。しっかり分解されたアミノ酸は分子量が小さく軽いからすぐには沈殿しない。そしてこれが、うま味成分として風味や香味のもとになってくれるわけだ」
この「微生物の働き」こそが、大久保醸造店の味噌のおいしさの秘密だと文靖さんは言う。
「味噌というのは、簡単にいえば蒸した、もしくは煮た大豆に塩と米糀や麦麹を加えて仕込み、熟成させたもの。本来の味噌造りでは、無塩の状態で大豆そのものにどれだけ微生物の関与を受けさせたかがとても大事なんだよ。うちでは蒸した大豆一粒一粒に麹菌をつけて大豆麹にして、この段階で微生物にしっかり働いてもらっている。そのあとで塩や米糀・麦麹を加えるんだけど、いま、一般に流通している味噌の中にはこの工程を省いているものも多い。それでうま味が少ない分、米糀などの甘みで味を補うため、甘い味噌が増えているんです」
広告