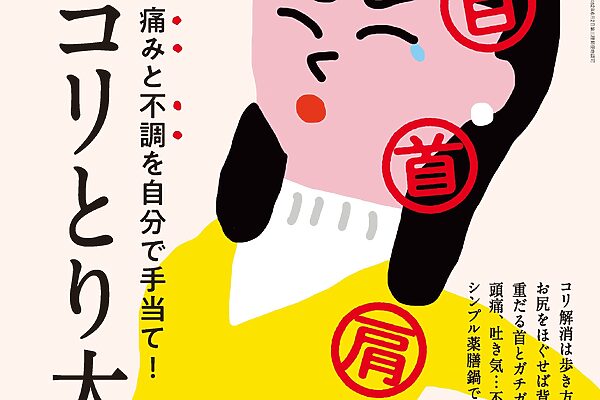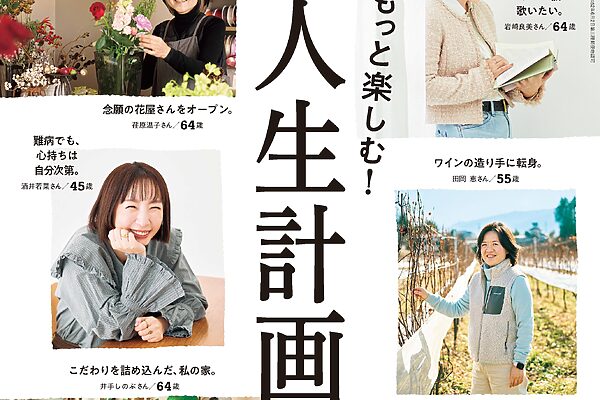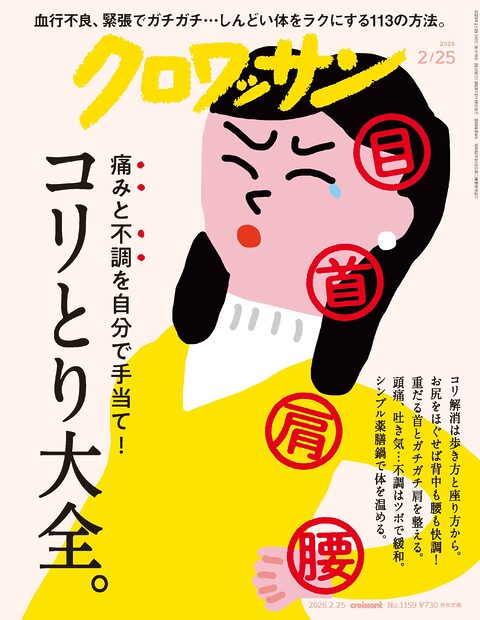消化吸収する力をいつまでも!発酵食品+αの腸活
スタイリング・佐々木カナコ イラストレーション・ワタナベケンイチ 文・熊坂麻美
人間の腸内には、約1000種類以上もの細菌が生息している。管理栄養士で、栄養学博士の蒲池桂子さんによると、発酵食品に含まれる乳酸菌や麹菌などの微生物は有用菌と呼ばれ、腸内で悪玉菌の繁殖を抑え、腸内細菌のバランスを整える働きがあるため、善玉菌と言うことができるという。
発酵食品は微生物によってすでにその成分が分解されているため、体内で消化されやすい。含まれている善玉菌は、善玉菌のエサになる食物繊維やオリゴ糖と一緒に摂ると、仲間を増やし、「短鎖脂肪酸」をつくり出す。
「短鎖脂肪酸は多くの種類がありますが、酪酸、酢酸、プロピオン酸が代表的です。腸のエネルギー源となり、腸の粘膜の傷を修復して免疫力を高めるなど、さまざまな健康効果があるとわかっています。善玉菌のエサとなる食物繊維のうち、不溶性食物繊維は腸の蠕動運動を活発にし、水溶性食物繊維は便が固くなるのを防ぎます。両方摂るようにしましょう」
腸内の善玉菌が多様なほど、健康が維持できる。発酵食品は決まったものだけでなくさまざまな種類を食べること、そして食品から摂った善玉菌は腸に定着しにくいため、少量を継続して食べることが大切。
「ヨーグルトやキムチ、発酵寿司などは、『生きた菌』を腸内に入れる意味で有効ですが、自分に合わない菌の場合はお腹を壊すことも。下痢をすると腸内細菌叢のバランスが乱れるため、食べ慣れない発酵食品の場合は少しずつ試してみて。一方、製造や調理の過程で加熱した発酵食品の菌は『死菌』となりますが、腸内で善玉菌を増やす働きがあります。酢や醤油、塩麹などの発酵調味料もいろいろ使ってみてください」

知ってた?こんな腸トリビア
人は腸に動かされている!?
ストレスで腹痛になることがあるように、腸と脳は影響を及ぼし合っている。この「脳腸相関」に腸内細菌が関わっているとされ、細菌が思考や行動の傾向にまで何かしら関わっているという研究結果も!
母子の腸内細菌は似る
自然分娩で産道を通る際、子どもは母親の腸内細菌に触れ、それらの菌が腸内に取り込まれるという説がある。成長過程で独自の腸内細菌を獲得していくが、母子の腸内細菌叢は類似性が高いとされる。
日本人はビフィズス菌が多い民族
日本人の腸内細菌叢はビフィズス菌の比率が高く、穀類や発酵食品を食べる生活が関連しているとも。ちなみにビフィズス菌の数は、乳幼児のときが一番多く、年齢を重ねるにつれて減っていく。
『クロワッサン』1133号より
広告