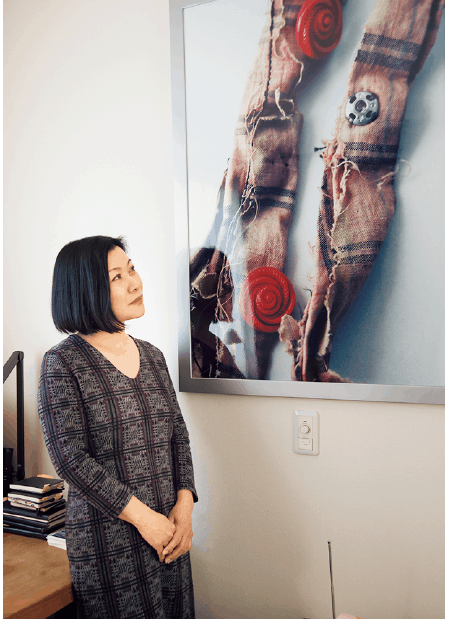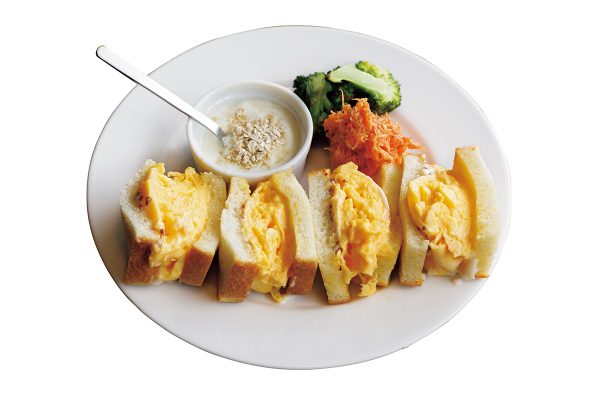44歳のとき『散るぞ悲しき―硫黄島総指揮官・栗林忠道』を上梓してノンフィクション作家になった梯久美子さんは、56歳になる今年『狂うひと―「死の棘」の妻・島尾ミホ』で読売文学賞と芸術選奨文部科学大臣賞を受賞した。しかし、文筆で生きていこうと決意したのは遅く、39歳のときだ。
「そんなに簡単に書く人になれるはずがない、って。詩とか小説とか、創作をしないと文筆では生きられないと考えていたんですよ。本の世界に強い憧れがあったので、できれば編集者になりたいと思ってました」
北海道大学文学部を卒業後、上京して出版部門のある上場企業の社長秘書になった。1年後、念願かなって学生時代に愛読していた『詩とメルヘン』の編集部に異動したのだが、1年で辞めてしまった。
「嫌な部長がいまして(笑)、ある日つまらないことで部長席に呼ばれて叱られたんですね。立ったまま叱責されているうちに、なぜか体が勝手に動いて、踵を返して自分の席に戻ってきちゃったんですよ。部長も唖然としてましたけど、そのとき周囲の世界が遠く見えて〝ああ、もうこの会社辞めよう〟と思いました」
24歳で退職。1986年のことである。退職金はわずか。貯金もなく、親戚もおらず、東京で一人暮らし。
「大学時代の親友が結婚して東京に出てきていたので、相談したんです。“じゃあ二人で今日から編集プロダクションやろうよ”と、学生ノリみたいな感じで、とりあえず名刺だけ作りました。文字を書いてお金がもらえる仕事なら、何でもやりましたよ。何も持たずに会社員の生活を手放したことがよかったんだと後から気づきました」
実力をつけてから独立しようとする人は多いが、ある程度キャリアのある人には小さい仕事を頼みにくいもの。しかし梯さんたちには、実力もキャリアもないことの強みがあった。
「小さい仕事をもらって、真面目に一生懸命やると、だんだん仕事が増えていくんですね。無我夢中で雑誌のコラムやチラシのキャッチコピー、ラジオの構成原稿から広告代理店のイベントの企画書まで、あらゆるものを書きました。そのうちインタビューの仕事も声がかかるようになって」