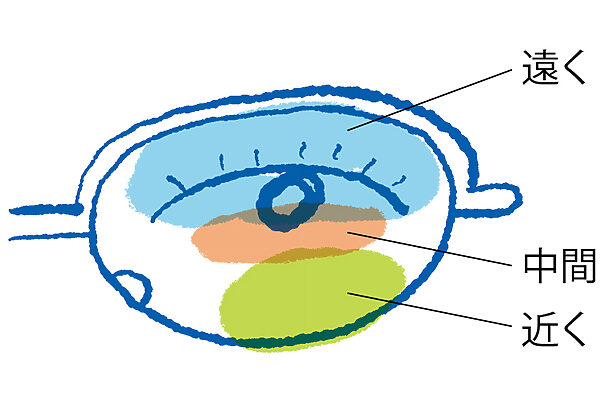『独り舞』著者、李 琴峰さんインタビュー。「苦難の果てに辿り着く、私は私の境地。」

撮影・中島慶子
李琴峰さんは台湾出身である。15歳の時に日本語を習い始め、2013年に大学院に入学するために来日。そして2017年に、実に初めて日本語で書いた本作品で群像新人文学賞優秀作を受賞するのである。
〈この一作を書かずにはいられなかった――。〉と帯にはある。
「日本の会社に就職して、ある日満員電車に揺られていたら、頭の中に“死ぬ”という言葉が浮かび上がってきました」
日本語の動詞で「ぬ」で終わるのは「死ぬ」だけである(古語を別として)。そう思った時に「ぬ」の持つ、何かぬめりのような語感を突き詰めてみたいと思った。
「この感じが小説の冒頭のイメージにつながりました」
主人公、迎梅もまた台湾出身で日本の企業で働いている。が、彼女にはつらい過去があった。セクシャル・マイノリティであることがきっかけで、ある「災難」に巻き込まれてしまうのである。女子校で育んできた大切な恋にも翳りが差し、運命は暗転する。
数年後、台湾から逃げるように来日した迎梅は、出会い系アプリで知り合った日本人女性、薫と引かれ合うようにもなるが、過去を明かすことですぐに破局。そして、あるトラブルを機に、自分の素性を会社にさらされ、ついに死を決意する。
「初めて日本語で小説を書くにあたり、まるっきり虚構を書くというより、なるべく自分自身から出発したいと思いました。もちろんほとんど脚色していますが……」
表題の“独り舞”に託されたイメージ。暗がりの中で独り踊り続けなければならない孤独や疎外感。それは作者自身のものでもある。
「台湾では戒厳令が解除された’80年代後半くらいから、それまで抑圧されていたものが解放されて、それを“移行型正義”と呼んでいます。そういう空気の中、セクシャル・マイノリティの文学のジャンルが確立されました」
一方、日本はどうだろうか。セクシャル・マイノリティを扱うときの手つきは、依然どこかぎこちなく、変にセンシティブであることは否めない。
「セクシャリティからくる生きづらさに目を背けたくないけれども、その葛藤だけを強調するのではなく、当たり前に生きている人間として描きたい」
研ぎ澄ましたような日本語の美しさを指摘すると、修士論文10万字を日本語で書いた成果です、と笑う。若き台湾の作家が、日本の文学の地平を切り開く。

講談社 1,600円
『クロワッサン』980号より
広告