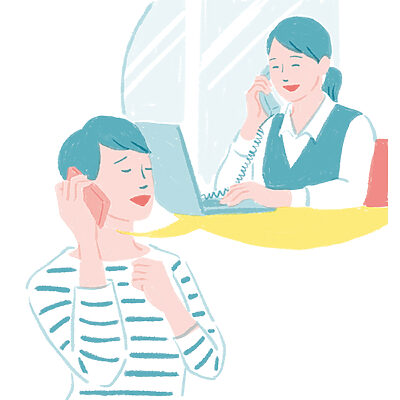【あの本を、もういちど。鴻巣友季子さん】書くことに対する姿勢を学んだかけがえのない河野多惠子さんの本。
撮影・岩本慶三 文・三浦天紗子
初の古典新訳を陰ながらずっと支えてくれて。

「朝とか夜とか関係なく、突然に電話がかかってくるんですよ。冒頭の“visit”を『「訪問する」と訳しちゃだめよ』とアドバイスをくださった時には、その箇所を“挨拶に行く”と訳したと説明したら、『わかってるじゃないの』と言われてホッとしたり」
『嵐が丘』の仕事を通して、河野さんと知り合うことができて、その出会いが『孕むことば』や『翻訳のココロ』といった文学エッセイの仕事にもつながったように思う、と鴻巣さん。
「不思議な縁を感じますね。河野さんに引き合わせてくれた人には、いまでも感謝しています」
鴻巣さん曰く「古典新訳というのはシェリーづくりに似ている」らしい。シェリーというお酒は、ソレラシステム(樽をピラミッド状に組む)によって作られる。組んだ樽のもっとも古い下の樽からまず抜かれ、減った分をそのすぐ上の樽から補充するしくみだ。新酒と古酒が混ざり合うことで、シェリー独特のこなれた風味が生まれる。
「最上段の一番若いワインの段はソブレタブラと呼ばれます。新訳はいわばその若いワインですよね。けれど、それはただ若いのではなくて、やがて80年以上に及ぶ邦訳の歴史と混じり合っていく。ソブレタブラのひとしずくになるのが、新訳者なのかなと思います」
いまも『小説の秘密をめぐる十二章』は、折に触れ、読み返している。鴻巣さんの持っている本には、付箋や書き込みがこれでもかというほど、ほどこされているのだ。
「特に第三章の〈作品はどう育てるか〉というところは翻訳の仕事を考える上でもとてもためになりました」
その章には、よい文学作品は嬰児が育つように全身的な育ち方をするものだ、という論が展開されている。
「100枚の小説にするとして、前半50枚まで書き進んだから“半分書けた”と考えるのは違うと。すでに書かれた前半の半分、つまり全体の水位25パーセントの部分が、実質的にはまだ書かれていない後半部分の25パーセントとうまく引き合わないと、いい作品は完成しないという部分には首肯しました。翻訳でも、その本のどこかに翻訳の腰が定まるポイントが必ずあるもので、それが見つかるまでとりあえず仮の訳語を当てて進めておくことはよくやります。枚数が半分まで来たから前半ができたわけではなくて、前半も後半が書かれてから完成するのだということは、しばしば実感しますね」
その50%理論を自分の年齢と重ねてみると、新しい覚悟ができた。
「『嵐が丘』を訳し終わったのが40歳のとき。それと同じ年に、子どもも生まれました。先の理論をポジティブに解釈すれば、40まで生きたってまだ半分の20歳。だったら私もまだがんばらなきゃと思えるんです」
最後に、鴻巣流の読書の楽しみを聞いてみた。
「河野さんも本の中で〈小説は人生の指針ではない〉〈おもしろいからこそ読み、今でもそうである〉と書いています。私も同じ。いかに生きるべきかを求めて読むのではなく、『読みたいと思うから読む』に尽きますね」
鴻巣友季子(こうのす・ゆきこ)●翻訳家。訳書にM・ミッチェル『風と共に去りぬ』(新潮文庫。全5巻)ほか。9月に東京・代官山で朝吹真理子さんとのトークショーを予定。
『クロワッサン』979号より
広告