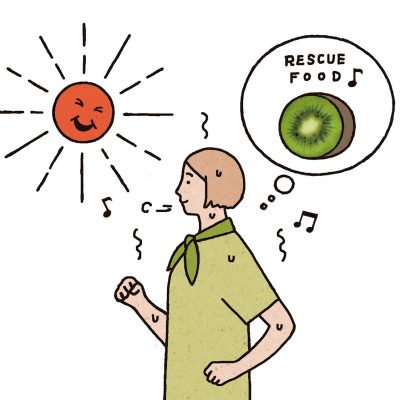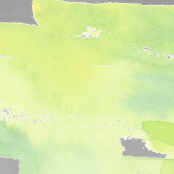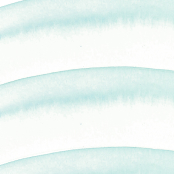『生きるとか死ぬとか父親とか』著者、ジェーン・スーさんインタビュー。破天荒で魅力的な父親を娘の視点で描く。

撮影・青木和義
女性が最大公約数的に抱える思考や現象を鋭く言語化し、共感を呼ぶ、ジェーン・スーさんの著作。
「いつも半径5メートル以内の自分のことを書いている」と自認するが、新作は、感覚的には半径1メートル? 最も身近な家族である父と、ふたりの親子関係を描く。
執筆のそもそものきっかけは、24歳の時に亡くした敬愛する母について、「母親」以外の顔を知らず、彼女の人生のことを何も聞けなかったという後悔。同じことを父で繰り返したくなかった。
「父の年齢も80歳で老い先が長いとは言えない。私も45歳になって、機が熟したんだと思います」
生前の母に「うちにはお父さんはいない、うんと年の離れたお兄さん」と称された父親は、女性の影が常にちらつき、株と事業の失敗で4億の借金。実家兼自社ビルを手放し、すっからかんに。その事態にただただ茫然自失な父に代わり、後始末を買って出ざるをえなかった娘。その夏の出来事を書くにはかなりの気力が必要だった。
「ただ、書かないことにはうちの家族のことは語れないので。でも書き終わっても、案の定、なんだやっぱりイヤな話だなって(苦笑)」
だが、一時期本気で縁を切ることも考えたというこの父が、同時になんとも魅力的な人物なのだ。戦時中のつらい話ですら笑い飛ばし、人を一刀両断で見切らない。「オレオレガチ」と友人が名付けた、娘にお金を無心する電話ですら、時にウイットに富み、どこか憎めない。確かに女性にモテそうだ。
「素直で愛嬌があるのが女性受けするんでしょう。そして金があろうがなかろうが、すごく人生を楽しんでる。そこは素晴らしいなと」
対するスーさんはいじらしく、「私は甘い、甘すぎる」とたびたび自戒しながらも「振る袖があれば」できる範囲の援助を惜しまない。
「自分でもいい娘だと思います(笑)。でも私が今稼げているのは親が稼いでくれたお金のおかげかなって。それに唯一残された肉親がお金が足りないって状況を思い出して、暗い気持ちになるのはいやなんで。自己防衛なんですよ」
と謙遜するが、愛の深さは読めば明らか。父娘ともに最愛の母の喪失によりバランスを崩した関係が、再び向き合うことで見えてきた新たな家族の形。最終章は、心に響く感動的な結びになっている。
「母が生きていたら、父との関係も違ったと思います。互いに歩み寄ることも理解し合おうとすることもなかったと。だからケガの功名だったのかなとも思いますね」

新潮社 1,400円
『クロワッサン』978号より