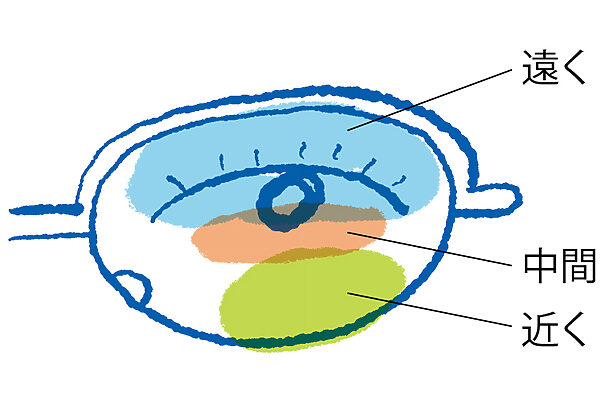『恋とか愛とかやさしさなら』著者、 一穂ミチさんインタビュー。「私はいつでも灰色の物語を書きたい」
撮影・TOWA 文・一寸木芳枝
「私はいつでも灰色の物語を書きたい」
一穂ミチ(いちほ・みち)さん
大阪府出身。2007年『雪よ林檎の香のごとく』でデビュー。’21年刊行の『スモールワールズ』が本屋大賞第3位、また同作で吉川英治文学新人賞を受賞し注目を集める。’24年『ツミデミック』で第171回直木賞を受賞。
日々、流れてくるニュースを前に、“自分だったら、どうするか”。そう自問することはよくある。では、恋人が盗撮で捕まったら? それもプロポーズの翌日に。本作ではページをめくるたび、その問いを何度も突きつけられる。
「信じる、ということの純度について一度書いてみたかったんです。きっかけは、辻村深月さんの『嘘つきジェンガ』に収録された[五年目の受験詐欺]という短編を読んだことでした。人を信じるって、こんなにも難しいんだと。それが心に深く残っていて」
物語の主人公は交際5年の新夏(にいか)と啓久(ひらく)。愛する人から求婚されるという新夏の人生最高の日の翌日、啓久が通勤中に女子高生を盗撮。なぜそんなことをしたのか「わからない」と繰り返す彼に、ふたりの関係はもちろん、周囲の人々にまで、その波紋は広がっていく。
「同じ女性として、性犯罪は絶対に許し難い。でも、もしも当事者になったとき、盗撮は罪であることは間違いないけれど、“一発アウト”まで踏み切れるだろうか。そんな危ういラインでの心の揺れ動きを書いてみようと」
答えが出ない問いを何度も何度も繰り返してもがく。
啓久の家族内でさえ、その反応は対照的だ。娘を持つ母でもある姉は絶縁を宣言。両親は示談成立後、もう問題は解決済みとばかりに振る舞う。また、新夏の高校時代からの友人、葵は〈問題のないカップルなんているわけない〉〈愛情って、総合的な判断のことでしょ〉とドライに意見。
啓久とて〈一回の出来心でニカ(新夏の呼び名)との間にひびが入って、母親は泣いて、父親は不機嫌になって、姉は怒り狂って、姪にも会えなくなった。リスクが大きすぎるって痛感した〉、だから〈コスパが悪い〉と言う。そして新夏自身も、怒り、迷い、悩み、泣き、ジェットコースターのように感情が揺れ動き、即座に「別れる」という選択には至らない。
「いろんなスタンスの人間を出そうとは意図しました。ただ、主人公は結論をその中から選ぶのではなく、きちんと自分で考えて答えを出す、というのも決めていて。でも、言語化するには難しい感情がたくさんあって、新夏の細かな感情の機微を描くのはとても苦労しましたね」
本書は新夏の視点で描かれる渦中を描いた前編、啓久の視点で描かれるその後の後編、2章で構成されている。特に啓久編では様々な場面で彼が犯した罪が暗い影となり、己につきまとう様子が描かれる。でも、啓久が“示談でラッキー”と、全てをチャラにできるような根が悪い人間ではないと読んでいてわかるからこそ、読み進めるほど苦しくなる。
「白でも黒でもないもの、割り切れずにこぼれ落ちてしまうもの。人生の中にたくさんあるそういったことを書くことで、読者にも何らかのフィードバックがあるはずだと信じています」
さぁ、あなたならどうしますか?

『クロワッサン』1132号より
広告