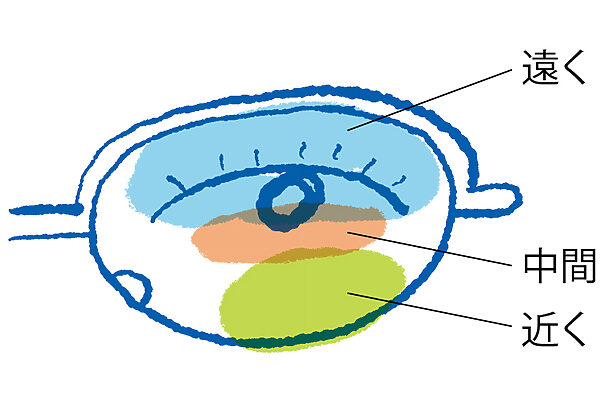認知症の母を受け入れられるようになるまで【助け合って。介護のある日常】
撮影・井手勇貴 構成&文・殿井悠子
母の認知症を治したかったーー。 受け入れて取り戻した母の笑顔。

内田家で一番のしっかり者だった睦子さん。豪傑で、細かいことは気にしない。時にくよくよすることもある夫の勝人さんの背中を叩いて励まし、娘の清子さんにとっても良き相談役だった。ところがある日、勝人さんから清子さんに連絡が入る。
「母さんの様子がおかしい。怒りっぽいし、何度も同じ話をする。時々『あなたは誰ですか?』と真顔で尋ねてくるんだ」
2017年、睦子さんの認知症状が家族のなかで明るみになった。
「最初は通帳がない、お金がない、と言い始めて。次に迷子。2020年6月頃は、記憶力が劣っている自覚が一番ある時。夜になると『家族に迷惑をかけるので私は実家に帰ります』と言い、出るはずのない亡き祖父母の家に何度も電話をかけては首を傾げていました。作り話や子どもの頃の話が増えたのもこの頃で。『あんまり過去の話をすると前に進めなくなっちゃうからね』と言う母だったので、戸惑いがありました」
自身が記録する介護日記を辿りながら、清子さんが話す。最近は、飲み物に食べ物を混ぜたりする“食べ遊び”が始まった。待ったなしに認知症は進んでいて、2カ月前までは大丈夫だったことができなくなる。
「母の認知症を治したかったんです」と、清子さん。清子さんは睦子さんの認知症を知ってから、介護の本を端から読み、市役所で認知症の講座があれば聞きに行き、その時に流行っていた民間療法を取り入れた。薔薇の香りがいいという記事を見つけるとアロマを焚いて、米ぬかがいいという話を本で読むと料理に使う。会話も正そうとした。

「母が何度も同じ話をすると、それさっき言ったよねとか、昨日は違う話をしていたよと諭して。父は眉毛をキュッとつりあげて『そうじゃないでしょ!』と強い口調で話すこともありました。すると決まってその日の夜、母は『家に知らない男性がいる』と言うんです」
否定をしない、会話を合わせる。介護のプロの人たちに、認知症の人への受け答えのアドバイスをもらい、ふと母が、愛犬に優しく怒らない接し方をしていたことを思い出した。
「何かの本に、認知症は死への恐怖を忘れさせてくれるものと書いてありました。人はいつか死ぬ。それならば、死を迎えるまでの間はつらいことはせず、にこにこ楽しく過ごしてもらいたい、と気持ちがスッと変わって。すると、認知症の母を受け入れられるようになったんです」(続く)
『クロワッサン』1124号より
広告