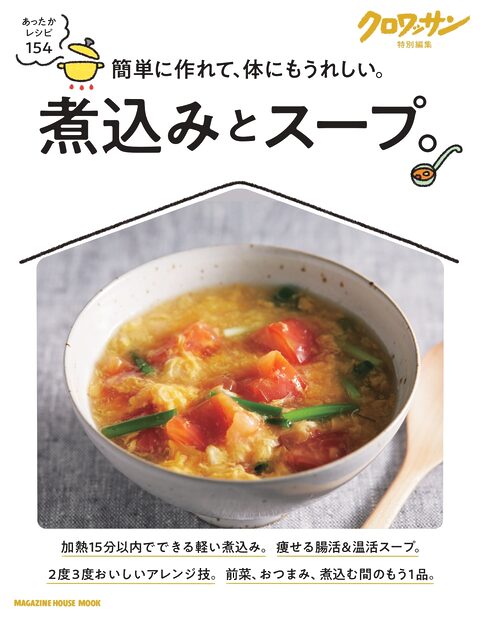『恐竜時代が終わらない』著者、山野辺太郎さんインタビュー。「太古から伝わる恐竜時代の物語です」
撮影・石渡 朋 文・鳥澤 光
「太古から伝わる恐竜時代の物語です」

ブラキオサウルスがジュラ紀の森を歩いて草を食み、アロサウルスが泉の水をごぶりと飲む。ステゴサウルスとアロサウルスが見つめ合い、ティラノサウルスの瞳に月明かりが映り込む。
中生代から現在まで、いくつもの時間の断片が重ねられ、小説の言葉によって地球史が貫かれ不意につながる『恐竜時代が終わらない』。
遠く時を隔てて存在した恐竜という存在に、「同じ地球に生きたもの」として幼い頃から親近感を抱いてきたという山野辺太郎さん。小説を書くにあたって最初にやってきたのは、種の違う恐竜同士が思いを通わせるイメージだったという。
「そこから、エミリオとガビノという男の子たちを結びつける感情や、マレナとフリオという2匹の恋のゆらめきが浮かんできました。それを語る恐竜と、さらにそれを先へと語り継ぐ人間もやってきて、マトリョーシカのような構造を持つ小説になっていったんです」
主人公は岡島謙吾。幼い日々に父から語り聞かされた太古の物語をランタンのようにかざして、曲がりくねった人生を歩んできた50歳の男。ひとり静かに暮らす彼のもとに、ある日「世界オーラルヒストリー学会」から手紙が届いたことにより、彼は「恐竜時代はまだ終わっていない」のだと聴衆に向けて語ることになる。
生命がめぐり、記憶が伝えられ死が新しい意味を持つ。
物語には捕食するものとされるものが登場する。では、その関係を新たに捉え直してみたら?
「草食恐竜が食われることによって肉食恐竜の身体に溶け入る。死が終わりではなくて、形を変えて生命を先へつなぐことなのだとしたら、そこには食われる悲しみだけじゃなく、喜びだって存在しうるんじゃないか。食物連鎖に組み込まれている恐竜自身がそんな思いを抱いていたとしたらどうだろう。そう考えをめぐらせながら書き進めていきました」
生命が循環し記憶が手渡される有機的な営みを夢想しつつ、人間がそこから疎外されていることにさみしさを感じてもいたという山野辺さん。かつて、自作『こんとんの居場所』について「死とは渾沌へ還ることなのかもしれない」と語った作家は、「小説という形で何かを作ろうとすると、死というものをどう捉えるかという問題にどうしても突き当たる」とも。その問いは、作家が“父と子の小さな話”と呼ぶ「最後のドッジボール」のうちにも流れている。
「父の死の数カ月後に書いた短編です。父という人について、その最期を静かに受け止める自分の心境について、小説の形で書き残しておきたかった。時間とともに記憶が薄れていったとしても、この短編が思い出を振り返るよすがになってくれるだろう、という個人的な願いも込められています」
物語を磨き上げることを生の拠りどころとする小説の主人公と作家の姿が重なり、奇想が光を放って、読み、書き、語るいくつもの人生の道行を明るく照らす。

『クロワッサン』1121号より
広告