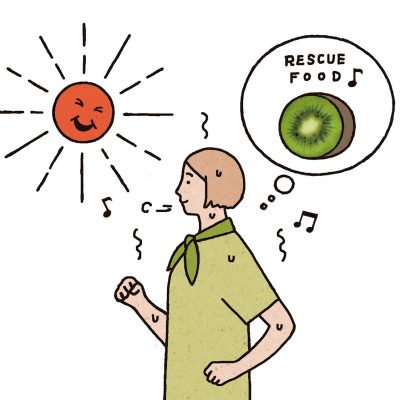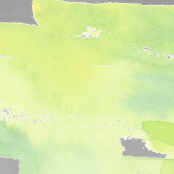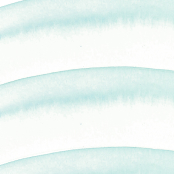「誰かの着物を、新しい誰かのもとへつなぐ」、青山のリサイクル着物店店主・大山和子さんの着物の時間。
撮影・枦木 功(nomadica) ヘア&メイク・高松由佳 着付け・奥泉智恵 文・西端真矢
誰かの着物を、新しい別の誰かへ。ここは、物語をつなぐ場所。

“C‘eraunavolta(チェ・ラ・ウナ・ボルタ)……〟それはイタリア語で「昔々あるところに……」。
物語の始まりを予感させるそんな言葉を店名に掲げる着物店が、東京・青山の住宅街にある。
店主は大山和子さん。実はこの店自体が長い物語を持っている。
始まりは、戦後まもなく。場所は表参道。かつてそこにあった『オリエンタルバザー』という店を記憶する人も多いだろう。中華風の大きな店構えで、街のランドマークだった。主に外国人に向けて日本の骨董品を売っていたが、その2階で大山さんの母が古布や浴衣、法被(はっぴ)などを扱う店を営んでいたのだ。
「母は非常にたくましい女性で、戦前、鹿児島から上京して洋裁学校で学び、職業婦人として自立していました。終戦後の混乱期には、まずは進駐軍の夫人向けに着物をドレスに仕立てる仕事をして、その後、外国人に土産物として古布を売る店を思いついたんです」
まるで朝ドラの筋書きのようだが、
「本当に。私の叔母に当たる妹と2人で店を始めたのですが、2人とも英語ができなくて、最初はお客さんが来ると接客を押しつけ合っていたそうです」
『大山キモノ』というその店は多くの顧客に愛され、2000年代まで続く。生き生きと働く母たちの姿を見て育った大山さんも、20代から店を手伝っていた。
「ただ、あの界隈の家賃が非常に高騰したこともあり、もう少し奥まった場所へ移ろうと決断して始めたのが今の店です。業態も転換して、日本人に向け、リサイクル着物とアンティーク着物を扱うことにしました」
昔々、という店名はその時につけた。
「イタリア人と結婚して、この言葉を知りました。新しい店では、昔々誰かのところにあった着物を別の誰かへとつないでいく。ぴったりの名前だな、と」

そんなリサイクル着物店の仕入れは、着物に特化した、業者向けの古物市場から行うのだという。留袖から木綿着物まであらゆる種類の着物が競りに上がり、一瞬のうちに価値を判断して競り勝ちにいく。まさにプロの世界だ。
「一枚一枚神経を研ぎ澄まして、一日が終わるとぐったりしてしまいます。時には欲しい着物を逃し、悔しくて夜中にハッと目が覚めることもあるんですよ。でも、楽しい。着物を着なくなったというけれど、これほどたくさんの、これほどバリエーション豊かな着物を日本人は作り続けてきたんだ!と、見ているだけで楽しくなるんです」
その中で、自分が本当にいいと思う着物だけを仕入れる。たとえ名匠の手になる一枚であっても、嫌いなものは仕入れない。そこは一貫している。
「私はやはり東京の人間なんですね。礼装の訪問着や総柄の小紋であっても、ぼてぼてしていないもの、たとえばこの青山の街にしっくりくるような、どこかすっきりとしたものを取っています。それが自然と店のカラーになっていますね」
そんな大山さんの今日の着物は、風合いから一目で上質なものとわかる無地紬だ。
「おそらく野蚕(やさん)糸で織られていて、着心地はとても軽やか。そしてこの静かな香色(こういろ)は草木染でしょうね。帯の遠山模様は古典柄で珍しくはないけれど、型彫りに力があり、藍一色で攻めているところも気に入っています」
もちろん、今日の着物も帯も、かつて誰かの手にあったものだ。
「それを自分サイズに直して、新しい、好みの色の八掛(はっかけ)をつけて。そんなふうにしてちょっと手間をかけて、自分に近づけていく。リサイクル着物のその過程が好きなんです」
これからも誰かの着物を、新しい誰かのもとへ。物語をつなぐ架け橋であり続けていく。
『クロワッサン』1110号より