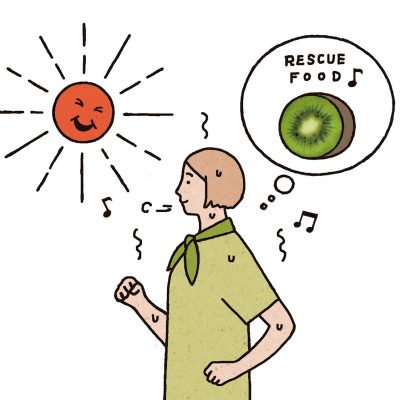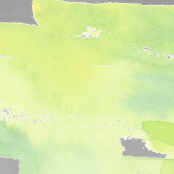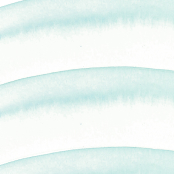『工芸喜頓』に聞く、奥深き民藝うつわの世界。
暮らしに取り入れやすい民藝うつわの魅力と使い方のコツを『工芸喜頓』の石原文子さんに聞きました。
撮影・深水敬介 イラストレーション・村松佑樹 文・輪湖雅江
「生活を楽しくするうつわを探していたら、民藝に辿りつきました」と話すのは、うつわと手仕事の店『工芸喜頓』の石原文子さん。
民藝とは名もなき職人がつくった民衆の日用品、つまり「民衆的工藝」の略。大正末期から昭和初期にかけて、思想家の柳宗悦を中心に始まった新しい美の基準。
それまでは”下手物(げてもの)”などと呼ばれていた生活道具や食器に、のびやかで素朴な美しさを見いだした柳宗悦は、全国の産地やつくり手を次々と訪問。土地土地の風土から生まれる簡素な形や力強い文様に心を揺さぶられた。
「今、民藝のうつわと呼ばれているのは、当時から続く工房や窯元のものと、その技術や精神を受け継ぐ個人のつくり手の品の両方です。作風も種類も多岐にわたりますが、なにしろ私が心惹かれるのは、そこに、日々の生活を支える料理をよりおいしくいただくための知恵が詰まっているからなんです」
たとえば、と厚手の鉢を手に取って、
「飯茶碗ならこのくらいの重さ、鉢ならこんな厚みという、日本人として慣れ親しんだ感覚がある。民藝のつくり手はそういう本能的な安心感を大事にしているように思います。薄くて軽いうつわは持ちやすいけれど、軽すぎると手にした時に違和感があるし、洗うのもそわそわしてしまいますよね」

さらに、おおらかで健康的なところも大きな魅力だと続ける。
「健康的、とはどんなふうに使ってもいい余白が残されていること。押しつけがましくないと言えばいいのかな。つくり手の思い入れだけで完成させるのではなく、うつわを生かすためのバトンを使い手に託しているんです」
”託されている楽しさ”は、自分で料理を盛って食卓に並べてみて、初めて実感できるものなのだという。
「民藝の根底には、つくる人や使う人への敬意が流れています。その敬意が、どうしても手元に置いておきたくなる愛らしさや、使う人に語りかけてくるような包容力を生み出しているのでしょうね。だからまずは目で見て、手に取った時の感覚で選んでほしい。その上で、民藝がもつ背景や物語を知れば、もっと愛着がわくはずです」

「日々を楽しくするもの」という視点で選ばれた陶磁器、木工、ガラスが並ぶ『工藝喜頓』。写真は大分の小鹿田焼。「ろくろの技術が高く、使い勝手がいい」という坂本工窯(さかもとたくみがま)のもの。