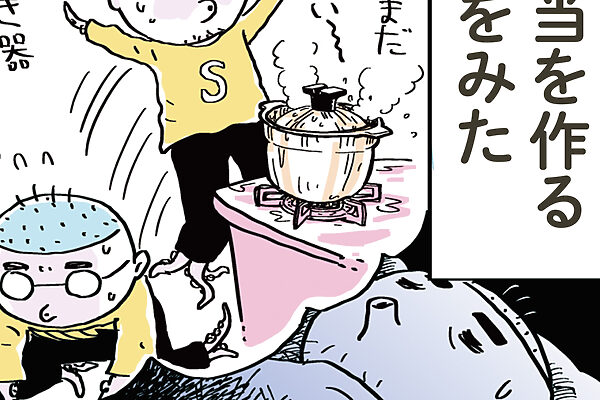『探偵はぼっちじゃない』著者、坪田侑也さんインタビュー。 「これまでの思いを全てこの小説にかけました」
撮影・黒川ひろみ(本) 天日恵美子(著者)


すらりと伸びた背丈は180センチほど。詰め衿の学生服が似合う精悍な顔立ち。坪田侑也さんは高校2年生、17歳の新人作家だ。
万城目(まきめ)学など数々の才能を見出した〈ボイルドエッグズ新人賞〉、それを受賞した本作を書いたのは、中学3年の夏休み。
「学校の自由課題で、僕は毎年小説を出していて。高校に入ると忙しくなると兄から聞いていたので、最後の中学生の夏、自分のこれまでの全てをぶつけようと書き上げました」
「賞への応募なんて少しも考えていなかった」というこの作品を、学校の展示から持ち帰って家族で読んだ同級生がいた。その保護者の勧めで投稿することになり、デビューにつながった。
主人公は中学3年生の緑川と、同じ学校に勤務する新米教師の原口。それぞれが今の自分の立ち位置に居心地の悪さを感じ、もがく心情が、視点を交互に変えて綴られる。
緑川は少し変わった存在感を持つ同級生・星野に「一緒に探偵小説を書かないか」と誘いを受ける。原口は、風采の上がらない先輩教師の石坂と関わりを持つように。物語は、2人の中学生と彼らが紡ぐミステリーの世界、2人の教師が追い求める「謎」という複雑な入れ子構造を形作りながら走りだし、絡み合い、集約されていく。
まず驚くのは、執筆時15歳の坪田さんが大人の目線を獲得していることだ。
「中学生の世界だけで書くと物語が単調になってしまうし、大人の立場を書いてみたいと挑戦する気持ちもありました。台詞回しが難しかったですけれど」
劇中劇を含む3つの視点という複雑な構成には苦心した。
「中学生パートと大人パートを別々に進めていて、夢中になって書いていたら、途中で時系列が合わなくなって。提出する直前に気がつき、慌ててカードにプロットを書き出して修正しました」
そしてこの作品をより魅力的にしているのは、随所にちりばめられたリリカルな心象風景だ。
中学生2人が図書館の屋上に上り、景色を眺める場面がある。
〈俺は一度だけ、スマホを取り出して写真を撮ろうとしたが、画面に映った景色が、あまりに現実と違って、色褪せて見えたのでやめた〉
青春時代に携帯がなかった世代にもわかる、この永遠の一瞬の尊さよ。作中、緑川は、書くことへの抑え難い気持ちを幾度も吐露する。
〈頭の中に湧き出てきた表現を、消えてしまわないうちに打ち込んで、吐き出してしまいたかった〉
〈「俺は、小説書いて生きていきたいんだよ!」そう叫ぶと、俺は自室に駆け込み、ベッドに倒れこんだ〉
坪田さんが「自分の気持ちをぶつけました」と語るこれらの言葉は、新星の誕生のような熱量の高い煌めきを見せ、眩しい。
現在、次回作を構想中。
「自分がいちばん読みたいと思う作品を書きたい。疾走感のあるエンターテインメントが好きです。謎が謎を呼ぶ、みたいなもの」
文学という広大な野に降り立った若武者、ぜひとも見守りたい。
『クロワッサン』1004号より
広告