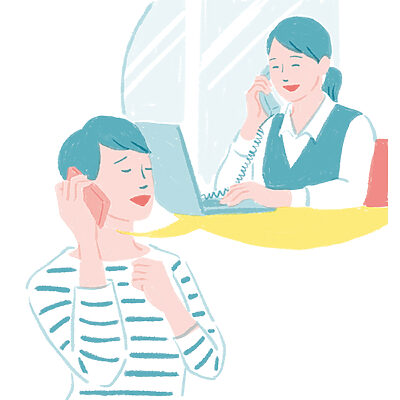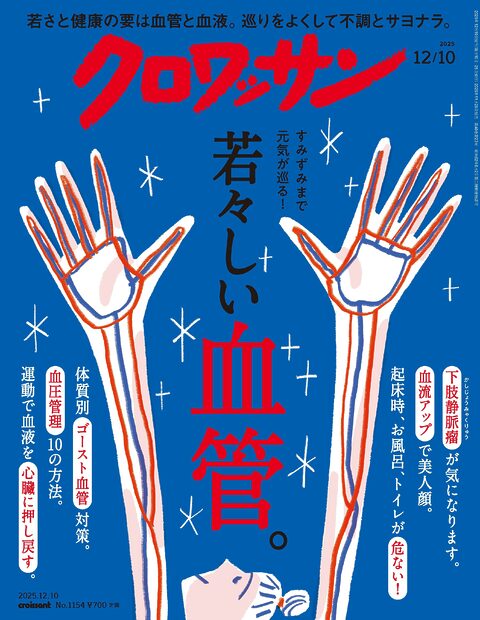おひつ、しゃもじ、精米機……。ごはんをもっと楽しむための道具。
撮影・青木和義 文・嶌 陽子
│ Seria │ シンプルしゃもじ 立つんです

へらが薄くてすくいやすく、自立するのも便利。
「エンボス加工されているため、ごはんがつきにくい。また、へらの部分がとても薄くできていて、ほんの少しカーブしているので、ごはんがきれいにすくえます」(原田さん)。柄の先端が平らで自立する。
│ マーナ │ 極しゃもじプレミアム

米のつきにくさ、持ちやすさ、どれをとっても超優秀。
「これまで使った樹脂製のしゃもじの中でダントツの米のつきにくさ。平置きしてもしゃもじの先端が浮く工夫、持ちやすいグリップなど、欠点が見当たりません」(しらいさん)。「米がつかず、ごはんをほぐしやすい」(土切さん)
│ 大久保ハウス木工舎 │ 杓文字 大久保型

「ごはんの盛りやすさ」を追求して作られた、独特の形と素材。
「友人の木工作家が試行錯誤の末に独特の細い形、ごはんがつきにくい栗の木の素材に行き着いたそう。独特の美しいシルエットと手触り。炊き上がったごはんに軽やかに入っていき、茶碗に対しての幅もとてもよいです」(マツーラさん)
│ 南部桶正(なんぶおけまさ) │ すし桶

すし酢の味がほどよくついておいしいすし飯が作れる。
吉野杉を素材に、接着剤を使わず竹釘を用いて組み立てたもの。「手巻き寿司やいなり寿司、ちらし寿司を作るときはこれの出番。ごはんを冷ます中で余分な水分を木が吸収し、すし酢の味を程よくつけられます」(長谷川さん)
│ 山本電気 │ 精米機「匠味米(たくみまい)」

白米から分づき米まで、好みに応じて手軽に精米。
料理人・道場六三郎さん監修。白米から分づき米まで好みに合わせて精米。「コンパクトで場所取らず。精米したてが食べられるのがうれしい」(坂井さん)。マツーラさんも愛用者で、「取り出した米ぬかは、ぬか漬けなどに使います」。
│ FUTAGAMI │ 鍋敷き

使い込むほどに味わいが増す、真鍮製の鍋敷き。
富山にある真鍮の鋳物メーカーの鍋敷き。「土鍋や羽釜を食卓に上げるときに使います。真鍮製なので焦げる心配がなく、色の経年変化を楽しめます。いろいろな形がある中で、私は『星』が一番シンプルで使いやすいです」(しらいさん)
│ タッパーウェア │ スーパーミックスボール

大きくて衛生的な保存容器が飯台として活躍中。
直径34.5cm、パン生地作りなどにも活躍。植松さんは独自の方法で愛用中。「熱いごはんと酢を合わせたら空気を抜きながら蓋をします。数分置いた後、蓋を静かに外すと水滴が蓋の裏側につき、あおがずに酢飯が完成」
すすめてくれた人
福田春美(ふくだ・はるみ)さん●ブランディングディレクター。商品開発、ホテルのブランディングや地域再生など多方面で活躍。自他共に認める料理好き。
長谷川ちえ(はせがわ・ちえ)さん●in-kyo店主。2007年、東京に雑貨店『in-kyo』を開店、2016年、福島・三春町に移転。エッセイストとしても活躍。
しらいのりこさん●料理研究家。炊飯系フードユニット「ごはん同盟」調理担当。お米料理研究家。著書に『これがほんとの料理のきほん』など多数。
植松良枝(うえまつ・よしえ)さん●料理研究家。旬の野菜を生かした料理が人気。近著に『春夏秋冬ふだんのもてなし 季節料理のヒントとレシピ』。
マツーラユタカさん●物書き料理家。フードユニット「つむぎや」の一員。昨年、故郷の山形・鶴岡市にカフェ&セレクトショップ『manoma』を開店。
原田ひ香(はらだ・ひか)さん●作家。シナリオライターから小説家に転向。食をテーマにした作品も多い。近著に『まずはこれ食べて』。
土切敬子(つちきり・けいこ)さん●だいどこ道具ツチキリ店主。東京・三鷹市にて、自身が使ってみて本当にいいと思った台所道具だけを扱う店を営む。
坂井より子(さかい・よりこ)さん●主婦。自宅で料理教室を主宰。主婦歴40年の経験を生かし活躍中。著書に『暮らしをつむぐ』など。
『クロワッサン』1018号より
広告