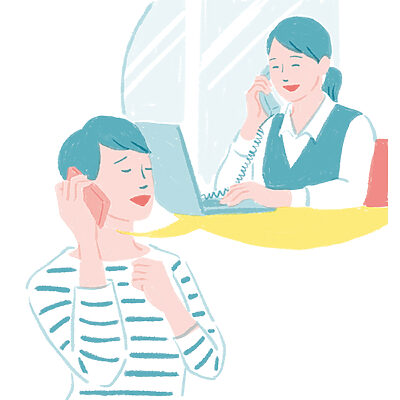『サイレントシンガー』小川洋子 著──沈黙とはそれを聴く者のためにあるのではないか
文・KIKI

小川洋子さんの新刊を、心待ちにしていた。いつもそうであるように、ページをめくる前から胸が静かに高鳴る。これまでの作品でも感じられた澄んだ静けさと、現実からわずかにずれた幻想の気配。その二つが今回の物語にも漂っていた。まるで湧き水をたたえる池のように澄みわたり、どこか不思議な、少しこわさを含んだ揺らめきを帯びている。
舞台となるのは「アカシアの野辺」と呼ばれる共同体だ。ここに暮らす人々はほとんど声を発さず、指言葉で意思を伝え合う。宗教でも営利でもなく、ただ沈黙を守り続ける人々。赤ん坊の頃からそこに身を置いた少女リリカは、沈黙を呼吸するように育つ。
やがて彼女は静寂から生まれる歌声を授かる。その声は決して派手ではなく、むしろいずれ消えてしまうことを前提としている。赤子の頃に老介護人から歌ってもらった子守唄、アカシアの野辺で羊を鎮めるために受け継がれてきた毛刈り歌。町で歌う機会が増えても、その歌声はいっとき空気に漂い、風によって流されていってしまう。歌い終えれば野辺の近くの家に戻り、沈黙の世界に寄り添うことのできる安心感をしみじみと実感する。
読んでいると、沈黙とは何かを度々考えさせられる。それは話す側に言葉がないのではなく、むしろ聴く側のためにあるものなのではないだろうか。身近な人との会話が途切れると、どうにか返事をもらおうと考えすぎ、かえって言葉を並べてしまう。そんな経験から、沈黙はわたしにとって苦い記憶を伴うことが多かった。けれど、この物語に流れる沈黙はまったく別の次元にあり、小川作品らしく神聖さを帯びている。
彼女のそばにあった二つの存在が、物語を大きく支えている。一人は、野辺で暮らす毛刈り担当の人だ。彼は言葉を発することはなかったが、いつもリリカをよく見ていた。羊の毛刈りの日、少し離れた場所で歌う彼女の声を受け止めていたのも彼だった。沈黙のなかで視線を送り、耳を傾けるその姿は、言葉よりも確かにリリカを支えていた。
もう一人は、野辺の外で働く料金所の人だった。リリカの姿の見えない歌声に惹かれ、やがて彼女と親しい関わりを持つようになる。しかし彼は沈黙を掬い取る耳を持たず、いつしか二人の間にずれが生まれた。
物語の終わりに、リリカは静かに歌う。その声は、これまで不在の誰かのためにしか差し出さなかった歌が、ようやく誰かへ向けられたものとして響く。歌は沈黙に抱かれ、風とともに遠ざかっていく。けれど、その声は向けられた相手には届かずに消えていった。
リリカのそばにいたのは、内と外、二つの世界から現れた存在だった。最後まで無言のまま見つめ続けた人と、言葉によって距離を近めた人。そのどちらと歩むかではなく、彼女は自分にとって自然な場所へと向かっていった。リリカの選択を思うと、胸の奥に切なさが残った。ふと耳を澄ますと、その切なさは沈黙の中でさざなみのように広がっていく。
『クロワッサン』1151号より
広告