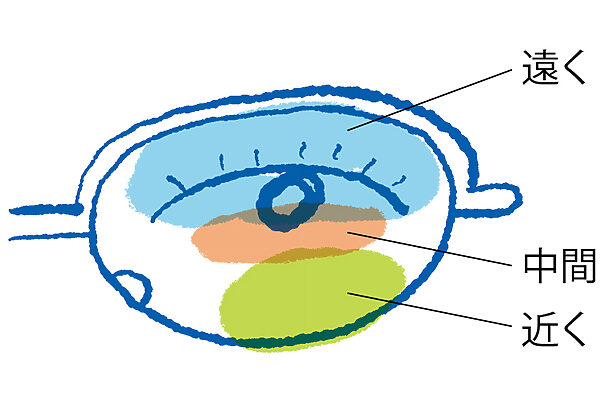『おまえレベルの話はしてない』著者 芦沢 央さんインタビュー ──「夢は人生を食い潰す呪いにもなる」
撮影・園山友基 文・一寸木芳枝

宇宙より広いという無限の指し手から“この一手”を選ぶ将棋。タイトル戦ともなれば、選ばれし天才たちが究極の頭脳戦を繰り広げる。だが当然、スポットライトを浴びる人間はほんの一握りだ。
「26歳までにプロ棋士の資格を得られなければ、自動的に追い出される奨励会って、すごく残酷ですよね。小さい頃から“神童”と呼ばれ、大学も行かず、彼女も作らず、バイトもせず、将棋のためだけに生きてきた人間だったとしても、年齢制限は絶対で、容赦なく追い出されるわけですから」
この将棋界特有のシステムに興味を持ったのを機に、ミステリー短編集『神の悪手』を書いた芦沢央さん。だが最新作では得意の“エンタメ”を封印。20歳でプロ棋士になった芝と17歳で夢を諦め、現役で東大に進学し現在は弁護士となった大島。奨励会を舞台に、同じ夢に青春を食い潰された男2人の生々しい激情を描き切った。
「夢を追うことはかっこいい、美しいと叫ばれるけれど、足元にあるのは地道な努力の日常で、芝のようにプロ棋士になっても成績不振にあえぎ、孤独な人間もいる。一方で世間的には“勝ち組”といわれる仕事に就いた大島でも、捨てたはずの夢への執着から逃れられない。“諦めなければ夢はいつか叶う”、その言葉がどれだけ呪いになるか。夢を追うことを美談にしたくなかった」
それは小説家という夢を追い続けてきた自身の本心でもある。
「並んでいればいつか必ず順番が回ってくるタクシーの列とは違うじゃないですか。すごい才能を持った新人も出てくるし、長編大作をさらっと書いてしまう化け物みたいな先輩もたくさんいる中で、私はまだ夢を追い続けている。怖いですよ(笑)。芝の言葉は、凡人なりにこの世界で生き延びている自分の感情から掘り出したものでもあると思います」
没入感をもたらす夢を追う者のヒリヒリとした焦燥
物語は芝と大島、それぞれの視点で語られる二部構成だが、芝編と大島編で文体が異なるのも本作品の特徴だ。特に前半の芝編は芦沢さんのこれまでの作品とは異なる純文学調の文体で綴られる。
「全ての仕事を一度ストップし、純文学の手法に一から挑戦しました。自分の力不足で物語のポテンシャルを引き出せないのが悔しくて。同業者からは“狂気の沙汰だね”と言われもしましたが(苦笑)」
結果、芝の章を完成させるまでに、実に2年という歳月を費やした。でもその挑戦は見事に報われたと言えるだろう。芝が抱えるヒリヒリとした焦燥感やAI研究への苦悩、先へ行くライバルへの嫉妬、大島に対するマウントの感情がリアルに迫り、息苦しさを覚えるほどの没入感をもたらしている。
「夢は叶っても叶わなくても人生は続いていく。この作品を書くことで、その事実を肯定的に考えられるようになったかもしれません。自分が選んだ道は自分で正解にしていくしかないのだと思います」

『クロワッサン』1154号より
広告