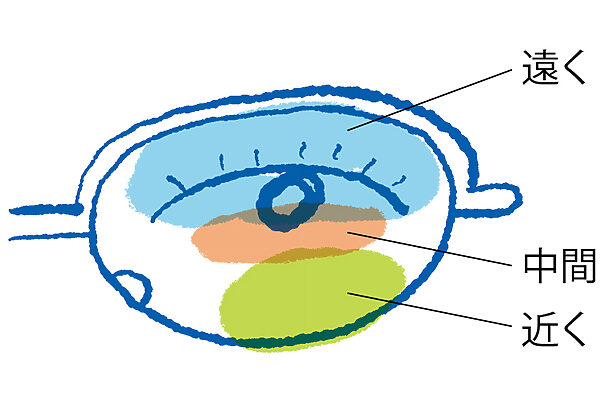『あるべきように 辰巳芳子の長寿の食卓』著者 対馬千賀子さんインタビュー ──「17年の食事で、私は生き直しました」
撮影・青木和義 文・越川典子

久しぶりに、師である料理家・辰巳芳子さんの自邸を訪れた。庭の梅の木には、色づき始めた実がたわわに生っている。
「先生と一緒に、毎年続けていた梅仕事を思い出しますね」
対馬千賀子さんは、17年もの間、辰巳さんと生活を共にした内弟子である。その辰巳さんは、現在100歳を迎えた。この本は、対馬さんがつけていた、80代の辰巳さんを支えた、ある1年間の食事の記録が元になっている。
「1日3食、辰巳先生は必ず召し上がります。先生の代名詞でもあるスープはもちろんですが、牛肉のソテーや煮込みもよくお出ししました。90代になられても、スープ教室では、何時間も立ったまま調理をしながら講義をした、その原動力はたしかに食でした」
食材選びから、出汁の引き方、下拵え、調味の方法……共に「食べる」ことで、対馬さんは自分でも体の変化を感じることになる。
食を共にすることで、なぜか疲れにくくなってきた
「よく『先生を守ってくれて』とお礼を言われることがありましたが、日々の食事作りはむしろ、私の体を守ってくれたのです。それまでの私は、料理に携わる仕事についていたのに、なぜこんなに疲れるかわからなかった。痩せすぎていたし、体調が不安定でした」
自分には何か足りないものがある──心のどこかで、ずっと感じていたのだという。
「一から生き直した17年間だったと思います。同じものを食べるようになって、疲れにくくなったのはもちろんですが、頭が働く、考えがはっきりしてきたとたしかに感じていましたから」
たとえば、前の晩に、いりこを水に漬けた鍋を冷蔵庫に入れ、翌朝、それで味噌汁を仕立てる。かつお節と昆布でとった出汁を冷蔵庫にストックしておく。これらは「自己救済術」なのだと辰巳さんとの暮らしが教えてくれた。
「先生はいつも(料理の)作り手が疲れてはいけないとおっしゃっていました。ですから、料理は合理的でした。先生ご自身が、本を読む時間、原稿を書く時間を捻出するために、どのように食べれば体を支えることができるか、真剣に考え続けてきたからでしょう」
その一つの回答が、「あるべきように」だった。人は、口にしたもので体ができる。口にする食材は自然が作る。旬の食材に体が癒やされるように、人は自然と共に生きることが自明の理だ。
「野菜、米、豆、魚介……モノを言わないものたちが、私たちの姿を明らかにしてくれるのよ、という先生の言葉をよく思い出します」
どう生きたらいいのか、先が読めない時代だからこそ、辰巳さんのメッセージを伝える必要があると対馬さんは感じている。そんな対馬さんは、今も変わらず、毎年の梅仕事を続けている。
「手をかければよくなり、不足があればそれなりの結果になる。この仕事も、自分をよりよく知るよすがのひとつなんです」

『クロワッサン』1146号より
広告