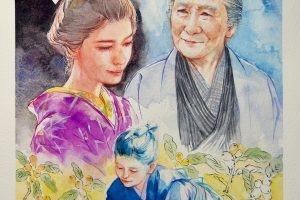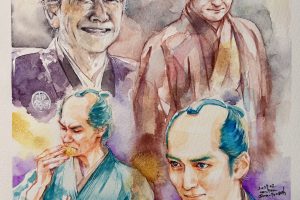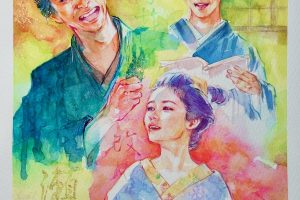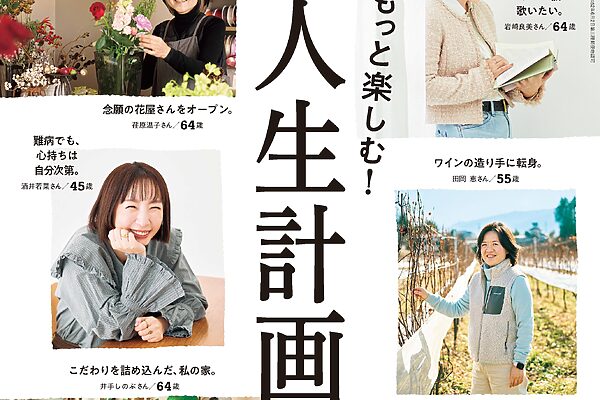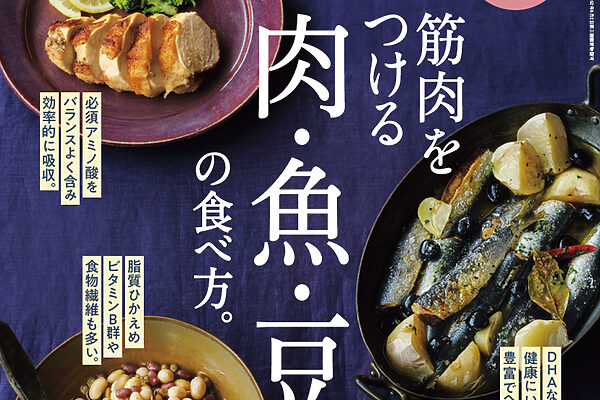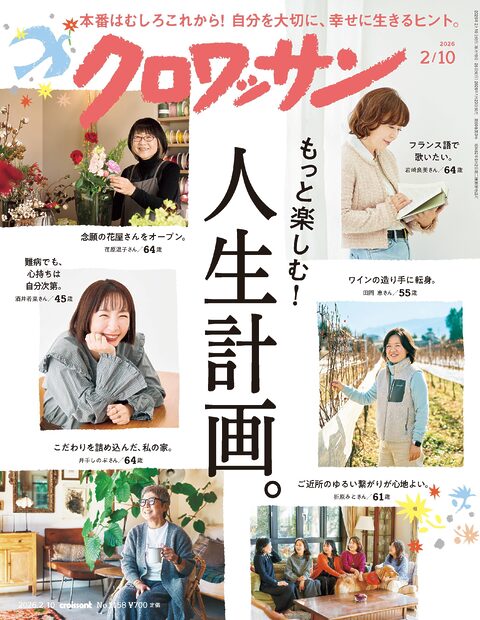考察『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』13話。鳥山検校(市原隼人)「嘘ばかりの女郎声など聴きとうない!」瀬以(小芝風花)にとって蔦重(横浜流星)がそうであるように、検校にとって瀬以は「たった一つの光」
文・ぬえ イラスト・南天 編集・アライユキコ
変わり果てた鱗形屋

「どうなったの? 足抜け」。
蔦重(横浜流星)に訊ねる平沢常富(尾美としのり)。よくぞ聞いてくれました、この一週間、ずっと気になっていたのだ。
うつせみ(小野花梨)と新之助(井之脇海)は本当に行方をくらましてしまった。9話(記事はこちら)で「足抜けをしても幸せにはなれない」という結論が出た後だったから、ふたりで秘かに行く末を誓ったのち、うつせみは「神隠しに遭いんした」と祭りの翌日にでも戻ってくるのかもと想像した。新之助は金を貯めて彼女の年季明けに請け出すという約束をしたのかなとも。けれど、やっと逢えたという喜びはもう二度と離れたくないという思いとなり、恋人たちを遁走させた。こうなったらもう、どうにか無事で逃げおおせてくれと祈る。
ところで蔦重は、何か知っているのか?
うつせみと新之助は捕まっていないが、鱗形屋孫兵衛(片岡愛之助)がふたたび偽板(無断複製の違法出版)で逮捕された。鱗形屋が負っていた債権の一つが当道座に流れてしまったのだ。主人(孫兵衛)に負担をかけないように返済したいと焦った手代が海賊版の早引節用集を秘かに出版、売却して金を作ったのだという。明和9年(1772年)の大火で板木(版木)類を焼失以来、地本問屋をなんとか立て直そうと悪戦苦闘した末に2度目の逮捕。鱗形屋の人相は変わり果て、一気に老け込んだ。白髪まじりとなった姿が苦しい。
盲人の職能集団である当道座の成立と、彼らが貸金業の資格を得た経緯はドラマレビュー8回で述べた(記事はこちら)。江戸幕府は福祉政策の一環として盲人に当道座への所属を奨励し、障害者の経済的自立を促したのである。
当道座の高利貸が貸し付けた金は「座頭金」と呼ばれ、その借り手は鱗形屋のような資金繰りの苦しい商人だけでなく、武士にも及んだ。厳しい借金取り立てによって首の回らなくなった武士が、娘を売る事態にまで陥るケースもあったという。
吉原の大見世、松葉屋にも女衒(ぜげん/売春労働斡旋業者)が武家の娘、さえ(新井美羽)を連れてきた。
松の井(久保田紗友)「旗本でありんしょう。ちかごろは珍しくもないけんど」
旗本とは、将軍家直属の家臣で石高一万石未満の、将軍に直接拝謁が許された家格を指す。日本を統治する将軍に仕える武士の娘が女郎となる。それが珍しくない事態。かなりショッキングだ。
松葉屋の通用口に山と積まれた米俵は「ここで働けば食わせてやるぞ」という証である。地方の貧しい農村から売られてきた幼い娘ならば目を輝かせるかもしれないが、さえの目には入らない。その表情には絶望と、押し殺した憤りがあった。
意次、治済に大博打を語る
なぜ幕臣──武士の生活が高利貸に頼らねばならないほど苦しいのか。
それは武家社会の給与の仕組みに起因するところが大きい。領地を持たない武士への給料は米で支払われる。その米を札差という仲介業者を通して米問屋に売却、その利益で生活するのだ。米の値が下がれば収入は減る。乱世が治まった江戸時代、各藩の新田開発により米が増産される。同時に平和な世は民衆の暮らしを変え、経済はめざましい発展を遂げた。生産量が需要を上回った米の価格が下落する一方、米以外の日用品(諸色)の価格が上がった。いわゆる「米価安の諸色高(しょしきだか)」の状態になりがちだったのだ。つまり、武士の生活は、米を売った利益だけでは立ち行かない。
では新田開発などをやめ、米の増産を抑えればよいのかといえば、冷害などで不作の年があればたちまち飢饉となってしまう。米を財政の主体とする江戸幕府は、常に危うい地盤の上に立っていた。
幕臣の生活苦は幕府上層部の耳にも入っており、老中首座・松平武元(たけちか/石坂浩二)は老中・田沼意次(渡辺謙)を「そなたが米の値を上げぬから!」と叱責した。
米価格の変動は、先述の理由だけでなく、貨幣価値ほか様々な要因が絡む。意次の「米の値、物の値。金の動きを操るのは森羅万象を操るようなもの」という言葉は、ただの言い訳ではない。
しかし武元は、あくまでも意次の責任だと責める。「足軽上がり」と意次の出自を罵るのも忘れない。石坂浩二の憎々しい芝居に、この理不尽ジジイ! と腹が立つ。
意次の甥である田沼意致(おきむね/宮尾俊太郎)が江戸城西丸目付を解任された。田沼派排斥の流れをひしひしと感じる意次は、大博打に出ると決意した。
気になるのは意次がその決意を語る相手が一橋治済(生田斗真)であること。
治済「田沼の者はよう働く。金繰りにも長けておるしの」
意致を一橋家の家老として雇用してもらえることもあり、意次は評価されたと安心しているが、治済の言葉にそこはかとない悪意を感じるのは気のせいか。よく働くというのはともかく、金繰りが上手いというのは武士にとっては誉め言葉ではない。意次、この人に胸の内を話してしまって大丈夫?
男前に生まれてきやがれ
意次の大博打とは、政の主導権を握るために座頭金、当道座を調査して摘発することだった。
西丸進物番の勤めにうんざりしている長谷川平蔵(中村隼人)は、西の丸からの異動を聞き届けてもらう代わりに意次の下で働く。進物番とは儀礼の場において大名家から献上された品(進物)を取り扱う職務である。重要な場で目を引く存在なので、眉目秀麗な幕臣が任命されたという。演じるのが中村隼人だ、そりゃあもう顔がいい。平蔵をやっかんで声高に嘲る西の丸勤めの旗本らに、
平蔵「てめえら。そんなに進物番になりたきゃ、男前に生まれてきやがれ」
本人も顔がいい自覚があるのに笑ってしまった。
平蔵の頼もしき仲間として当道座を探る者は、吉原でも引き連れていた取り巻き・磯八(山口祥行)と仙太(岩男海史)。振り売りの商人に扮して探索するその姿は、時代劇『鬼平犯科帳』の密偵たちを連想させる。
そうか、彼らが「おかしらのためなら、たとえ火の中、水の中」という存在になるのかと、時代劇ファンとしては嬉しい扮装だ。
平蔵が調査報告した旗本たちの座頭金負債は、意次たちの予想をはるかに上回るものだった。そこに、西丸小姓組の森忠右衛門(日野陽仁)が一家そろって失踪したという情報がもたらされる。
調査した座頭金借入者リストとあわせて、この事件を「使えるな」とほくそ笑む意次。
もはや弱き者にあらず!
意次は、将軍・家治(眞島秀和)と西の丸の主・家基(家治の嫡子、次期将軍/奥智哉)の前で、森忠右衛門失踪事件の詳細を明らかにする。
森忠右衛門と息子が平伏している。二人は頭を丸めていた。
家基は、長年信頼を置いてきた古参の家臣の変貌に衝撃を受ける。森の告白は、その姿以上に深刻なものだった。
20年間給料が上がらず、生活が苦しくなるいっぽうであった森は、成人した息子の御番入り(小姓組・御書院番・大番役など将軍家警護の役職に就くこと)願い出を考えた。願い出に必要な賄賂のためにを工面するために座頭から金を借りる。だが、息子の就職は叶わず、借金は膨れ上がっていく。ついには息子に継がせるべき家督まで借金のカタに取られ出家、そのまま失踪したのだという。
ここで意次が絶句する家基、将軍・家治に強く説く。
「将軍家は己の旗本すら養えておらぬのでございます」「高利貸を行う検校たちを取り締まらせてはいただけないでしょうか」
「不法且つ巧妙な手口で蓄財をした検校たちは、もはや弱き者にあらず!」
そうだ! あくどい座頭金をやっつけろ! と叫びたくなる。「検校から金を借りている徳川家臣、民草を救うべきと考える」と宣言した将軍・家治の英断を讃えたくなる。
だが根本的な問題は、誰もが認めるほど真面目に長く勤めている人間の給料が低いまま据え置かれていること、就職のために賄賂が必要なこと。これらが悪党成敗の大看板で覆い隠されてしまっている。
このあたりは現代の日本が抱える問題とリンクしている描写だ。
座頭金を取り締まったところで、生活が苦しければ他の高利貸が跋扈するだけだ。事実、幕臣と米問屋の仲介業者である札差には高利貸としての顔がある。ドラマ内で描かれた、返済期日を幕臣の給料日前に設定して借金を膨らませる悪質な手口は、座頭金だけでなく札差の常套手段だ。札差の貸金業は幕府からたびたび規制を受けながらも幕末まで続くのである。
意次の「徳川の世を支えたい」という言葉は嘘ではないだろう。米を財政の中心とする幕政改善にも時間はかかる。このドラマ内では彼の座頭金摘発は、大きな力を振るい政の流れを自分の手に握るための道具、大博打だ。
家基は意次に側近の惨めさを明らかにされ、それに気づかなかったと指摘された。爪を噛むその姿には「足軽上がり」に諭された屈辱感が満ちているように見えるが、はたして意次はこの大博打に勝ったのだろうか。
鳥山検校の失望
高利貸で江戸一番の大金持ちとなった鳥山検校(市原隼人)は、妻の瀬以(小芝風花)を喜ばせようと本をどっさり贈った。喜ぶ瀬以、その声を聴いて顔をほころばせる検校。
だがここで、鳥山検校と瀬以の夫婦関係の亀裂があらわになってしまう。
「もっとそなたと居ることとしよう」と言った検校は、瀬以からの「では、ご一緒に過ごせるときは旦那様に読んでさしあげます」という言葉がほしかったのではないだろうか。
花魁・瀬川との初会に、本を読んでくれたのがふたりの始まりなのだから。あのときの瀬川の機転は素晴らしいものだったが、自分を虜にしたその優しさは、女郎の接客だった──そう捉えてしまったのか。落胆と失望は怒りに変わる。
まざまざと蘇ってしまうのは、吉原から訪ねてきた客・蔦屋重三郎と語らうときの、妻の弾けるような明るい声。
検校「しょせん儂は客ということか。どこまで行っても女郎と客。そういうことだな?」
「嘘ばかりの女郎声など聴きとうない!」
それは違いますと必死の弁明をする瀬以を振り払った勢いでつまずき、倒れ込む検校。すぐに起き上がることができず、手探りで本棚に縋り立ち上がる。意次が「もはや弱き者にあらず」と断じた検校だが、金の力と切り離されたら弱者だとはっきり描かれている。
たった一つの光
蔦重のもとに検校の使いが迎えに来た。蔦重が幼い頃、瀬以に贈った『塩売文太物語』を携えて。なにかあったのかと問う蔦重に使いの者は「来ればわかる」。押し殺した声に良い話ではないと蔦重も勘づいたが、黙って従った。
検校は蔦重を招いたことを瀬以に伝え、
検校「返事次第では斬ることになるかもしれぬからな。不義密通の罪じゃ」
江戸時代、妻の不義は重罪であった。8代将軍吉宗の下で制定された「公事方御定書」(寛保2年/1742年~宝歴4年/1754年成立)の内「御定書百箇条」で不義密通についての罰則が定められた。密通をした妻、相手の男ともに死罪。そして「密通の男女共に夫殺候はば無紛においては無構」。それが事実であった場合、夫は妻と愛人の男を殺しても罪に問われない。逆に夫が妻以外の女性と関係を持った場合は法的な問題にならなかった。
なんだそりゃとは思うが、儒教思想による男尊女卑が深く根付いた江戸時代の法律である。
検校の「お前は骨の髄まで女郎だな」という言葉に、瀬以の本心が涙と一緒にほとばしる。瀬以にとって蔦重は苦界でたった一つ出会えた光。でも、この世で誰よりも大切にしてくれるあなたを傷つけるこの思いを消してしまいたい。信じられないなら命を絶たれてもよい──花魁言葉で語られても、これが女郎としての手練手管でないことは鳥山検校には声音でわかる。
瀬以の心が他の男にあると知っても、手を下すなどできない。自分の思いを受け止めようと真剣に思い悩む人間は彼女だけ。瀬以もまた検校にとって、たった一つの光なのだ。この女を愛していると、検校の目、言葉を失い震える唇が語っている。
取り繕った顔をかなぐり捨て、鳥山検校と瀬以は真の心をぶつけ合った。このまま向き合い続けられたなら、夫婦として歩む道が拓けたかもしれない。しかしこの夜に奉行所の家宅捜索の手が及んだことは、検校にとって不幸なことであった。
本が運んでくる幸せ
13話で印象的だったのは、平賀源内(安田顕)の蔦重への言葉。
源内「本ってなあ、人を笑わせたり泣かせたりできるじゃねえか。そんな本に出会えたら人は思うさ。『ああ、今日はツイてた』って。本屋ってなぁ随分と人にツキを与えられる商いだと、俺は思うけどね」
蔦重「確かに。本が運んでくる幸せにゃ、俺も覚えがあります」
次週予告。
サブタイトルが「蔦重瀬川夫婦道中」。 め、夫婦? と思ったら蔦屋の店先で瀬以を抱きしめる蔦重。待った、感情が追いつかない! 大文字屋市兵衛(伊藤淳史)が奉行所のお白洲に。一体なにごと。鳥山検校の横顔、美しいけどこれはきっとよくないことが起こった後なんでしょ?
14話も楽しみですね。
*******************
NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』
公式ホームページ
脚本:森下佳子
制作統括:藤並英樹、石村将太
演出:大原拓、深川貴志、小谷高義、新田真三、大嶋慧介
出演:横浜流星、安田顕、小芝風花、高橋克実、渡辺謙 他
プロデューサー:松田恭典、藤原敬久、積田有希
音楽:ジョン・グラム
語り:綾瀬はるか
*このレビューは、ドラマの設定をもとに記述しています。
*******************