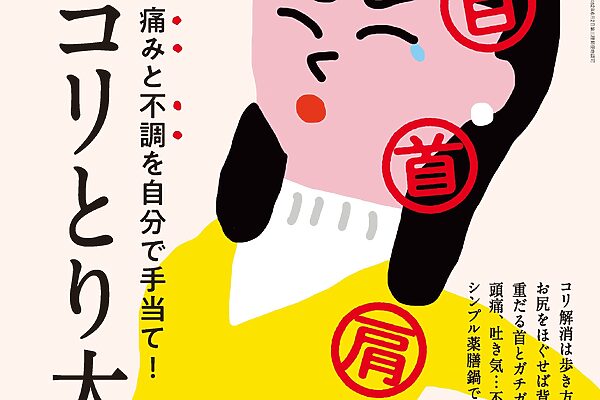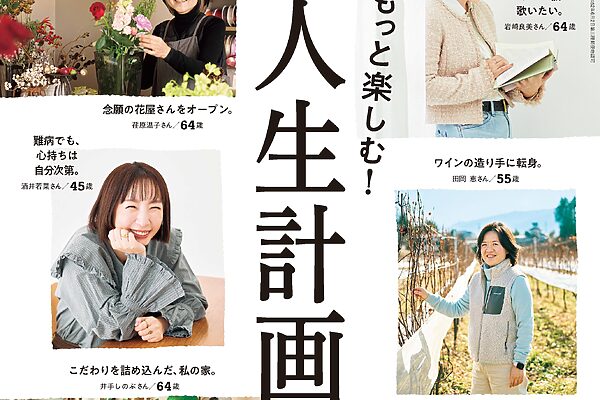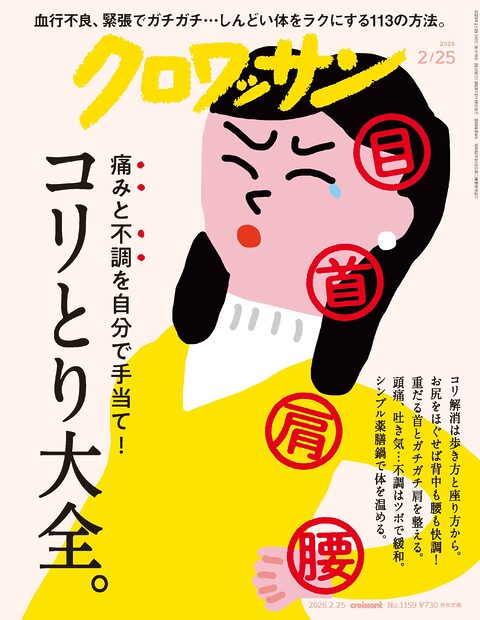いくら必要?何に使うの?一番気になる「介護のお金」
イラストレーション・朝倉世界一 文・黒澤 彩
ステップ3:使える給付やサービスについて調べておく
要介護認定を受けると必ずケアマネジャーがついてくれるので、介護保険関係のことは自分で申請しなくてもケアマネジャーが動いてくれる。
要介護度に応じたサービスや給付に関しては、自分ですべて一から調べて申請しなくても、取りこぼすことなく受けられるはずだ。
「ただ、ケアマネジャーが手続きしてくれるのは公的な介護保険に関わるところだけ。施設の費用をどうするか、日常の生活費をどうやって引き出すかといったお金の相談はできません」と牧本さん。
高齢者のための公的制度は、医療と介護に関して充実しているものの、金融の分野がほぼ手付かず。介護保険以外のお金のことは、自分で調べて任意後見制度や民事信託サービスを利用する必要がある。
子が受けられる制度
介護休業制度(介護休業給付金)
家族の介護のために仕事を2週間以上休まなければならない場合、給与の67%が雇用保険から給付される。最長で93日まで、3回に分割して取得できる。雇用保険に加入していない非正規の働き方では利用できないので注意。
介護休暇制度
短時間から取得できる休暇制度で、法律で定められ、すべての労働者が利用できる。介護する家族1人につき年5日まで取得でき、1時間、半日といった短い単位での取得が可能。突発的な事態や、病院への付き添いなどに対応できる。
家族介護慰労金
介護保険サービスを利用せず、自宅で同居して1年以上にわたり要介護4、5の要介護者を介護している家族に対して、自治体から年額10万〜12万円が支給される制度。諸条件が自治体ごとに異なり、実施していない自治体もある。
親が受けられる制度
公的介護保険

公的介護保険の要介護度別保険給付限度額(居宅介護)
介護を社会全体で支える仕組み。40歳以上の人全員が介護保険料を負担する。要介護度に応じた限度額が決まっていて、その範囲内であれば1割※の自己負担額でサービスを利用できる。また、利用者の自己負担額が上限を超えた場合に超えた分が払い戻される「高額介護サービス費」の制度も。
(※一定以上所得者の場合は2割または3割)
親の資産を守る「家族信託」とは?
家族の誰かが受託者となって親の資産を管理する方法。認知症などで判断能力が低下すると、銀行口座が凍結され、不動産の売買などもできなくなってしまうので、そうなる前に、信頼できる家族に資産を託すためのサービスだ。
銀行では、家族であっても資産状況や暗証番号を教えてもらうことはできないし、本人が通帳と印鑑を持って窓口に行かなければ預金を下ろせない。目の前に親自身の資産があるのに使えないという事態になってしまう。
認知症が進んだ後で預金を引き出したり契約をするには、成年後見制度を利用するしかなく、そうなると家族の意向を反映しづらい上に、後見人に支払う費用の負担も生じる。資産管理については、本人の判断能力があるうちに手を打っておきたい。家族信託のほか、裁判所を通じて認定される任意後見制度、生前贈与なども親のお金を守る選択肢になる。
広告