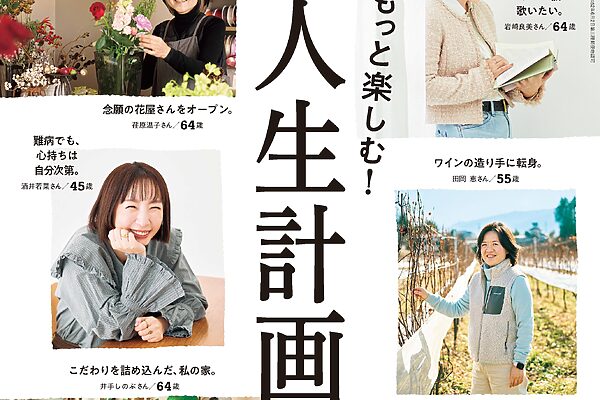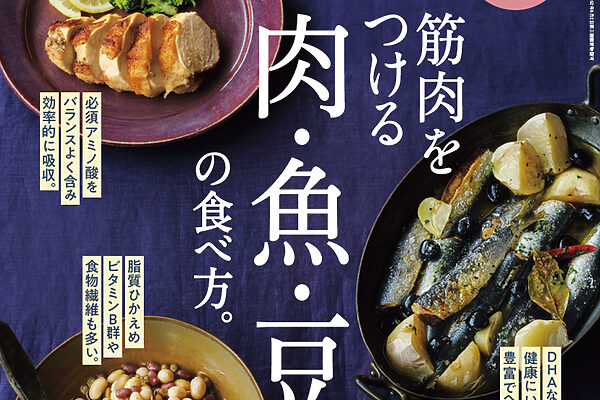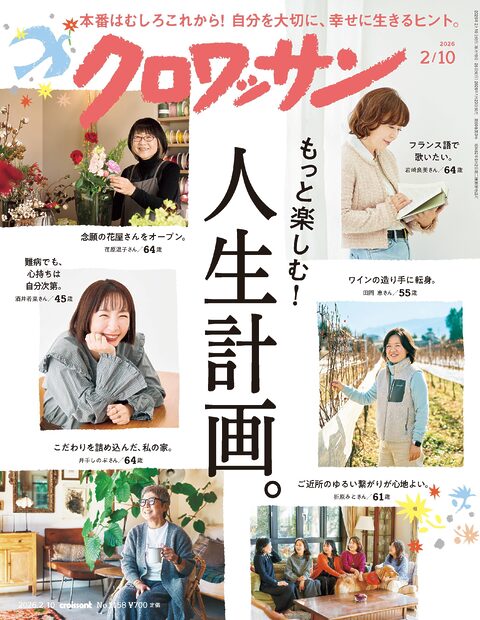知っておきたい介護の基礎知識:介護が必要になったら「介護サービス」を利用しよう
イラストレーション・山里美紀子 構成&文・保手濱奈美
介護サービスを利用するには、介護保険の申請をして、介護、または支援の必要があると認定されることが条件。在宅での介護サービス開始までの流れを把握しよう。

ステップ1. 介護保険の申請をする
申請の受け付けは、親が住んでいる市区町村の役所の介護保険担当窓口。
「申請の際に必要になるのは、窓口や市区町村のホームページから入手できる『介護保険要介護認定・要支援認定申請書』と介護保険被保険者証(介護保険証、※5)です。本人や家族が申請を行うほか、難しい場合は包括に記入済みの申請書と介護保険証を託して、代行を依頼することもできます」
申請書の記入欄はここに注意!
面接調査日程等の連絡先
意見書作成医師
介護保険を申請すると認定調査員が親の自宅に来て、介護や支援が必要かどうかの調査を行う。
「調査にはできるだけ家族が同席したほうがいい。家族間で相談して、立ち合う人の名前を申請書の『面接調査日程等の連絡先』に記入を」。
また、「意見書作成医師」の欄に記入した医師に役所が意見書作成の依頼をするため、「親の生活上の支障をよく知る、かかりつけ医の名前を書いて」
ステップ2. 親と一緒に訪問調査を受ける
調査員と都合のよい日時を電話ですり合わせると、申請から10日前後で訪問調査が行われる。
「調査は本人や家族への聞き取り形式です。身体や生活上の支障の有無など74項目にわたり、なかには片方の足で立てるかなどの運動機能のチェックもあります」
親が「介護は必要ない」とばかりに、調査当日に普段より元気に振る舞ってしまったら?
「調査員の多くはケアマネです。プロなので本人が無理をしていれば、大概気づきます。家族は、日頃の親の困り事を調査員に具体的に伝えられるように、事前にメモなどを準備しておくといいでしょう」

親が介護保険の申請を拒んだら?
「介護が必要」ではなく「ラクになるよ」と伝えてみて。
介護、しかも他者に手助けをしてもらうとなると、抵抗感を抱く親がいるのも無理はない。
「『介護』という言葉自体が、老いの烙印を押すような印象を与えてしまいやすい。『介護が必要』など直接的な表現ではなく、親の生活の困り事を挙げて『それをやってもらえるから今よりラクになるよ』とポジティブな面を伝えてみましょう」
ステップ3. 認定結果が親の家に郵送で届く
結果が届くのは、申請から約1カ月後。
「要介護認定(※6)または要支援認定(※7)の通知であれば、介護サービスが利用可能に。その後の手続きは、要介護なら居宅介護支援事業者(※8)、要支援なら包括と窓口が異なります。一方、結果が非該当(自立、※9)の場合は、介護サービスを利用できません」
要支援の場合:ステップ4. 要支援なら包括に連絡をする
ステップ5. 介護予防ケアプランを作成する
包括に連絡をすると、担当者が親の自宅を訪問。家族も一緒に集まる機会を持つ。
「介護サービスを利用するには、介護予防ケアプラン(※17)の作成が不可欠です。作成の流れは要介護と同様ですが、利用できるサービスの範囲は要介護と比べて限定されます。そのなかから担当者がサービスの種類や回数を本人と家族に提案。了承したら介護サービス事業者と契約を締結。サービスが開始します」
↓
サービス開始へ
要介護の場合:ステップ4. 要介護なら居宅介護支援事業者を選ぶ
要支援の場合は窓口が包括なので親の住所の管轄内の包括に連絡をすればいいが、要介護は認定結果の通知と一緒に届く居宅介護支援事業者のリストから自分で選ぶ必要がある。
「各事業者の規模や併設サービスの有無などから比較検討を。ホームページやクチコミも参考にしてみてください」
ステップ5. 居宅介護支援事業者に連絡をしてケアマネジャーを決める
ステップ6. ケアマネジャーと契約をする
担当してくれるケアマネが決まったら契約を交わす。といっても金銭は発生しないので安心を。
「ケアマネは介護生活の伴走者となる存在。相談しやすく納得できるケアプラン(※10)を提案してくれる人を選びましょう。ケアマネとの連絡窓口は家族間でキーパーソン(※11)を決めて、一本化しておくこと」
ケアマネは契約後でも変更できる
ケアマネとの相性がいまいち……と感じたら変更OK。
「同じ事業者内で代わってもらうか、事業者自体を替えて別のケアマネに依頼することもできます。利用中のサービスは継続可能です」
ステップ7. ケアプランを作成する
介護サービスを利用するためのケアプランを、ケアマネに作成してもらう。
「とはいえ任せきりではなく、誰もが納得できるように、親本人、家族、ケアマネで自宅に集まり、困り事などを話し合いながら一緒に作ることが大切です。ケアマネは、親の状態なども鑑みたうえで、ケアプランの土台を提案してくれます。介護サービスの種類や回数など、合意ができたら、サービス担当者会議(※12)へ」
ステップ8. 介護サービス事業者と契約をする
ケアプランの土台を基に、ケアマネが介護サービス事業者(※13)を手配。担当者が自宅に集まり、サービス担当者会議を行う。
「親と家族も参加して、サービスの内容を確認します。ケアプランが決まったらホームヘルパー(ヘルパー、※14)や福祉用具サービス(※15)の事業者などと契約し、サービス開始。ここまで、家族が同席する場面はほぼ平日。仕事と重なったら介護休暇(※16)の利用が賢明です」
↓
サービス開始
サービス開始までの空白期間はどうすれば!?
緊急時には前倒しできます
介護保険を申請してから、認定が出るまで約1カ月。さらに介護サービス開始まではケアプランの作成があるなど、実際にサービスを受けられるまで空白期間ができてしまう。
「緊急の時には、役所に申請書を提出した日付から“見込み”の介護度で介護サービスを利用できます。ただし、それより低い認定結果が出たら、その月だけ自己負担額が10割になってしまう。介護度がどの程度になるか、包括に相談するとおおよそ見極めてもらえるはず。なお、総合事業(※18)なら、介護認定がなくても訪問介護などが利用できます」
※の説明は「はじめての介護のための用語集」へ。
『クロワッサン』1134号より
広告