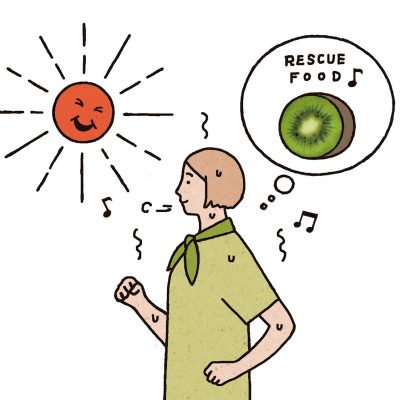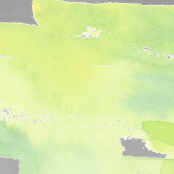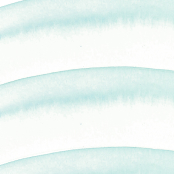同居はしない、ホームに入ることに抵抗はない、日本とアイスランドの介護の違い【助け合って。介護のある日常】
撮影・滝川一真 構成&文・殿井悠子
「私は私の道を歩むーー。母の人生を見守るために、私にできること。」滝川シグルンさん・滝川一真さん

前回の記事はこちら。
「やりたいことは全部やってきた。私のお葬式には、フランク・シナトラのマイウェイを流してね」
アイスランド国籍のシグルンさんの母親トラさんは、3度の結婚をし、3度目の結婚でシグルンさんを産んだ。仕事は客室乗務員を務めた後、大学院に通って歴史を学んで教師になり、70歳まで働いた。
変化があったのは、トラさんが仕事を辞めて間もなくの頃。診断を受けるとアルツハイマー型と脳血管性認知症の混合型だった。その後、遠距離介護の限界を感じたシグルンさんは、夫である滝川一真さんの母国・日本から、家族を連れてアイスランドへの移住を決めた。
シグルンさんが戻ってきて、トラさんと夫のバルドゥルさんは、60歳以上の人限定の1階建てアパートに引っ越した。両親の近くに住むが同居はしない。それが当たり前なのがアイスランドだ。老人ホームへ入ることにも親子共に抵抗はない。最期まで自宅で暮らすことにこだわっている大阪の両親を思い浮かべて、一真さんは日本との違いを感じている。
シグルンさんは、両親の安否確認をするためにセキュリティ会社と契約をしている。トラさんの夜間徘徊対策には玄関ドアにアラームを付け、足腰がすっかり弱くなったバルドゥルさんには転倒予防ペンダントを付けて、何かあればシグルンさんの携帯に連絡が入る。すると、夜中に出て行ったトラさんを追いかけたバルドゥルさんが転倒しかけて、両方のアラームが鳴るという事態。二人暮らしに限界を感じ、手厚いケアを受けられる老人ホームへ申し込み中だ。

看護師として老人ホームで働いているシグルンさんは、両親の老いに対し都度やるべきことを的確に判断し、見守ってきた。母のトラさんのように、振り返って人生に後悔が少ない人ほど、歳をとっても悪い執着がなくスッキリしていることも理解している。それでも、認知症が発覚してからの13年間、ゆっくりゆっくりと、母親の記憶が消えていき、生自体がどんどん色褪せていく様子を見るのはつらいと、涙を拭う。
「母は生きている。けれど、自分の知っている母はもう生きていない。一緒にいてお風呂に入れている時間はリアルだけど、その5分後には母の記憶から私はいなくなっています。でも、少なくとも一緒にいる時間、母はすごく楽しそうなので、その瞬間瞬間に今できるすべてを注いでいる。それが今の私ができること」
トラさんを見習って、悪いことに執着しない。現実がつらい時は、母親と一緒に過ごすことで実現できた幸せな事柄を具体的に考えるようにして、日々を過ごしている。(続く)

『クロワッサン』1112号より