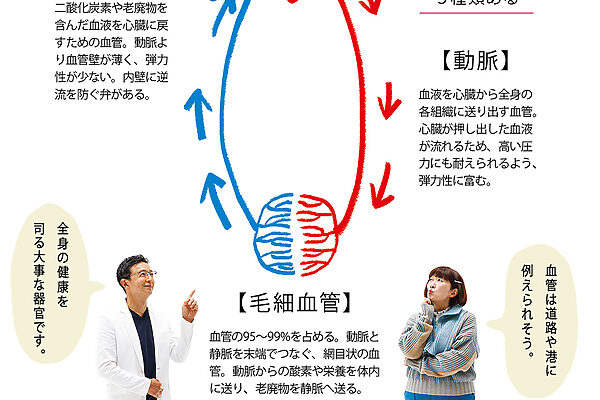『幽玄の絵師―百鬼遊行絵巻―』著者、三好昌子さんインタビュー。「見えないけどそこにある世界を書いてきた」
撮影・黒川ひろみ(本・著者)


6つの段からなる物語の主人公は、室町時代の絵師、若き日の土佐光信である。時の将軍・足利義政の命で絵師として活躍しつつも、御所に次々と起こる不可思議な出来事の見守りや、解決にまで乗り出すはめになる。
義政は、大飢饉や災害に瀕しながら政治を疎んだ将軍として後世評され、後継問題から応仁の乱を引き起こすが、物語はその前夜を描く。一方で、能楽を愛し、庭師や絵師を厚く遇す義政は「心の中が読みにくい御方」として、側に仕えるものの口から語られるが、
「子どもの頃に父親が暗殺され、続けて将軍となった兄も幼くして病死、それも毒殺されたのかもーー
そんな環境にあった子どもが一筋縄でいく人間に育つわけはないだろう、と。そういう意味でも、義政というのは魅力的でおもしろい」
と、三好昌子さんは分析する。
その義政が心血を注ぐのが、室町御所、通称“妖物屋敷(ばけものやしき)”の造営だ。怪しげな噂が立ちこめる御所が中心となり、各段のエピソードには、個性も彩りも豊かな妖(あやかし)たちが立ち現れる。曰くある高楼で光信と酒を呑み交わす異国風の老爺、雪の庭に佇む血塗れの女、幼き日の光信に語りかける鯉、老女からあどけない女童に変ずる鳥女……。物語のもう一方の主役は、こうした“人ではないもの”たちである。
「見えないからといって存在しないわけではないと思うんです。空気だって目には見えなくてもちゃんと重さもあるし、人から放たれるエネルギーに温かみを感じることだってあるんですから」
活き活きと描き出される、“人ではないもの”たちの姿。
たまたま見える、感じる人と“人ではないもの”たち。それらを今までごく当たり前の人間としてひとつ世界の中で書いてきたのだと言う。光信も、その一人だ。件の「どう見ても普通の人間ではない」高楼の番人から、「おまえの心には壁がない、だから私たちが見えるのだ」と語りかけられるとおり、周囲の人間には感知しえないものを見、時に形に描く。その“人ではないもの”たちが、各々、実に活き活きとして魅力的なのである。
「今、妖怪は友だちか悪さをするもの、対人間という捉えられ方をされている。人間が主体なんです。そうではなく、人間もいれば彼らもいて、ひとつの世界の中に全てが入り込んでいる。それがこの世のありようだ、というのが私の世界観の根底にあるんです」
そうした多彩な“もの”たちと、光信、義政といった歴史に名を残す面々とが、応仁の乱前夜を背景に、さまざまな局面で出合い、物語を紡ぐ。そして、それぞれのエピソードは巻末ですとんとひとつところに落ちていく。さぞや緻密に練られているのかと思いきや、
「私は前もってあらすじは書かないんです。書き始めると、続きがひらめいて降りてくる。だからいつも、これは私が書いているんじゃない、何かに書かされているんだ、と言っているんですけれど」
と、楽しげに三好さんは笑うのだ。
『クロワッサン』1011号より
広告