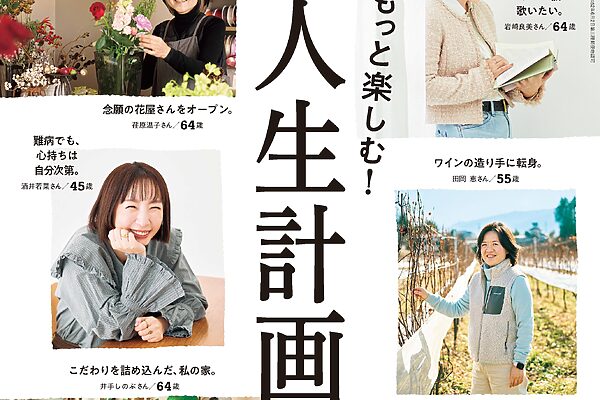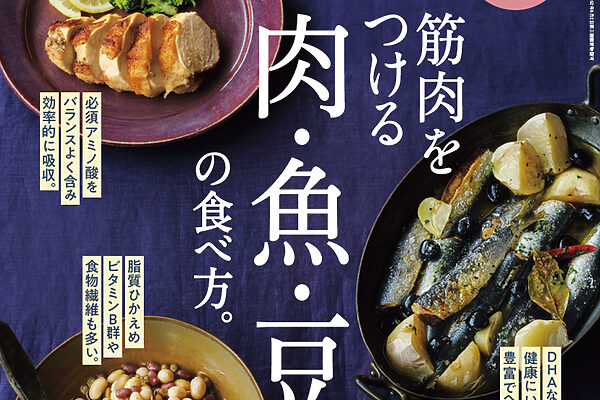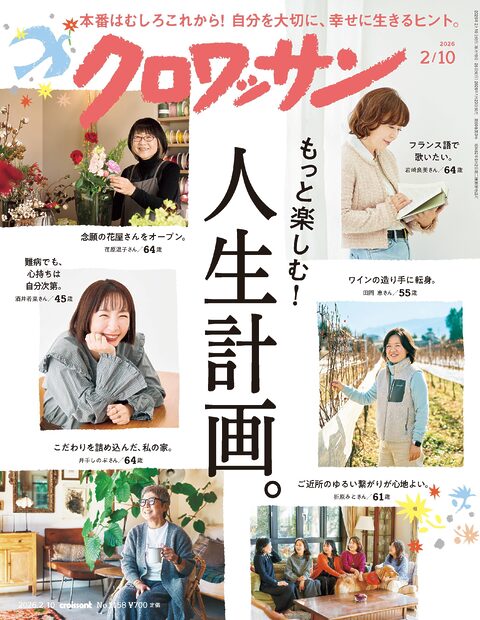【白央篤司が聞く「自分でお茶を淹れて、飲む」vol.3】奥村忍(「みんげい おくむら」店主)「飲むと一瞬、『違うどこか』へ連れていってくれる」民藝的魅力溢れる中国茶の日常
取材/撮影/文・白央篤司 編集・アライユキコ
めちゃくちゃもう……手仕事の世界

奥村忍さんの事務所兼アトリエを訪ねたのは真冬の午後2時、風の強い日だった。壁一面が窓なのに、中はさほど寒くない。コンロには大きな銅製のやかんがかけられていて、シュウシュウと湯の沸く音が耳に温かく響いた。

奥村 湯沸かしは中国の四川省で買ってきたものです。気軽にお茶が楽しめる茶館という場所があちこちにあるんですが、そこで実際に使われているものですよ」
奥村さんは、各地の生活道具と民藝のうつわを探し求める旅人である。簡単にいえばバイヤー兼販売者だが、実際の暮らしの中でどのように使われているのか、作られているかを目にしてから買い付けるのがモットー。ウェブサイト「みんげい おくむら」(情報はこちら)は、料理研究家や調理人の間でも人気のサイトだ。

奥村さんとお茶とのつきあいは大学時代、25年ほど前にさかのぼる。当時姉が台湾に留学しており、「せっかくいるんだし」と遊びに行って、中国茶を味わった。
奥村 お茶を淹れて飲むことが日常、カジュアルに行われていて新鮮でした。僕はカフェインの強いお茶は体に合わないのですが、中国茶だとものによっては平気で、それもよかったんです。
29歳から現在の仕事を始め、台湾を再訪する。あるとき、現地の茶農家を見学する機会を得た。茶摘みや茶干しに使うカゴや布類の風合い、肌感にすぐさま魅せられたが、より惹きつけられたのは、その茶自体だった。
「女性が朝から茶葉を摘んで、男性が夜通し製茶するんです。めちゃくちゃもう……手仕事の世界で。淹れてもらって味わって、おいしかったですね」
手塩にかけたものを、つくり育てた人が目の前で淹れてくれる。最高のぜいたくというか、ご馳走の一杯に思える。そのとき味わって以来愛飲しているという「東方美人茶」を、私にも淹れてくれた。


蓋碗(がいわん)という茶器に茶葉を入れ、お湯を注いでいく。冬の光の中を湯気が立ち昇る。ふたをして茶葉が開くまで、しばし待つ。

奥村 この蓋碗、200mlよりちょっと少ないぐらいが入りますかね。青磁的というか、青みがかった肌の色だとお茶がすごくきれいに見えるんです。厚手で丈夫なのでで、旅にも持参していますよ。中国のものではなく、鹿児島の作家さんにお願いして作ってもらいました。

頃合いを見てふたをずらし、茶海と呼ばれる片口、というかピッチャー的なものに茶を移す。茶杯(いわゆる湯呑み)に注いで、「どうぞ」と差し出してくれた。ひと口いただけば、胸のスッとするきれいな香りが広がる。ほんのりやさしいかすかな渋みが心地よく、すぐに飲んでしまった。
奥村 2015年に仕入れたもので、かなり熟成しています。誰が淹れてもおいしくなるお茶ですね。華やかで、香りに余韻があって。熟成しているからまろやかですが、若いものはマスカットのような感じもあります。紅茶だと果物のような、甘い香りがするものもありますが、そういう感じがより強い。

「民藝的なもの」の手ざわり
飲む中国茶も、そのときの気分によっていろいろだ。
奥村 朝食を食べてお腹が落ち着いたら、1種類目のお茶を飲むんです。午前中はそれを何煎も。昼食後にまた別の種類を淹れて飲んで、午後はずっとそれ。夜はお酒も飲みますが、終わりにお茶を飲むことも。お茶を飲むと一瞬、「違うどこか」へ連れていってくれる感じがある。そこがいいですね。考えごとをして煮詰まったとき、リセット的にお茶を飲むことも多いです。
湯沸かしから蓋碗、茶海、茶杯と、淹れ終えるまでに触れるものが日本茶より多い。実際に触れてみると、感触は当然それぞれ違う。手作りならではの肌感を多様に感じてからの、ひとすすり。これが心地よかった。奥村さんの愛する「民藝的なもの」の手ざわりである。そしてお茶は、陶器や木工品などと同じく民藝的なもの、という思いも奥村さんにはある。
奥村 茶摘みから作る過程も見ているから、大事に淹れたいという思いに自然となりますね。茶器を先に湯で温めるのは茶葉を開きやすくするという意味もあり、茶葉の量と茶器の大きさのバランス考えるのも、おいしく淹れるためには必要です。

「気の抜けない作業も、どこかあっけらかんと行う職人たち。土地、風土という個性を生かしながら、人の手や感覚が加わってできあがる。そんなお茶作りを、僕はとても民藝的と感じたのだ」(『増補版 中国手仕事紀行』より)(本の情報はコチラ)

最近の買い付け先は主に中国、中でも福建省と広東省が多いという。
奥村 食べることや料理も好きですから、旅先では市場もよく訪ねるんです。魚の仲卸の店頭には、さっき僕が淹れたみたいなお茶のセットが必ずあって、ゴム長姿のおっさんたちが休憩のとき自分で淹れて飲むんですよ。その感じがもう、むちゃくちゃ良くて(笑)。ホント、日常にお茶がある。
奥村さんが出会った台湾のある茶人は、「(中国茶には)日本の茶道のような様式はない。基本的に楽しければいいんだ」と語ったそう。
奥村 とはいえ、人それぞれにお茶の楽しみ方があります。しつらえに凝る人もいるし、季節感を大事にする人も。いろんな美学があって、それぞれが自由。そのぐらいの距離感が僕にはちょうどよく、ありがたいんです。