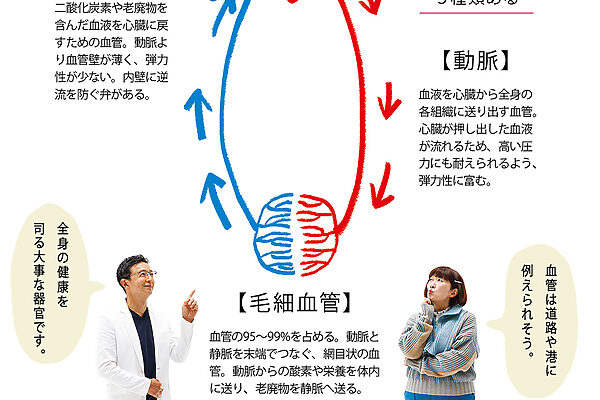『書き出し小説名作集 挫折を経て、猫は丸くなった。』天久聖一さん|本を読んで、会いたくなって。
日常の景色を「小説」にスライドする面白さ。

撮影・森山祐子
「私が嫉妬する女はいつも、花の名前を名乗っていた。」「『これの色違いありますか?』八百屋に妙な客が来た。」「党は分裂をはじめ、やがて見えなくなった。」——。
物語の冒頭、たった一文を提示する「書き出し小説」。ミニマムな情報から、どこまでも空想を広げられる自由さが魅力的だ。もともとはウェブサイトの読者投稿企画から始まった試みだが、将来新しいジャンルとして成立するのでは、という勢いを見せている。本書は、過去に投稿された〈書き出し作家〉たちの作品の中から天久聖一さんが選りすぐった416篇を収録したものだ。
「『国境の長いトンネルを抜けると雪国であった』とか、『我輩は猫である』とか、有名な書き出しって、作品全体を読んでいなくても妄想の余地があるんですよね。最初は、そういった名作書き出しのパロディのつもりで始めた企画だったんですが、何回も作品を募集しているうちに、書き手の皆さんの目線が洗練されていって。書き手と受け手の共犯関係で完結する、新しい文学ジャンルなのでは、というのが徐々に見えてきました」
現在では、募集ごとに1000通を超える応募が来るように。
「いくつか理由はあると思うんです。もともと日本人は、短歌とか俳句とか、短い文章にそれ以上の意味を込めることが好きじゃないですか。文章に限らず、電化製品なんかも、小型化されたボディに多くの機能を見立てようとしますよね。また、小説とうたっている以上は、フィクションであることが前提ですから、俳句や短歌のようにものごとを写生しなくてもいいので、作品を作りやすいのも特徴ですかね。日常を見つめる目線を小説風にスライドすると、くだらないことが純文学風になる面白さがあります」
どの書き出しも、アマチュアが考えたとは思えないほど、妄想の世界へのドアとしての役割を見事に果たしている。
「いくらサッカーが得意でも、プロ選手に混じって90分ピッチで走り回って勝つのは無理かもしれない、でもPK戦だけなら勝てるかもしれない。テレビ番組で、芸能人がプロ選手に挑んで勝ったりしてるじゃないですか。それと同じで、小説を一編書こうと思ったら作家に適わないかもしれないけれど、書き出しの瞬間風速だけだったら、プロに匹敵する、勝てるものを作れるんです。そういう、変則的な競技として面白がってもらえたらいいなと思います」
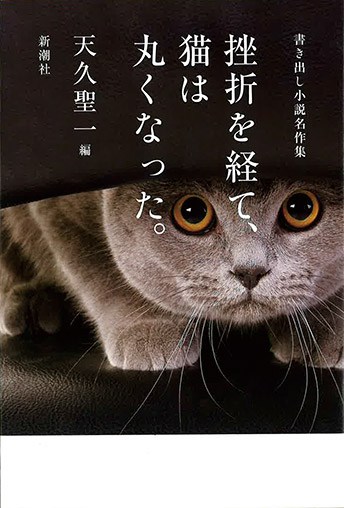
広告