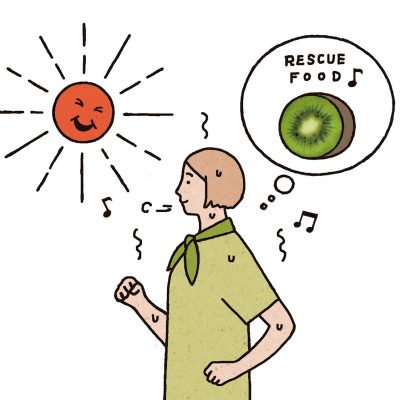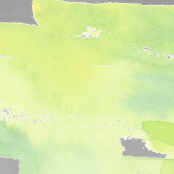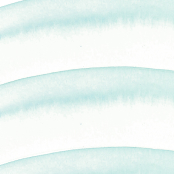中嶋朋子さんの人生の道しるべとなった、ミヒャエル・エンデ。
撮影・岩本慶三 文・嶌 陽子 ヘア&メイク・新田美佐子
変化しつつある自分に戸惑い、揺れ動いていた時期。中嶋さんは、『ものがたりの余白』に出合った時の自分をそう振り返る。「もう勢いだけでは進んでいけない年齢だし、自分の人生というものがはっきりと仕事に表れてくる段階に差しかかってきた。私が今までやってきたことは合っていたのか、このままの道でいいのか。行く先の灯りを見つけたいという気持ちがありました」
誰かに背中を押してもらいたい、“間違っていない”と思いたい。そんな心を抱えつつ、ページをめくった。「読んでいるうちに、“間違ってもいいんだ”と思えたんです。自分が今いる状況を、ありのまま受け止めてみようという気持ちになれたんですよね」

確固たる信念を持つこと、ユーモアを忘れないこと、柔軟な心を持つこと。エンデが自身の文学に通底する思想を語った言葉のひとつひとつが、中嶋さんの道しるべとなった。「なかでも印象的なのが、“光と闇”についての考え。エンデは、闇があるからこそ光の値打ちがあるのだと、闇の大切さを説いています。それは、まさに私自身、小さい頃から思っていたことなんです。私も、ずっと闇というものに関心があったし、子どもの頃も少しダークな部分、いわゆる“エグミ”がある物語じゃないと惹かれなかった。それはなぜなんだろうって。その謎解きをしてくれたのがエンデでした」
幼い頃からテレビドラマ『北の国から』の子役として注目を集めてきた中嶋さん。自身が演じた“蛍”という役柄同様、自分も“いい子”でいなくてはならないという呪縛もあった。
「でも、“闇は闇としてあっていい、それをちゃんと見つめて先に進むことが大切”というエンデの考えに出合って、そうか、人間ってそういうものなんだって。あるがままでいいんだと許された気がしたんです。それは、『はてしない物語』などの作品でもきちんと語ってくれています」
日々の生活でも、物事のとらえ方や考え方がかなり変わった。そのことを「いろんなスイッチを手に入れた感じ」と、中嶋さんは表現する。
「物事をほんのちょっと角度を変えて見てみるだけで、許せるようになったり、笑えることに変わったり。怒りも、ただ怒りのまま終わるのではなく、考えることや発見につながりました。そうすると、気持ちもふわっと楽になるんですよね。常にそんなふうに上手にできているわけではないけれど、そういうスイッチを持っていると思うだけで、ちょっと安心できます」