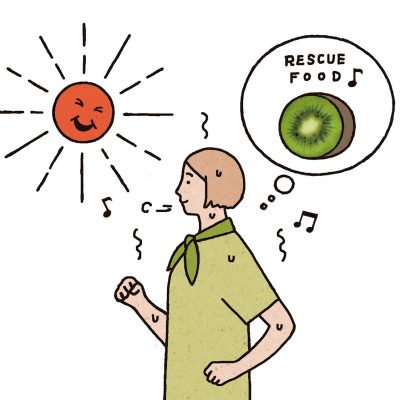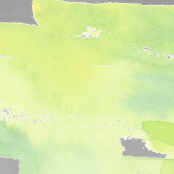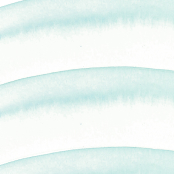12歳の少年の瞳が捉える過酷な現実と希望とは?映画『存在のない子供たち』
文・坂上みき

深い悲しみを湛えた少年の瞳に、何度も胸を締め付けられた。“目力”というのとはちょっと違う。口をへの字に結び、虚空を見つめ、絶望の淵を彷徨うかのような、悟ったような、諦めたような、大人の表情。これが演技だとしたら、この子は一体ナニモノなのか?
物語の舞台は、中東の貧民窟。12歳のゼインは、他の兄弟たちと重なるように狭い部屋で眠り、朝から働きづめの日々。学校に行かせてもらえないどころか、出生届けも出されなかったので、法律上、彼は、この世に存在しない。唯一仲良しだった11歳の美しい妹は、生理が来たとたん、大人の男に嫁がされてしまう。家を飛び出したゼインに、さらに過酷な現実が。そして、衝動により起こした事件で捕まった彼は、獄中から両親を訴える。なんの罪で? 「僕を産んだ罪」で。

自分も子を持つようになってからというもの、いわゆる「子供もの」には滅法弱い。「えっ? そこで!」ってくらい些細なシーンで涙腺崩壊、滂沱の涙。でも、この映画では泣けなかった。いや、おいそれと泣いてはいけない気がしたのだ。それくらい悲しみの次元が違っていた。
演じるゼイン君(役名と同じ)は、シリア難民で、役と近い境遇を生きてきた。ベイルートのストリートでキャスティング・ディレクターの目に留まったという。どうりで、「天才子役」などというヤワな言葉では括れない空気が漂っていたワケだ。他のキャストもほぼ全員、一人一人の半生がすべて物語になってしまうほどの過酷さで、撮影中に違法就労で逮捕された者もいる。まるでドキュメンタリーのようなリアルな肌触りが、深いところにズンと響く。

レバノン人の女性監督ナディーン・ラバキーは、知ってもらうことが大事と力説する。スマホのトップニュースがタレントの不倫、みたいなぬるい日本においてはなすすべもないのだが、「知った」ことは大きい。
ラストには希望が。その表情を見て初めて、ジュワッと涙が溢れ出た。

坂上みき
(さかじょう・みき)●パーソナリティー、ナレーター。現在『坂上みきのエンタメgo!go!』(ラジオ日本/月~金曜 8時50分~)に出演中。
『存在のない子供たち』
監督・脚本・出演:ナディーン・ラバキー 脚本:ジハード・フジャイリー、ミシェル・カスルワニー 出演:ゼイン・アル=ラフィーア、ヨルダノス・シフェラウほか。東京・シネスイッチ銀座、ヒューマントラストシネマ渋谷ほかで上映中。
『クロワッサン』1002号より