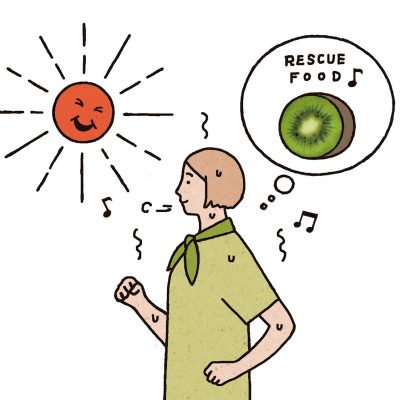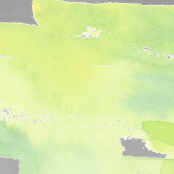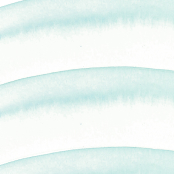『夢見る帝国図書館』著者、中島京子さんインタビュー。 「上野の図書館をいつか書いてみたかった」
撮影・黒川ひろみ(本)岩本慶三(著者)


「上野にある国際子ども図書館について、いつか書きたいと思っていたんですよね。建物がとてもすてきなのですが、当初の設計ではロの字型だったのが実際にはその一辺しかできなかったとか、多くの作家たちが訪れたなどの、歴史的な逸話がぽろぽろあって」
中島京子さんが語るように、物語の中で、図書館は主役を担い、その歴史が語られる。福沢諭吉の提言により近代国家に必須として図書館建設は始まるが、一筋縄ではいかず難航。その後、永井荷風の父・久一郎が奔走し、明治5年に開館した日本初の近代図書館には名だたる文人たちの若き姿が、そこここに現れる。現在の国際子ども図書館の前身である帝国図書館は、明治39年に完成した。
一方で描かれるのが、中島さんいわく「図書館の妖精、もとい魔女」のような女性、喜和子さんの生涯。語り手である「わたし」は作家であり、ライターだった当時に国際子ども図書館を取材した帰り、上野の公園のベンチで偶然隣に座った喜和子さんと知り合う。奇抜なファッションに身を包み、レトロな長屋住まいの彼女と、不思議と気が合い、交流は続くことになる。屈託がなく、自由に暮らす、母親のような年頃の喜和子さんに「わたし」は惹かれるのだが、実はその人生には小さな、時には大きな謎が垣間見えるのだ。喜和子さんの人生に散らばる謎が立ち現れ、解きほぐされていく過程と、近代の幕開けに誕生した帝国図書館の歴史。それらが交錯しながら、物語は進んでいく。
文化もあって、猥雑で。上野は身近で好きな街。
舞台となるのは、上野から谷中にかけての界隈。そこから御茶ノ水、根津、湯島まで、二人はたびたび歩き回り、さまざま語り合う。
「東京というと、メトロポリタンでとんがったものがある、特に私の若い頃はそんなイメージが良しとされた時期だった。けれど、上野はそれとは違う、文化の漂う雰囲気ながら、猥雑な感じもあって。そんな上野が好きで、書きたいなというのもあったんです」
帝国図書館が存在した上野と、喜和子さんを結びつけていたのは何だったのか? その謎こそが、物語の要のひとつとなっている。喜和子さんを彼女たらしめているもの、幼い頃の幸せな記憶がそこにはあるのだ。中島さん自身も、幼い頃の図書館を記憶している。
「当時住んでいた団地の集会室にお母さんたちが作った子ども文庫があったんですね。毎週土曜日になると借りに行って。あそこに行けばいくらでも本が読める、というのが自分には幸福な思い出ですね。並んでいる本全部を読んでいいんだ、という。図書館というものがすごく好きでした」
自分であることの自由を取り戻すために奮闘したひとりの女性の人生と、人間を真理によって解き放つ図書館という存在と。ふたつが不思議と混じり合い、登場人物たちと読み手をも解放してくれる、愛すべき、希有な物語である。
『クロワッサン』1001号より