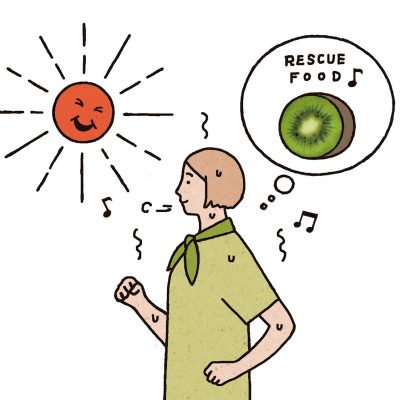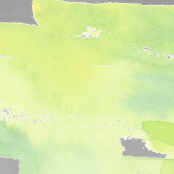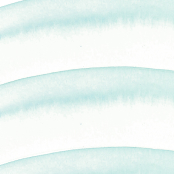『影を歩く』著者、小池昌代さんインタビュー。 「人間の生を多重線でつかまえてみたい」
撮影・黒川ひろみ(本) 谷 尚樹(著者)


そのもの本体よりもその影のほうが時に気になる。小池昌代さんはもともとそんなたちだった。
「街路樹本体よりも、その一本一本から伸びた濃い影にじっと見入ってしまったり……」
近年、百人一首を現代語に訳すという機会があって、影という言葉を古語辞典でひいた。すると、
「影はもともと光という意味も含んでいたらしいです」
たとえば“月影”の影は、光に置き換えるとわかりやすい。
「影と光はかつて分化していなかった。いつか影をテーマに作品を書こうと考えていたので、ならばこの分化してしまったものをもう一度まとめて書いてみようと」
4編の詩、14編の短編からなる本作にはさまざまな影が登場する。結婚運がない娘の顔にさす影、お墓のお供えを盗みにくる小さな人影、海の波の底に見えるひとの面影……。しかし、小池さんの筆がとらえるのは影そのものではない、影が引き連れてくる周辺の曖昧な何かである。
もともとはエッセイの連載としてスタートしたものが。
面影という言葉は不思議だ。それを口にするだけで、どこか物悲しい気持ちになる。
「普段はこのひとの顔はこうと思っていても、ひょんな拍子にそれがゆらめき、二重映し、三重映しに見えることがある。面影とはきっとそのひとの顔から立ちのぼってくる蜃気楼のようなもので、生きるということもきっとそれと同じ、多重線でできあがっているのではないか」
短編「水鏡」では主人公の夫がフェリーから転落死する。が、もしかするとそれは自殺ではないか。人生の真実は誰にもわからない。
ところで、本作品に収められた掌編群は版元である出版社のウェブに連載されたものをまとめたものである。そして、どの作品も、どうみても小説の手触りであるのだが、もともとはエッセイとして開始されたものだという。
「エッセイとして書き始めてもどうしてもフィクションに寄っていってしまう。それは書かれるものの宿命だと思う」
何かについて書くと、確かにそうだったよね、でも本当はこうだったでしょう? と、書いたものが次々とほかの何かをおびき寄せてくる、それこそ多重線で輪郭を引くように。
「正解はひとつではない。近年ますますそう考えるようになってきました」
虚と実、そのあいだを揺れ動く振り幅がすごい。ある作品では「小池さん」と本人の名前がそのまま出てくるかと思えば(「不思議な矢印」)、ある作品では登場人物の男性が敷布の上で液状化して消えてしまう(「あみゆるよちきも」)。
「本当はこうだったよね、と亡霊のように立ち上がってくるものに自分は蓋をすることができない。それを書かないわけにはいかない」
真実とは何か、そして生きるとは? 小説の生まれる瞬間を閉じ込めたような作品集である。
『クロワッサン』997号より