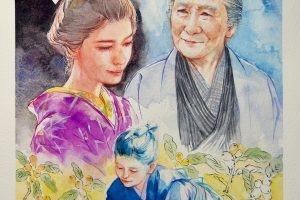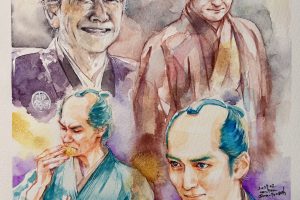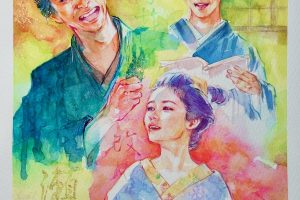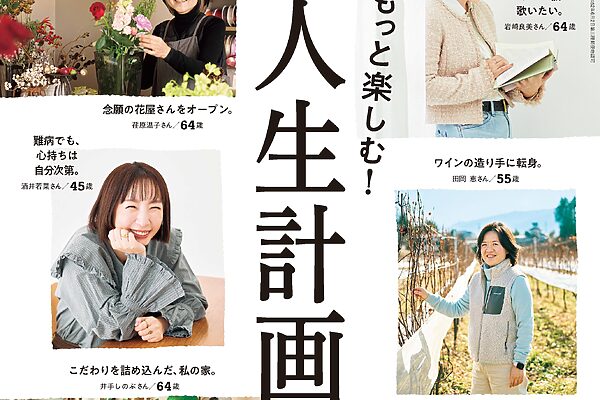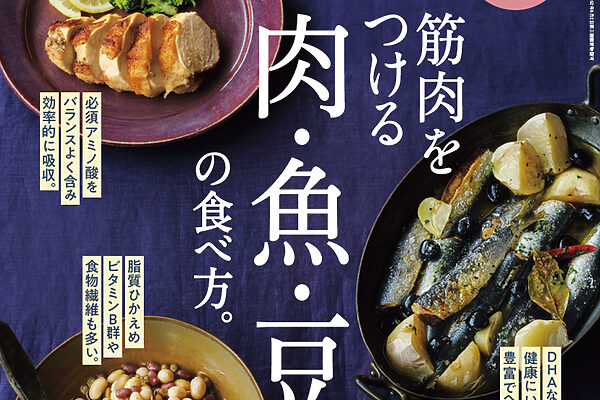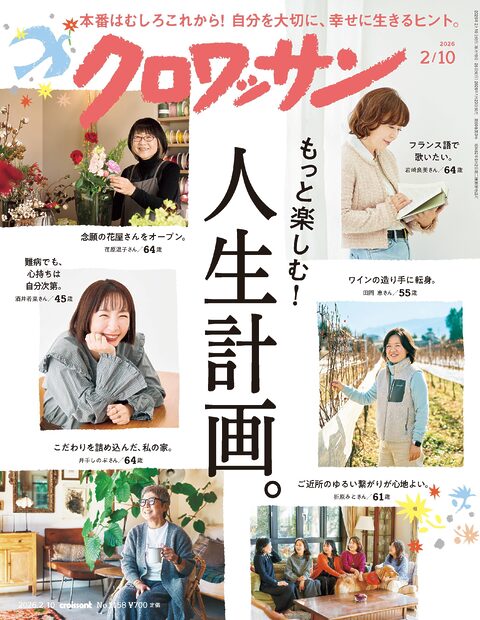考察『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』7話 花の井(小芝風花)「まかせたぜ、蔦の重三」男前すぎるぜ五代目!お値段以上「細見」大作戦の熱い展開
文・ぬえ イラスト・南天 編集・アライユキコ
倍売れる「細見」

第7話は江戸城の描写は一切なく、蔦重(横浜流星)の地本問屋への熱き戦いを描いた。そして、これまではチラリチラリと垣間見せていた、江戸時代の身分制度と差別を前面に打ち出してきた回だ。
鱗形屋孫兵衛(片岡愛之助)が偽版出版で捕らえられた。地本問屋仲間の寄合では、彼が手がけてきた「吉原細見」の出版を今後誰が請け負うのかという問題が発生している。
吉原に客が戻ってきた今、「細見」は金の成る木だ。地本屋たちは我も我もと手を上げる。
そこに乗り込んできた蔦重は、自分が版元(板元)となって「吉原細見」を出す、鱗形屋逮捕で空いた席に、新たな地本問屋として加えてもらうと宣言した。
蔦重「倍売れる『細見』を出してみせやす」「そうなりゃ皆さんだって儲かる、悪い話じゃねえでしょう」
地本問屋は出版元であると同時に、小売りの書店でもある。今までより倍売れる書籍なら、欲しくないわけがない。鶴屋喜右衛門(風間俊介)は、倍売れる「細見」を持ってきてみろ、そのうえで本当に倍売れたら仲間に加えるという約束をした。
蔦重が帰ったあと、その約束をした鶴屋に西村屋(西村まさ彦)をはじめ、地本問屋たちが抗議する。
松村屋弥兵衛(高木渉)「ごめんですよ、ここに吉原者を入れるのは! 」
江戸市中において、吉原で生きる者たちへ向ける目は厳しかった。文化13年(1816年)成立の随筆『世事見聞録』(武陽隠士)では忘八らを「天道に背き、人道に背きたる業体にて、およそ人間にあらず。畜生同然の仕業、憎むにあまりあるものなり」と記す。
ドイツ人医師ケンペルは『日本誌』(1727年)で「彼がいかに裕福でも、決して公正なる市民とは認められない」。遊郭の楼主と、それに付随する商いをする者たちが日本社会でどう見られていたかを記録した。
幕府公認の遊郭・吉原。政府がその存在を保証した組織は、賤業とされていたのだ。
鶴屋「倍なんて売れるわけありませんよ」「蔦重の『細見』がさほど売れぬよう、よい『細見』を出すという手もありますよね。どうでしょうか、西村屋さん」
鶴屋喜右衛門のにっこり笑顔の圧力が怖くていい。蔦重に条件提示しつつ、細見の売り上げで直接対決するリスクは西村屋におっかぶせてしまうというしたたかさ。
ドラマファンとしては待望の、悪い役を演じる風間俊介! よっ、待ってました!
「俺も張った!」
蔦重は忘八連合に話を通しに行った。今回、忘八らがやっている遊びは「穴一(あないち)」だろうか。銭を穴や桝に向かって投げ入れて、入らなかった者の銭を入った者が総取りする博打である。
大文字屋市兵衛(伊藤淳史)に勝手なことをしやがってとぶん殴られても、蔦重は引き下がらない。吉原の者である蔦重が認められたら、吉原が自前の地本問屋を持てる。外部業者である他の地本問屋に委託せずとも『雛形若菜』のような外部業者とのタイアップ本も、行事の摺物──集客イベントのお知らせも、吉原発で江戸市中に売ることができる。
大黒屋りつ(安達祐実)「そりゃ吉原を売り込み放題にできるってことかい?」
一瞬だが、この安達祐実の芝居がたまらない。そりゃうまい話だねェという表情。
大黒屋も他の忘八たちも、蔦重の出た賭けに「張った!」「俺も張った!」と大ノリだ。
だが意気揚々と引き上げる蔦重の背中を見送る、義父・駿河屋市右衛門(高橋克実)の表情は冴えない。可愛い息子が本屋になるのが面白くねえのかとからかう扇屋宇右衛門(山路和弘)に、
駿河屋「こりゃ上手く行きゃ、市中のやつらが俺たちを認めるってことでしょう。そんな筋、真に受けていいもんなんすかねえ」
駿河屋は蔦重の話に懐疑的だ。そしてその言葉を傍で耳にした駿河屋女将・ふじ(飯島直子)はそっと目を落とす。駿河屋夫妻のその様子に、長年まともな人間として扱われてこなかった吉原者の、これまでの人生を想像した。
お値段以上「細見」大作戦!
鱗形屋孫兵衛は奉行所に捕らわれた後、厳しい取り調べを受けていた。「偽版作りは小島松平家の家老からの発注であった」と本当のことを述べているのだが、聞き届けてもらえない。
役人から「武家に罪をなすりつけるつもりか!」と、殴る蹴るが続く。
8代将軍・吉宗が命じて制定された法典『公事方御定書』では死刑に相当する罪人、凶悪犯以外への拷問の濫用が禁止された。石抱などの責め問いも制度化されたが、今回のような素手での殴打は拷問、責め問いにはカテゴライズされなかった。このシーンのように自白の強要は横行していたのではないだろうか。非道極まりない。
蔦重を吉原者と蔑む地本問屋に属する鱗形屋が、武士に腐れ商人と罵られ虐げられる。
平和を謳歌し豊かな町人文化が花開く江戸時代だが、その底には覆しがたい身分制度と差別があった。
恐ろしい取り調べを受けている孫兵衛を見て、これは密告したと勘違いされた蔦重は、さぞ恨まれているだろうな……と想像した。
鱗形屋孫兵衛の偽版作りを知りながら、捜査の手が伸びようとしているときに黙っていたという自責の念を抱える蔦重。それでも前に進もうとする彼を愛おしく思い、よしよしする義兄・次郎兵衛(中村蒼)に今週も和む。撫でやすい月代(さかやき)部分じゃなくて髷をよしよしするの、なんで? と思いつつ笑っちゃう。ほんとになかよしだねえ。
そして蔦重が立てた作戦は。「吉原細見」を倍売るためには、書店にそれだけの数を仕入れてもらわねばならない。ならば、売り値を半額にすれば、従来の仕入れ値で倍の冊数を置いてもらえる。しかも、これまでよりも良い内容のものを。お値段以上「細見」大作戦!
早速どんな「細見」だったら欲しいのか、マーケティングリサーチが始まった。次郎兵衛だけでなく二文字屋の女将・きく(かたせ梨乃)、蕎麦屋の主人・半次郎(六平直政)も協力して、吉原に来る客らに意見を求める。
今週の尾美としのりは、このリサーチ場面。蕎麦屋の画面向かって左端の席で蕎麦をたぐっている。前回よりも難易度がちょっとだけ高い。
かなりの数の「貴重なご意見」が集まったのち、更に強力な助っ人が現れた。平賀源内(安田顕)の助手で、松葉屋のうつせみ(小野花梨)の馴染みである新之助(井之脇海)だ。
新之助「もう少し薄くならぬか? この厚さでは懐に入れたとき、かさばるではないか」
蔦重「薄く……これだ!!」
薄くすれば紙にかかるコストを低く抑えることができる。薄くて持ち歩ける、そして内容が充実した「細見」。これを目指して蔦重たちと助っ人陣の奮闘が始まった。既存の商品を分析し、改善点を洗い出す。持ち運びやすくする以外に、実際の店の並び通りに頁を構成する案が出た。これらは現代でいうところの、旅先での街歩きガイドブックで想像すれば、なるほどと思えるアイデアだ。
蔦重に対抗して新しい「細見」を出版する西村屋も案を練っていた。主・孫兵衛のいない隙に鱗形屋に乗り込んで「吉原細見」の版木(板木)を買い取ればコトは簡単だったが、妻のりん(蜂谷眞未)と次男坊の万次郎(野林万稔)に突っぱねられたのでそれはできない。西村屋・手代の忠七(斉木テツ)が、一から版木を起こして本を作るのはかなりのコストがかかるので無理をしてやらずともよいのではないかと、やんわり意見する。西村屋は吉原という大きな宝の山をみすみす逃す手はないと、計画を進める意向だ。そこで忠七は鱗形屋ほどの大手ではないが、「細見」を作っている人間──浅草の摺物屋・小泉忠五郎(芹澤興人)を思い出す。これだ! 西村屋も閃いた。
ところでこの場面は、手代の忠七が膝枕で西村屋与八の耳かきをしていることで、彼は与八にとって公私ともにパートナーなのだと伝わる。与八は膝枕でリラックスして仕事の話をするし、忠七は店のことを把握しているので答えることができるし。ドラマの中で憎らしげな立ち回りをしている西村屋与八だが、人間味ある一面が垣間見えてとてもいい場面だった。
花の井の晴れやかな笑顔
西村屋手代・忠七が指摘したように、新しい細見制作は多くの手間と費用がかかるものだ。薄くして低く抑えられる経費は紙代だけで、人件費は従来通りかかるはず。そこを蔦重は、新之助にはうつせみの揚代を、彫師・四五六(肥後克弘)ら職人には吉原での大宴会を奢るということで、ボランティア或いは破格の手間賃で仕事を引き受けてもらっている。
揚代にしろ宴会にしろ、蔦重紹介の客だからといって吉原の忘八らが安くしてくれるわけではない。細見の売り上げからその費用を出すのでは、蔦重はまったく儲からない。
深川や品川など他の遊郭で遊ばせろと言われたらお断りだが、吉原で遊んでくれるというなら大歓迎だと笑う蔦重に、新之助は「蔦重の吉原への思いは李白の『静夜思(せいやし)』のようだな」と微笑んだ。
『静夜思』は中国唐の時代の詩人・李白の、月光を見てひとり静かに故郷を思う詩である。
吉原は蔦重にとって大切なふるさとなのだ。新之助の言葉に嬉しそうに微笑み返す蔦重は、かなりの教養人だ。だてに本を扱っていない。
そこへ、忘八連合から蔦重へ呼び出しがかかった。
西村屋は忘八たちに、小泉忠五郎と組んで「細見」を出版するという宣言と、忠五郎がこれから吉原の各女郎屋に改めのために回るからよろしくと挨拶をしていた。
しかも、蔦重の「細見」を買った女郎屋の女郎は、今後『雛形若菜』に掲載しないという脅迫とセットだ。『雛形若菜』は蔦重が身を引いた後も大人気シリーズとして続編が出版され続けていた。この成功で味をしめたからこそ、西村屋は吉原にこだわっている。
蔦重が西村屋と組んで『雛形若菜』を出版するのは地本問屋ではないからと許されなかったのに、今回限りとはいえ地本問屋でなくとも忠五郎なら良いとされるのは筋が通らない。
それはつまり、蔦重が吉原者だから弾かれたのだと悟り、同じ吉原者として忘八たちの表情は一様に険しくなる。
ここで忘八連合を説得する蔦重の演説が抜群によい。
蔦重「やつらに流れる金は、女郎が体を痛めて稼いだ金じゃねえですか。女郎の血と涙が滲んだ金を預かるなら、女郎に客が群がるように、その中から客選べるようにしてやりてえじゃねえですか」「吉原の女はいい女だ、江戸で一番だってしてやりてえじゃねえですか。胸はらしてやりてぇじゃねえですか」
「女郎が体を売って稼いだ金」ではない「体を痛めて」。吉原で育った彼は今まで女郎が傷つく様を、きっと嫌というほど見てきている。閑古鳥が鳴く遊郭では、たちの悪い客でも断れない。「客選べるようにしてやりてえ」という言葉に、キツい客を引き受けたという朝顔(愛希れいか)を連想する。台詞ひとつひとつに無駄がない。
蔦重「それが女の股で飯食ってる、腐れ外道の忘八の、たったひとつの心意気なんじゃねえっすか」
下品な台詞である。長年の大河ファンで多くの作品を観てきたが、こんなにも下品な台詞は今まで聞いたことがない。
だが本作『べらぼう』の主人公、横浜流星が演じる蔦重は、これでいい、これがいいのだ。
吉原者が蔑まれていることも、その理由も知っている。その一人である自覚もある。八つの徳を忘れても、人間としての矜持を持てよ! と忘八たちを叱咤する熱さに震える。
吉原発の地本問屋を生むために、共に戦ってほしい。この地をふるさととする男、蔦重の願いに、松葉屋主人・半左衛門(正名僕蔵)と女将・いね(水野美紀)も動いた。ことの顛末を聞いていた花魁・花の井(小芝風花)に、半左衛門が声をかける。
半左衛門「花魁。ひとつ、俺たちも考えてみるかい。『細見』を倍売る手立てをさ」
花の井「あい!」
この場面での小芝風花の芝居が繊細だ。蔦重の名を聞きつけて廊下に出る、そこから松葉屋主人夫婦の会話を聞く心配そうな表情。主人から表立っての協力を持ち掛けられ、嬉しそうに答える晴れやかな笑顔。いつも重三の前では幼馴染としての態度を崩さないが、この短い時間で花の井が心の底から蔦重を愛していることを、観ている我々は知るのだ。
吉原の女郎とここで働く男の恋は御法度である。通じあえば厳しい制裁が待っている。だから、花の井は心を蔦重に明かさない……蔦重のために。
そして松葉屋主人夫婦は、とうの昔に花の井の恋に気づいているに違いない。
吉原一番の大見世・松葉屋が総力を挙げて蔦重を応援する展開も、これまた熱い。
花の井改め瀬川
西村屋が本気を出して潰しに来たとわかり、蔦重に更にエンジンがかかった。マーケティングリサーチで得た意見の通り、大見世以外の中見世、小見世、切見世と、すべての所属女郎たちも漏らさず掲載する。蔦重が改めで調査してくるたびに、原稿を書く新之助、版木を彫る四五六が、何度も何度もやり直し。情報がまとまったら持ってきてあげて! と思うが、おそらく吉原の全ての見世で次々と女郎が入れ替わるためにこうなってしまうのだろう。字はどんどん細かくなる、新之助も四五六も気の毒……。
松葉屋では女将いねが「見切ったざんす!『細見』がバカ売れするのは、名跡の襲名が決まったときさ!」おお! と盛り上がる半左衛門。
この見切ったざんす! の時の水野美紀が、とってもキュート。水野美紀はこれまでも随所でテンポの良い細かな芝居をしているので、ぜひ注目してほしい。
『一目千本』のときと同じく、切見世・二文字屋で製本された新しい『吉原細見 籬(まがき)乃花』。もう出来上がってしまったこの本に、もう一人名を改めた女郎を加えてほしいと花の井が蔦重に差し出した紙に書かれた名は「花の井改め 瀬川」!
先代(四代目)の瀬川が身請けされて間もなく自害してしまったことで次の襲名を避けたゆえに、20年空いてしまった。なぜ自害したのか詳しくは伝わっていない。
松葉屋瀬川は女将いねが語った通り、今にも伝わる有名な名跡だ。落語にはその名もズバリ
『松葉屋瀬川』という噺がある。この噺の後半部分には「雪の瀬川」という、ゆかしい題名がついている。「雪の瀬川」では松葉屋の花魁がまことの恋を叶えるのだが、花の井は──五代目瀬川が胸に秘めた恋は、果たして──。
彼女は自分にしかできないことで蔦重に合力したのだ。礼をのべる蔦重に、いつものクールな笑みで「まかせたぜ、蔦の重三」。男前すぎるぜ、五代目!
吉原の皆の願いを背負って、蔦重が地本問屋仲間に乗り込んでゆく。
これは倍売れる!
地本問屋仲間での本の仕入れ会場で蔦重がスッと懐から取り出した『吉原細見籬乃花』に、皆が注目する。歩きながら使えるよう、薄く見やすく。今の吉原の情報が全て入った一冊。そしてとっておき、大名跡・松葉屋の五代目瀬川の名! 最新情報は西村屋の『新吉原細見』には入っていない。
蔦重「吉原の外にいる方に応じろというのも、難しいでしょう! 」
吉原者だからこそ作れた「吉原細見」だと示して見せる。しかも値段はこれまでの半分だ。
狙いは金持ちではなく、江戸市中にいる一般庶民の男性。『新吉原細見』は今まで通り48文『籬乃花』は24文。江戸時代のファストフード、蕎麦一杯は当時16文。
便利で安くて、初めて五代目瀬川の名が載る祝儀の細見というレア感なら……倍売れる!
たちまち、仲間内の義理もしがらみもかなぐり捨てた地本問屋たちからの注文が殺到した。
痛快そのものの展開だが、たくらみが砕かれた鶴屋喜右衛門の顔がこわいよ。
そして、鱗形屋に孫兵衛が戻ってきた……須原屋市兵衛(里見浩太朗)が迎えに行ったのか、頼りになる。ていうか地本問屋の仲間、誰も迎えに行かなかったんかい。
鱗形屋の逆襲が始まる!
次週予告。出たっ『金々先生』! 第1話(記事はこちら)の花魁道中と比較してみようぜ。着物の下に筋肉が隠されていそうな坊主が出てきた。口笛はちょっと下手です花魁。「耕書堂さんの仲間入りはなかったことに」えっ今なんて言った?
8話が楽しみですね。
*******************
NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』
公式ホームページ
脚本:森下佳子
制作統括:藤並英樹、石村将太
演出:大原拓、深川貴志、小谷高義、新田真三、大嶋慧介
出演:横浜流星、安田顕、小芝風花、高橋克実、渡辺謙 他
プロデューサー:松田恭典、藤原敬久、積田有希
音楽:ジョン・グラム
語り:綾瀬はるか
*このレビューは、ドラマの設定をもとに記述しています。
*******************