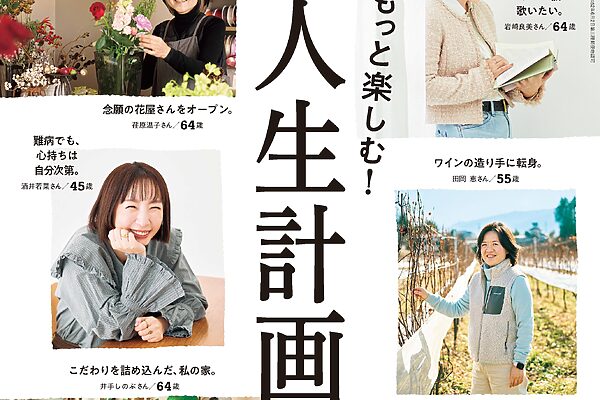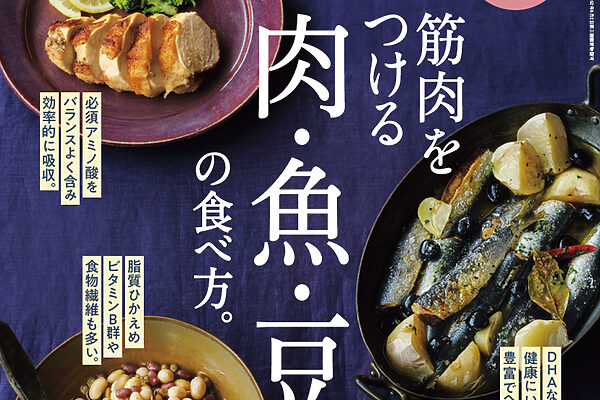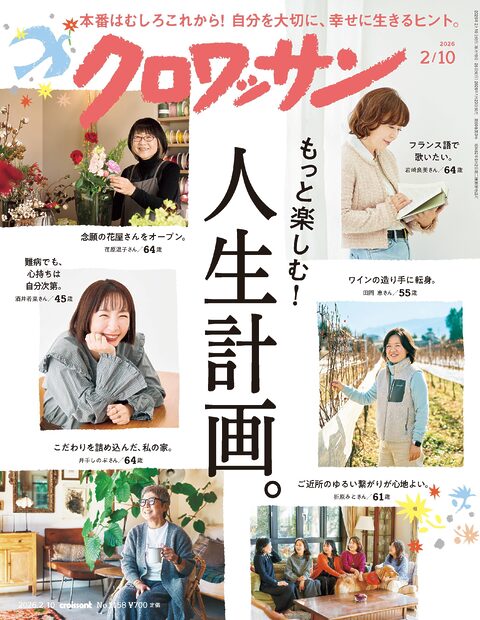はじめての介護:認知症の世界を理解して実践「ケアの目的はよい関係を結ぶこと、心が通う5つのステップ」
撮影・土佐麻理子 イラストレーション・イオクサツキ 通訳・石川裕美 文・松本あかね
ユマニチュードでは着替える、おむつを替える、体を拭くなど日常のケアを5つのステップを踏んで実践する。
1. 「出会いの準備」
2. 「ケアの準備」
3. 「知覚の連結」(実際のケア)
4. 「感情の固定」(ケアの振り返り)
5. 「再会の約束」
この5つのステップを連続して行う。「1つの物語」に例えられるこの流れを友人宅の訪問に置き換えてみるとわかりやすい。
人を訪問するとき、インターフォンを押さずに家に入り、用が済んだらさっさと帰ったりはしないのに、ケアの場ではこれと同様のことをしてしまっていることに気づかされる。逆にいえば、ケアの場でも友人宅を訪問するのと同様のステップを踏めば、相手の拒否に遭わず、和やかに終えることができるのである。
また、このステップを実践することによって、「楽しかった」「心地よかった」という『感情記憶』が残り、次のケアもスムーズにいく可能性が高い。そうやっていつものケアがお互いのよい関係を育む時間になっていく。
ステップ1. 出会いの準備:来訪を告げて了承を得る

3回ノックして、3秒待つ。ベッドボードや椅子でも。
友人の家のインターフォンを鳴らし、来訪したことを知らせるように、「あなたのプライベートな空間に入ってもいいですか?」という了承を得ることからスタート。
具体的には扉を3回ノックして3秒待つ。返事がなければもう一度3回ノックして3秒待つことを繰り返し、それでも返事がなければ1回ノックして「失礼します」と声をかけて入室を。
ノックするのは障子の桟、個室でなければベッドボードや座っている椅子の背もたれでもよい。
このように相手の反応を待つことも大切な技術の一つ。黙って部屋に入り、いきなり耳元で「オムツを替えますよ」と声をかけるとびっくりして嫌がられるのはいわば当然のこと。
うとうとしていたり、認知機能が落ちているために、状況を把握するのに時間がかかったとしても、ノックを繰り返すことによって、覚醒水準を徐々に高め、相手を驚かせずにすむ。
ステップ2. ケアの準備:ケアに入る前によい関係を結ぶ

いきなり用件を話さない。相手の嫌がる言葉は避ける。
部屋に入ったら、本人の顔の向いている方向から近づいて。
認知症の人は認識できる視野の範囲が狭いため、近い距離から急に視野に入ると驚かせてしまう。視野のトンネルの真ん中に入っていくつもりで近づき、本人から3メートルの位置まできたら視線を捉え、目が合ったら3秒以内に声をかける。
ただし、いきなりケアの話はしないこと。顔から遠い背中や肩からゆっくりと触れ、「見る」「話す」「触れる」技術を存分に使い、会えてうれしいという気持ちを伝えて。
相手から笑顔が返ってきたとき、または顔の近くを触れても大丈夫になったら、ケアの提案を。
もしお風呂が好きでないなら「身だしなみを整えましょうか」「お散歩に行きましょうか」など別の言い方で。このときもし「いや」とか、体をこわばらせるなど拒否のメッセージがあれば、いったん諦めること。ここまで3分以内を目安に。
ステップ3. 知覚の連結:4つの技術を用いてケアを行う

「見る」「話す」「触れる」技術を並行して用いながら。
「知覚の連結」とは3つの技術を使って視覚・聴覚・触覚にポジティブなメッセージを伝え続け、ケアを受ける人が心地よく、リラックスした状態になること。
このとき、優しい言葉をかけながら腕をぐっとつかむなど、3つの感覚の間に矛盾が生じないようにすることが肝要。もし、本人が好きではないケアの場合は、前向きになれる話に気持ちを向けるとよい。
「お隣がワンちゃん、飼い始めたんですって。ワンちゃん好きでしょう?」
認知症の人は同時に2つのことに注意を向けることが難しいため、犬の話に気持ちが向いている間にケアを進められる。
ケアの内容へ意識が向いてしまうと防御態勢に入る可能性もあるので注意を。ケアが終わる頃になったら、「きれいになったから気持ちいいね」と実際のケアに意識を向けるようにする。それから、「じゃ、ワンちゃんに会いに行こうか」などと促すとよい。
ステップ4. 感情の固定:ともに過ごしたよい時間を振り返る

「楽しい」「気持ちいい」、ポジティブな感情を残す。
ケアが終わったらすぐ立ち去るのではなく、一緒に過ごした時間を振り返るステップへ。
たとえば普段、お風呂が好きではないなら、今日はうまくいったということをポジティブな言葉だけを使って振り返る。
「お風呂に入ってさっぱりきれいになりましたね」「シャワーのお湯の温度もちょうどよかったですね」といったように、ケアの内容を前向きに振り返り、「協力してくれて助かりました」と相手の態度を前向きに評価する。
「私もとても楽しかった、ありがとう」と伝え、今日のケアがお互いにとっていいものだったと語り合うことで、苦手なお風呂のイメージをポジティブなものに上書きするのがねらい。
認知症の人も、“記憶の仕組み”で説明したように、感情記憶は覚えていてくれるので、次のケアを肯定的に受け入れてくれる素地になる。ここまでの振り返りは40秒程度で、長く行う必要はない。
ステップ5. 再会の約束:次のケアへつなぐ

カレンダーに印をつけても。次のケアもスムーズに。
最後のステップは、次回に会う日をお互いに確認し、具体的に約束をすること。このステップは、たとえ約束を忘れてしまう人にとっても必要な手続き。ポジティブな何かを約束したという記憶が感情記憶にとどまっていると、次に訪れたときに笑顔で迎えてくれる可能性がある。
また、約束をしたことが社会とのつながりを取り戻したという実感となり、ケアに対し前向きになってくれるなどの効果が期待できる。
約束をしたら「15時に来ます」「○月○日、○時〜、お風呂」といった具合に、具体的な日時をボードに書き留めたり、カレンダーに印をつけるなどするとよい。本人が何度も確認することができ、またそのことを周りの人と話題にするきっかけにも。
4つ目、5つ目のステップは次のケアを受け入れてもらいやすくするだけではなく、ケアする側の充足感にもつながる。
『クロワッサン』1134号より
広告