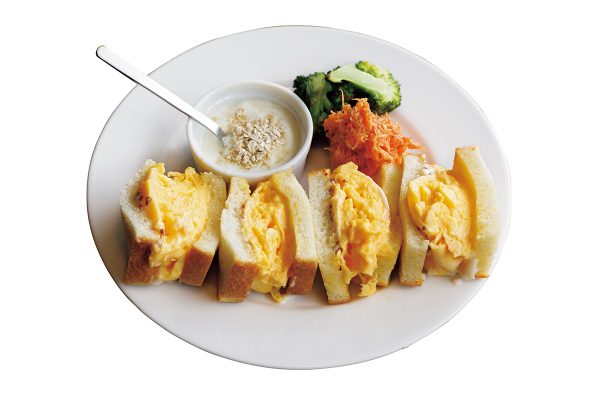華族制度の廃止をテーマに、没落する一族の姿を描いた『安城家の舞踏会』。同じ没落ものであるチェーホフの『桜の園』を下敷きにした脚本は、新藤兼人によるもの。名コンビ、吉村公三郎監督のドラマティックなカメラワークもキレッキレ。戦争中、思うように仕事ができなかったフラストレーションが、一気に爆発したかのようです。
主役の原節子は、高貴な美貌が華族令嬢という役柄にピッタリなだけでなく、自由と平等を尊重する新しい時代の精神を体現して、息を呑むばかり。事実、新藤兼人はセットに佇む原節子を、ライオンのような王者の風格を漂わせていたと語り、「誰も近づけなかった」と回想しています。
持てる者と持たざる者。日本映画では後者の野心が描かれがちですが、持てる者が失ってゆくときに味わう敗北と絶望の心理は、ゆるやかな下降線をたどるいまの日本の気分と、妙に重なる気がします。オリンピックという舞踏会を終えたら、過去の栄光はすっきり忘れて、価値観を一新しましょうや!
にしてもこの作品、1947年(昭和22年)5月の日本国憲法施行から、なんと4カ月後という驚異のスピードで公開されています。荘厳な雰囲気の文句なしの名作ですが、もしかしたらリアルタイムの観客の目には、超ホットな時事ネタを扱った、セレブのリアリティ番組、みたいに映ってたかも?