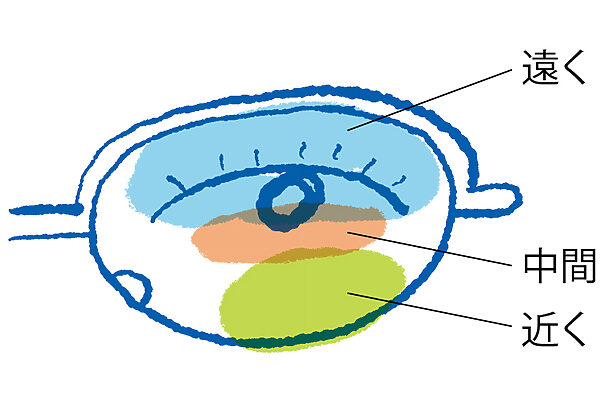「余命わずかと言われた父を大家族のようなホスピスへ」【助け合って。介護のある日常】
撮影・井出勇貴 構成&文・殿井悠子
「本人も家族も一人にしない大家族のようなホスピスで。」内田清子さん

「お父さまの余命は、もってあと1週間くらいでしょう」
2021年12月、神奈川県茅ヶ崎に住む内田清子さんは、訪問医にそう告げられた。父親の勝人さんは膵臓がんだった。
一般的に、自宅で看取りをするには介護する人が3人以上必要だといわれている。当時、鎌倉の実家に住む母親の睦子さんには、2017年頃から認知症の症状が出ていた。内田さんはなんとか自分の手で最期まで看病したいと思ったが、訪問医から専門の施設に入るべきだと何度も説得された。
間もなく、勝人さんが自宅で転んでしまった。骨折を防ぐためにも、内田さんは勝人さんのホスピスへの入所を決めた。訪問医が紹介したのは、’21年10月にオープンしたばかりのホームホスピス、シェアハウス『かのん』だった。
「できたばかりで大丈夫かしら?」。心配な気持ちで見学に行ってみると「ご家族も一緒に泊まって大丈夫ですよ」と、代表であり看護師の髙本征子さんが笑顔で迎えてくれた。
勝人さんがかのんに入居したのはクリスマスイブの日。髙本さんの計らいで、内田さんは空いていた勝人さんの向かい部屋を寝床にすることになり、まるで自宅のようにかのんで暮らした。医療的なことはスタッフに委ねた。
かのんの方針は、「一人ひとりの人生の物語を知り、本人が望む場所で望むように生を全うできるように支援を行う」こと。なかでも“生きる”に直結する食事を大切にしていた。
勝人さんは食欲がある時とない時の起伏が激しかったので、食べられる時に食べたいものをスタッフが作るようにした。大好きなアイスの〈ガリガリ君〉を冷凍庫に常備して。ある時は、「半熟のそのまた半熟の目玉焼きをください」と勝人さんがリクエスト。そうすると髙本さんが、とろとろの目玉焼きと小さなブレッド、それから果物をワンプレートにしてくれて、それを食べた勝人さんは再びぐっすり眠りにつく、ということもあった。


こうして、かのんで暮らした勝人さんは、1週間をとうに超え2カ月を生きた。その間、痛み止めを使うことは一度もなく、穏やかな親子の時間(とき)を最期に過ごすことができた内田さんと勝人さん。
今でも内田さんは、かのんのイベントに顔を出し、認知症が進んだ母の睦子さんのことを髙本さんに相談している。(続く)
『クロワッサン』1122号より
広告