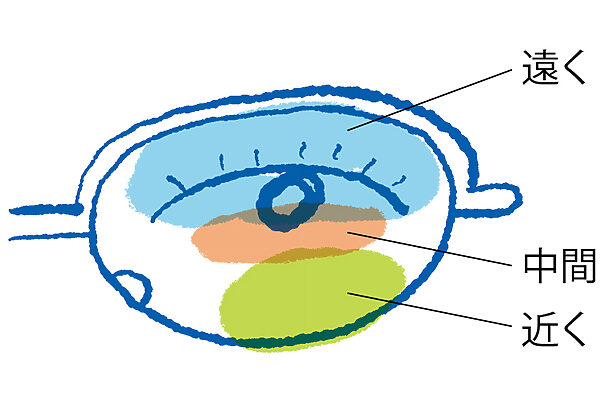『ウィスコンシン渾身日記』著者、白井青子さんインタビュー。「2年間の日記は、大切な生きがいでした。」

撮影・谷 尚樹 文・石飛カノ
夫の転勤で白井青子さんがウィスコンシン州マディソンで暮らし始めることになったのは、2015年の夏。31歳のときだった。
「キャリアもない、子どももいない、年寄りではないけど若くもない、英語を話すこともできない。行く前はとにかく不安でした」
その不安をぶつけたのは、大学時代のゼミの教授、哲学研究者でコラムニストの内田樹さん。恩師の口から出てきた言葉は、「ウィスコンシンの生活について日記を書いてみたら?」というものだった。
「生きがいじゃないですけど、大きなプレゼントをもらったなと思いました。素敵なものをもらったんだから、無駄にしたくない、と」
かくて月に1度の「渾身日記」を恩師にメールで送る日々が始まった。それが内田さんのブログでリアルタイムで紹介されることに。
「小さいときから本を読むことがすごく好きで、何かを書くということに対して憧憬を抱いていました。人生の中でそれがひとつでも形になれば、そんな幸せなことはないなと。でもまさかエッセイを書くとは思いませんでした。書くとしたら、なんとなくフィクションかなと思っていたので」
日記は1回につき4〜7ページ。これが掌編小説のように面白い。ティーンばかりの語学学校で最初は浮きまくっていた31歳の女性が、中学生以下の英語レベルのクラスからやがて大学生ばりにアカデミックなクラスに進級していき、映画好きが高じてウィスコンシン大学の映画の授業をゲストで聴講するまでに。まさしく、ビルドゥング・ストーリー(教養小説)。
「頑張って勉強して英語も話せるようになってきて、少しずつ自信がついて殻を破れるようになった気がします。タフになっていきましたね。大学の映画の授業はネイティブの英語だったので聞き取りに苦労しました。周りの学生が咳ばらいをするのも腹が立つくらい真剣でしたね(笑)」
一方、語学学校ではお洒落で愛嬌のあるサウジアラビア人、日本文化にやたら詳しい中国人、軽薄そうで実は真摯な一面を持つコロンビア人などの学友たちと異文化交流。次々と綴られる発見は、読み手の色眼鏡をも落としまくる。
「何か発見があったら、いったん心の中に留めておいて、しばらくして何か別のことと繋がったとき、日記に書いていました。ランニング中にふっと物事が繋がって、慌てて家に帰って書くことも」
この夏から再びウィスコンシンへ。第2弾の日記が待ち遠しい。

幻冬舎 1,500円
『クロワッサン』982号より
広告