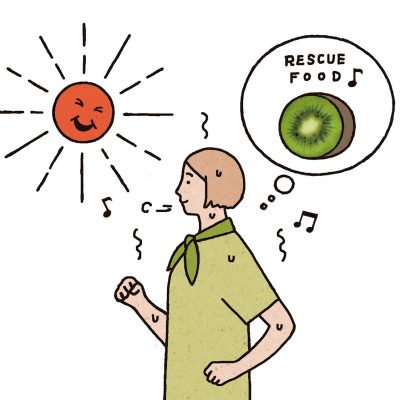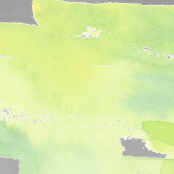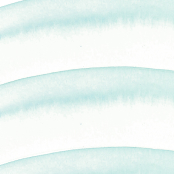『父「永六輔」を看取る』永 千絵さん|本を読んで、会いたくなって。
父は病気でも上を向いている人だった。

撮影・青木和義
「六輔のことは書けないけれど、孝雄(永さんの本名)のことは書けると思ったんです」
昭和を代表する才人、永六輔さんが亡くなって1年あまり。長女の千絵さんが記した本書は、六輔さんがパーキンソン病を患い、その後、大腿骨骨折。リハビリを懸命にする中で入退院をくり返し、最期は自宅で看取るまでの10年間の介護の日々を綴る。冒頭の言葉どおり、そこには家族しか知り得ない六輔さんの素顔が垣間見える。
「当時は父がラジオで病気のことを話すのをドキドキしながら聞いていました。ただ今思えば父は番組で“ぼくはパーキンソンのキーパーソン”とか言いながら楽しんでいた気がします。基本的にはどんなときもずっと上を向いている人だったんだと思うんです」
“病院は嫌いだけれど、先生と話すのは好き”“MRI検査を逃亡、その後の再診では涙目になっている”“手や顔を洗わない”など紹介されるエピソードは思わず笑ってしまうものも多い。
「子どもっぽいといえば子どもそのもの。嫌なことは嫌なんです。そのうえ、どうでもいいと思えることでも『なんで』『どうして』とそれこそ重箱のすみをつつくように尋ねてくる。好奇心のかたまりでした。私や家族、それにヘルパーさんやナースさんが井戸端会議ならぬ床端会議をしているときも、その中からネタ探しをしていましたね(笑)」
介護認定を受ける際の手続きの煩雑さや、実際に“在宅”を選んでからの夜中の体位変えや、身の回りの世話のことなど、千絵さんが体験した介護の現場を記す章は、身につまされる。
「嫌いな薬を飲ませるときに説得するのがすごく嫌でしたね。父も私に怒鳴られてまで寿命を延ばしたくはなかったように思うんです。今でも“薬飲まなくていいよ”と言ったらなんと答えたのかと考えます。“ホント!”と喜んだのか、“あなたが困るでしょ”と言って飲んでくれたのかな、と」
在宅介護にして3カ月になろうとした頃、六輔さんは息をひきとる。前日の夜には妹の麻理さんと親子3人でニュースを見てアイスキャンディを食べて、慣れないするめをしゃぶったりしながらいろいろな話をした後だった。
「介護と書きましたが、父のおかげでそう言うのが申し訳ないほど楽しかった。子どもの頃はまったく家にいなかった父と濃密な時間も過ごせて、私にとっては父に“ありがとう”という気持ちです」

宝島社 1,300円