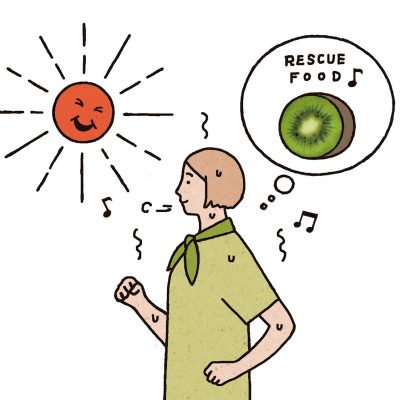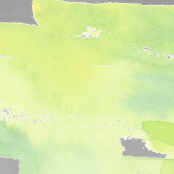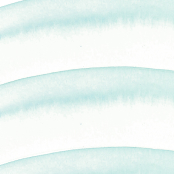『spring』著者、恩田 陸さんインタビュー。「多様な才能のあり方、引き出し方がある」
撮影・森山祐子 文・合川翔子(編集部)
「多様な才能のあり方、引き出し方がある」

舞台芸術を愛する恩田陸さんが新たに挑んだテーマは“バレエ”。
「私は怠け者なので、ハードルを上げないと縮小再生産になるという自覚があって。これまで芝居、ピアノときて、さらに難しい主題となるとバレエかなと思いました」
8歳でバレエに出合った主人公の少年・萬春は、15歳でドイツのバレエ学校に留学する。この世の森羅万象を踊りで表現したいという欲求を抱き、ダンサー兼振付家としてその才能を開花させていく。
恩田さんは取材を重ねるにつれ、バレエの世界に魅了されていった。
「パリのオペラ座バレエ団は定年が42歳。どんなに鍛錬しても長くは踊れない。常に怪我の危険と隣り合わせで、成長過程のその時分でしか表現できない踊りもある。そこが残酷であり、美しいところ。極限の刹那の芸術だと思います」
王子、妖精、ゲイの男性……。両性具有的な美しさをもつ春は、ダンサーとして、時に野性的に、時に妖艶に、役を拡張させていく。そして、振付家として、踊り手の恐れや悲嘆といった心情を見抜き、振付に昇華させていく。ページを捲るごとに、春が踊る姿や手がけた演目の壮大な世界が躍動的に脳内に立ち上がり、会場にいるかのような臨場感に包まれる。
「卓越したダンサーは体を通して役にコミットしているので、振付家より振付を理解し、どんどんその役を育てていく。一方、優れた振付は、立体的で情報量が多く、何か考えさせられるものがある。そんな実感を春に投影しました」
春は、今まで恩田さんが書いた主人公で一番惹かれた人物だという。
「人物設定を細かく決めないので、書いていって、しゃべらせてみないとどんな人かわからない。春は、クリエイティビティには貪欲だけど、けっこういいかげんなところがあって。想像以上に面白い人でした」
ふと自分と重なり、胸をつかれる時がある。
バレエ学校で共に過ごした深津、春の叔父・稔、春と協働で演目を手がける作曲家の七瀬、そして春本人と、本書は章ごとに違う視点で「春」という人物が語られる。
「育てる才能、影響を与える才能、共感する才能、多様な才能のあり方、引き出し方がある。物理的な春の才能と、彼らの精神的な才能が影響し合うことで、何が生まれるのか、そこを掘り下げたいと思いました。ずっと才能の発露の仕方に興味があって。だから、野球のコーチやスカウトマンが書いた本を読むのが好きなんです(笑)」
本書を書き終えてもなお、恩田さんのバレエへの情熱は尽きない。
「だいたいは、かっこいい!きれい!と言って観賞するんですけど、時々ふと自分と重なり、胸をつかれる瞬間がある。舞台の上で代わりに踊ってくれて、生き直す自分を観ているような感覚になるんです。こういう瞬間のためにバレエを観ているんだなと思います」
美しくも残酷な世界で命を燃やす人々の姿に、私たちはどんな感情を抱くのか。この一冊を通して、その余韻を存分に味わいたい。

『クロワッサン』1114号より