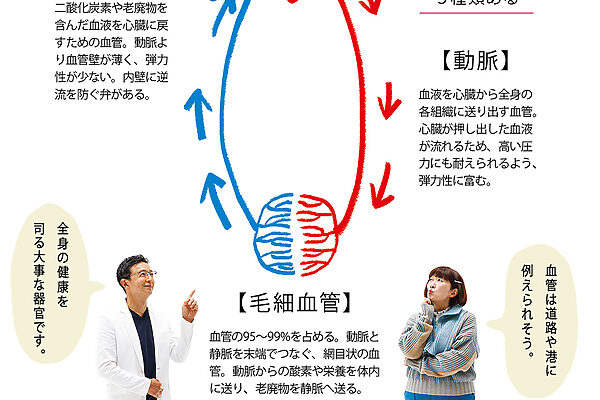『名探偵の生まれる夜 大正謎百景』著者、青柳碧人さんインタビュー。「日本人が自発的に自由を推進した大正時代」
撮影・岩本慶三 文・中條裕子
「日本人が自発的に自由を推進した大正時代」

「大正って、デモクラシーに象徴されるように、日本人が借り物ではない自由を自分たちで始めた時代なのだと思っていて。漠然とした憧れは昔からあったんです」
そう語る、青柳碧人さんの新作は、大正時代に活躍した個性豊かな人物たちが交錯する8つの物語集で成っている。
そこにはちょっとした謎が横たわり、時に事件が起こることも。誰もが知る人、知る人ぞ知る人……大正という時代に実在した人物たちが動き回り、語り、笑い、嘆き、生き生きと蘇った。
登場するのは、江戸川乱歩、芥川龍之介といった作家たちから、歌人の与謝野晶子、女優の松井須磨子、野口英世に南方熊楠といった学者まで多彩な面々。この短い時代にこれだけの才、個性が集っていたというのがまず驚きだ。
「震災や戦争、スペイン風邪の流行などが15年という短い間にあった時代。その明るい面を描きたかったというのもある。日本人全体が学生だった、そんな時代なのかもしれないな、とも感じます」
実在の人物たちが登場するだけに、当時の資料を読み込んで齟齬のないよう、けれど想像もまた存分に羽ばたかせて、とその絶妙な塩梅がなんとも魅惑的な世界を生み出している。中でも、資料を読んでそのイメージが変わった人物について聞いてみると……。
「渋谷のハチ公にまつわる話で、その飼い主である帝大教授の上野英三郎について調べていたら、週一で駒込に山手線で通っていたんですね。ハチが改札で待ってたのはその時だけ。それ以外は自宅のある渋谷から職場の駒場まで英三郎は歩いて通っていたので。でも、ハチをいつも教室まで連れて行ってたらしいんですよ。当時学生として授業を受けた人の手記に『先生は犬を連れてくるから初めはみんなびっくりする』とあって。ハチが学生たちのアイドルだった、というのには驚きましたね」
と、笑いながらなんとも微笑ましいエピソードを教えてくれた。そんな上野英三郎とハチがいったいどんな事件に巻き込まれてしまったのかは、読んでのお楽しみ。
数十年の時を経て巡り合う、人々が織りなす最終話。
そんな一つ一つの物語は、横にもまた繋がり、新たな一編が紡がれていく。
8番目の「姉さま人形八景」では、紙でできた姉さま人形を巡り、それまで語られてきた人々が数十年の時を経て巡り合い、つながっていく不思議に満ちた最終話となっている。
そこには主人公としてクローズアップされた者だけでなく、物語を傍でそっと支えた愛すべき面々もまた顔を出す。多くの者たちが登場するからこそ、時に共感を覚えたり反発したり。どの人物に肩入れするかも、おもしろいところ。
時代ならではの空気感に、時代を経ても変わらぬ心情、そして日常にふと入り込んでくるちょっとした不思議や謎。どの方面から楽しむかは、まさに読み手次第。一編ずつは短くとも、読み応えも余韻もまた、たっぷりな一冊なのだ。

『クロワッサン』1088号より
広告