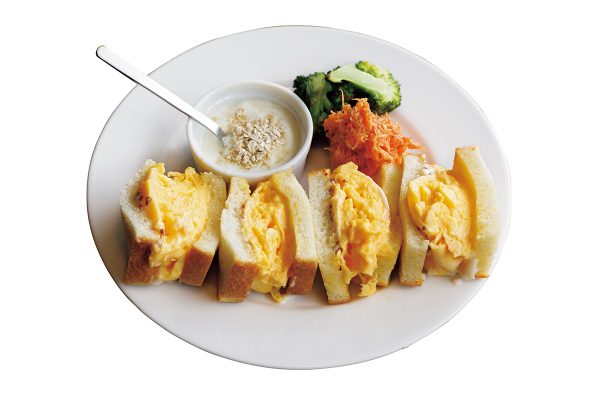「この言葉を推進力にすれば、あらすじというものがなくても何かが書けるのではと思いました」
『点滅するものの革命』著者、平沢 逸さんインタビュー。「無意味の先にあるものをあらわしたかった」
- 撮影・谷 尚樹 文・堀越和幸
「無意味の先にあるものをあらわしたかった」

主人公の「わたし」、ちーちゃんは5歳の女の子である。ちーちゃんは父ちゃんと二人暮らしで、父ちゃんは毎日多摩川の河川敷に繰り出し、一日中草を刈ったり穴を掘ったりしている。未解決事件の報奨金目当てに、使われた拳銃を探し出そうとしているからだ。
第65回群像新人賞を受賞した平沢逸さんの本作はそんな設定の小説だ。そしてその設定は読み進めていっても大きな変化を迎えることはない。ただ、何となくそこに集う雀荘のママや、掘っ立て小屋の住人や、失恋を引きずる大学生の姿がまるで定点カメラのように捉えられていくのである。
「小説を書くきっかけは冒頭にある、〝暁は数じゃない、量だ〟という言葉が頭に浮かんだからです」
それは5歳のちーちゃんが早朝の土手で遭遇する世界の感触だ。
音楽の音に意味はあるか?
作家の町田康さんは本作をこう評した。何の意味もない人間が集まって、意味もない言葉を発するという、私たちが普段やっていることをそのまま描いて面白いという稀有な作品(本の帯から抜粋)。
ところで、小説における意味とは何なのか?
「テーマがあって現代社会に相通じるという小説もたくさんあると思いますが、一方で自分は意味と無意味が区別なくとけあわさったような先に見えるものとは何か、という思いでこれを書き進めました。無意味の豊饒を目指すと言いますか」
スコップや鎌を携えて日々同じ行為を繰り返す父ちゃんはまさにそのシンボル的な存在だろう。
「父ちゃんは奇跡みたいな人だと思います。はたから見れば同じ繰り返しにしか見えないことも、彼にとってはきっとそうではない。同じ日など一日も存在しない、ということを心の底から感じられる人間なのではないでしょうか」
定点で据えた世界の中で、多摩川周辺の描写が美しい。空に浮かぶ雲の群れ、色の移ろい、川面に揺れる光、高架橋を轟かす電車の音、地面の木漏れ日……。
「風景をたくさん書いたのは、風景を見る行為自体が、その人にとっての喜びだと思うからです」
どういうことか?
「人は言葉を駆使して頭の中でいろいろ考えますが、何か煮詰まったりすると、散歩なんかで思考が前に進んだりすることがありますよね。言葉とか意味とかだけに頼るのではなく、そうして人間は物事を考えているのではないか」
無意味の先にある無意味の豊饒とは、平沢さんにとって音楽のようなイメージでもある。
「素敵だなと思うメロディーを聴いて、この音はどんな意味か? って、いちいち考えませんよね。それが小説でできたら、と」
10代の頃は文学少年というよりは音楽少年だった。次作が楽しみな、新しい才能があらわれた。

『クロワッサン』1081号より

この記事が気に入ったらいいね!&フォローしよう
※ 記事中の商品価格は、特に表記がない場合は税込価格です。ただしクロワッサン1043号以前から転載した記事に関しては、本体のみ(税抜き)の価格となります。
人気記事ランキング
- 最新
- 週間
- 月間